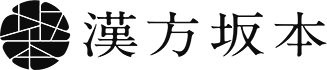□自己免疫疾患・アレルギー性疾患
~原因不明の炎症・その漢方治療~
<目次>
■ステロイドで収まらない炎症 ~自己免疫疾患やアレルギー性疾患治療の難しさ~
■原因不明の炎症性疾患・今までの概念では充分に対応できていないという現実
■『傷寒論』で論じられている炎症の特徴
■長期化する炎症に対する本国での試行錯誤
1.「温清飲」という解答
2.「柴胡剤」という解答
■勢いを弱めない炎症像に対する新しい解答・『温病条弁』
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ステロイドで収まらない炎症 ~自己免疫疾患やアレルギー性疾患治療の難しさ~
現代では原因不明の炎症を生じる病が数多く存在しています。アトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患や、乾癬などの皮膚の病、そして関節リウマチなどの自己免疫疾患、また潰瘍性大腸炎やクローン病などがこれに属しています。
何故炎症が起こってしまうのか、これらの疾患ではその原因が未だ不明であるため、とにかく炎症を抑えるという対症療法が主として行われています。根本治療が難しいことから一度改善をみてもその後に悪化を繰り返すという経過をたどりがちで、さらに炎症がおさまらない場合はステロイドといった強力な炎症止めを長期にわたって用いる必要があります。
根本治療が難しく、ステロイドの副作用が危惧されることからも、治療が難しい病という印象が持たれています。
■原因不明の炎症性疾患・今までの概念では充分に対応できていないという現実
日本でもこれらの疾患に対して、昭和時代の漢方家が多くの治験を残してきました。ただし漢方の歴史から見てもこれらは新しい病に属しているため、その治療は試行錯誤の連続でした。そして現在でもその傾向は継続し、漢方家によってその治療方法は様々であるという現実があります。
自身の経験としては、このような原因不明の炎症性疾患に対して昔から行われ続けている治療法、つまり昭和時代から繰り返し行われてきた治療方法では、その治療成績に限界があると感じています。西洋医学的な炎症という概念に捉われ、東洋医学的に炎症をどう捉えるかという考察が未だ十分になされていないことが、その大きな要因の一つだと考えています。
そこで、ここでは原因不明の炎症性疾患に対して、今まで漢方はどのように対応してきたのか、そして今後どのように対応するべきなのかということを、一つの見解として解説していきたいと思います。
■『傷寒論』で論じられている炎症の特徴
歴史的にみれば、日本は今まで炎症を抑える手法を『傷寒論(しょうかんろん)』という書物から導き出してきました。「傷寒」とは風邪のような感染症を主体とした病態を指しています。傷寒はその名の通り先ず「寒」という刺激ありきで始まる病態ですが、そこから病化することで「熱」を生みます。この「熱」は今日でいうところの炎症という現象を包括していると考えられていることから、「傷寒」の治法を論じた『傷寒論』を研究することで炎症性疾患に今まで対応してきました。
傷寒という病態は大きく2編に分かれます。一つを「陽病(ようびょう)」といいます。生体に抗病力が未だあり強く炎症を起こすことが可能な病態です。もう一つは「陰病(いんびょう)」といいます。これは逆に生体の新陳代謝が衰え、体力がなく炎症を強く起こせなくなり炎症を鎮める力も失っていく病態です。『傷寒論』では陽から陰へという病の流れがその理論の大枠をなしています。したがって傷寒論での炎症は、長期化する場合には必ず活発な状態から沈静化した状態へと向かっていきます。
今日の炎症性疾患にも当然そのような傾向があります。つまり始め活発に生じた炎症は、時間が経つにつれて落ち着いてくる傾向があります。しかし原因不明とされる炎症性疾患では、炎症が沈静化しきれず、ある程度の活発さを保ったまま炎症が長期化していく傾向があります。炎症が長引き、出血などによって貧血へと陥り、体力を失ってもなお炎症に力がある状態。これがいったい如何なる病態なのか、この点に関しては今までの『傷寒論』の解釈では明確な回答が導き出されてきませんでした。そして、これがそのまま原因不明の炎症性疾患に対する治療の難しさとなって、今までのやり方に限界を持たせているといえます。
■長期化する炎症に対する本国での試行錯誤
大正・昭和・平成と時代が進むにつれて、原因不明の炎症性疾患が本国において増加してきました。そして『傷寒論』の手法ではこれらの疾患に対応しきれないという現実に、昭和の漢方家たちは何度も直面することになります。その中で様々な試行錯誤を繰り返し、これらに対応する考え方を次々と提示してきました。その努力の結晶は、現在頻用されている手法の原型を形作っています。有名なものを2つ上げてみましょう。
1.「温清飲」という解答
有名な手段の一つが「温清飲(うんせいいん)」という処方を用いる手法です。温清飲はもともとは血崩(けつほう)と呼ばれる大量の不正性器出血に対して用いられていた処方です。そして熱(炎症)を冷ます「黄連解毒湯(おうれんげどくとう)」と血行を促す「四物湯(しもつとう)」とを合わせた構成を持ちます。昭和時代の漢方家たちは、本方が黄連解毒湯という炎症を抑える処方を内包しているという点に注目します。そして「炎症を鎮めつつ、組織の血行を促して病巣を消失させる」という考え方のもと、慢性的に継続する炎症性疾患に広く応用するようになりました。
この手法が最も頻用されているのは、アトピー性皮膚炎や乾癬などの皮膚の病です。温清飲加荊芥連翹(うんせいいんかけいがいれんぎょう)などといった加減を施したり、一貫堂と呼ばれる流派が好んで用いた柴胡清肝散(さいこせいかんさん)や荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)などを用いることで対応してきました。しかしアトピー性皮膚炎や乾癬においては、これらの手法をいくら用いても充分な効果を発揮することができないという現実があります。
本来炎症を起こした病巣は、時間経過とともにその炎症が落ち着いた場合、炎症によって破壊された組織が後に残ります。温清飲運用の本筋は、この状況に対応させるという考え方の上に成り立っています。すなわち、炎症が強い状況では黄連解毒湯を主として清熱させ、炎症が治まった後は四物湯をもって組織の修復を強めるという考え方です。温清飲はこの両者を包括して行い得る方剤として注目されましたが、本方の適応病態はあくまで「炎症が落ち着く」という状態が前提となっている点に注意しなければなりません。
すなわち温清飲は「活発な状態から沈静化した状態へと向かっていく」という炎症像に対応するための手法であり、あくまで『傷寒論』にて述べられている治療方法の延長線上にあります。「いつまでも沈静化しきれず、ある程度の活発さを保ったまま長期化していく」というアトピー性皮膚炎や乾癬に対しては、十分な解答が出せているとは言い難いのです。
2.「柴胡剤」という解答
原因不明の炎症性疾患に対して、比較的最近になって頻用されているのが「柴胡剤(さいこざい)」です。特に「柴苓湯(さいれいとう)」という処方や「柴朴湯(さいぼくとう)」という処方がステロイド治療とよく平行して用いられています。自己免疫異常が指摘されている潰瘍性大腸炎やクローン病などにおいては、柴苓湯エキス顆粒剤が頻用されているようです。そして柴朴湯エキス顆粒剤は気管支喘息治療において頻用されている有名処方です。
慢性経過する炎症性疾患に柴胡剤を用いるという手法は古くから行われてきました。柴苓湯や柴朴湯は「小柴胡湯(しょうさいことう)」という『傷寒論』にて提示されている処方が基礎となっています。小柴胡湯は少陽病(しょうようびょう)という炎症の亜急性期から慢性期にかけて発現してくる病態に適応する処方です。そういう考え方を根拠として、慢性化している炎症に対しては小柴胡湯を基本とするという手法が古くから行われてきました。
しかし先述のように、いくら『傷寒論』の考え方から紐解いたとしても「活発さを保ったまま長期化してくる炎症」に対しては充分に対応することが出来ません。実際に柴胡剤をいくら自己免疫疾患に応用したとしても、これらの処方にて炎症を抑えることは困難です。原因不明の炎症性疾患に柴胡剤が使用される場合、消炎作用はそれほど期待されていないというのが現実です。例えば柴苓湯を使う目的はあくまで西洋医学的治療への補佐です。西洋薬による肝機能障害とステロイドからくるむくみなどの副作用を予防する目的で使用されている傾向があります。また柴朴湯に関してもあくまで気管支喘息の寛解期に用いる方剤です。つまり喘鳴が生じるほどの炎症が強い状態を消炎させる効果は期待されておらず、喘鳴が落ち着いた後に気道に浮腫や緊張が生じにくい状態を形成していくという段階においてはじめて効果を期待されて用いられています。
このように、本国においては原因不明の炎症性疾患に対する試行錯誤が繰り返されてきました。特に昭和時代に編み出されてきた手法は今でもその基本として用いられ続けています。しかし現実的には未だ十分に効果を発揮し得るものとは言い難く、さらなる研究の余地を多く残しているというのが正直な所です。これらの治療はあくまで『傷寒論』の考え方を基礎してい派生しています。『傷寒論』の手法を理解しながらも、これに縛られない次なる一手がこれからの時代に求められています。
■勢いを弱めない炎症像に対する新しい解答・『温病条弁』
次なる一手、その一端を担う考え方は、実はすでに存在しています。『温病条弁(うんびょうじょうべん)』。日本ではあまり認知されていない書物ではありますが、一部の漢方家たちはすでにこの書物の考え方に着目しています。
『温病条弁』とは本国において盛んに『傷寒論』研究が進んでいた時代、お隣中国において記されていた書物です。中国では清代において「温病(うんびょう)」という病態が考察されました。そして呉鞠通(ごきくつう)という人物によってそれが体系化され、『温病条弁』が著されます。この本は傷寒論の理論を踏襲しながらも「寒」ではなく「熱」刺激によって病態がどのように推移していくかという見解を示したものです。要するに、身体を灼焼し続ける熱(炎症)に対して、どのように対応していくのかという理論を打ち出しています。この見解は傷寒論の理論を補完する意味でも重要ですが、同時にアレルギー疾患や自己免疫疾患など、原因不明とされる炎症性疾患治療に非常に重要なアイデアを示唆しています。
昭和漢方が隆盛を極めんとする時、隣国中国の書物がなかなか入ってこないという時代の影響を受けて、本国ではこの書物の研究が遅れてしまいました。そして当時の昭和漢方家たちが現在の保険漢方を作り上げたため、「温病」の思想は広がりを見せることが出来ませんでした。現在、日本においてはその流れが未だに続いています。銀翹散(ぎんぎょうさん)など一部の処方が運用されているに過ぎず、暑温(しょおん)・伏暑(ふくしょ)・湿温(しつおん)といった重要病態に対しては、依然としてその考え方が広まっていないというのが現状です。
『傷寒論』は漢方において基本中の基本であり、漢方家にとってこの書の読解は終わることのない責務といえるでしょう。しかし同様に今まで培われてこなかった理論に対しても広く目をむけ、時代とともに変化していく病に対応しつづける努力もまた必要です。とりわけこの「温病」という概念は本国において軽視されてきた傾向があります。現代の臨床においては必ず知る必要のある理論であり、特にアトピー性皮膚炎や関節リウマチなどではその必要性を強く感じます。
・
・
・
■病名別解説:「関節リウマチ」
■病名別解説:「アトピー性皮膚炎」
■病名別解説:「乾癬・尋常性乾癬」
■病名別解説:「クローン病」
■病名別解説:「潰瘍性大腸炎」