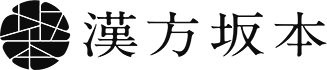非結核性抗酸菌症(肺MAC症)について
明治時代から昭和20年代にかけて、日本では結核が大流行し、「亡国病」と呼ばれるほど高い蔓延状態が起こりました。時代が進むにつれて効果の良い薬剤が開発され羅患率は減少してきました。しかし現在これと反して増加傾向にある病があります。「非結核性抗酸菌症(ひけっかくせいこうさんきんしょう)」です。
あまり聞かない名の病ですが、実はお困りの方が多い疾患です。また比較的近年になって増えてきた病であるだけに、その診断方法や治療方法は未だ模索の段階にあります。しかし私見では漢方治療によって改善を見るケースが多い疾患です。したがってここでは本疾患にお困りの方のために、漢方治療の実際の所をやや詳しく解説していこうと思います。
非結核性抗酸菌症とは
非結核性抗酸菌症は、結核菌以外の抗酸菌(非結核性抗酸菌(NTM))が感染して起こる病です。主に肺に感染し、咳や痰などの症状を発生させます。近年世界的に増加傾向にあり、日本では非結核性抗酸菌の中でもM.avium complex(MAC)が起因菌として最も頻度が高い(80%)ため、「肺MAC症」と呼ばれることもあります。またカンサシ菌など他の抗酸菌によって起こる場合もあります。
これらの菌は土や水などの環境中にいる菌です。感染力が強いわけでもなく、人に感染がうつるわけでもありません。多くが慢性肉芽腫性病変(※)といって、免疫機能の減弱を伴いながら進行していきます。患者さん自身の弱さに起因して、本疾患が発症してしまうという印象があります。
※免疫の役割を担う白血球(好中球)が、病原体への殺菌を行なえなくなる病を慢性肉芽腫症という。好中球による活性酸素の産生が行われなくなることによる。免疫機能が減弱するため感染にかかりやすくなる。
・症状
色々なタイプの非結核性抗酸菌症が存在しますが、多くは数年から10数年かけてゆっくりと進行していくという特徴があります。劇的な症状を起こすことは比較的少なく、特徴的な症状があまりありません。咳・痰・血痰・だるさ・発熱・寝汗・体重減少などを起こすことがありますが、症状がない、ということもあります。したがって病院で検査をしてみて初めて指摘された、という方も多くいらっしゃいます。
・病型と特徴
数種の病型がありますが、特に以下の2つが有名です。
〇「線維空洞型(結核類似型)」
男性に好発し、もともと肺疾患(陳旧性肺結核症・塵肺症・COPD・排泄所や胸郭形成手術後・気管支拡張症・肺線維症など)を持つ方で多く見られます。結核と同様に画像で確認すると肺尖や上肺野中心に空洞が多発していることが特徴で、一般的に予後の悪いことで知られています。多くが進行性で、その場合診断されれば直ちに化学療法の適応となります。手術の適応となることもあります。
〇「小結節・気管支拡張型」
肺に器質的障害を持たない痩身の中高年女性に多く見られます。病勢はさまざまで、進行しているものから、進行を認めないものもあります。病の進行が緩徐なため経過観察にて様子を見るというケースも多く、治療開始時期は症状と画像所見に応じて決定されます。
・診断と西洋医学的治療
非結核性抗酸菌症の診断は難しいケースが多く、症状・画像所見・組織所見だけでは結核と鑑別できません(結核は人から人へと感染するため鑑別が非常に重要です)。したがって起因菌を同定することが必要で、主に喀痰にて数回にわたり検査されます。
MAC菌が原因の場合で、かつ症状や肺の画像所見が悪化してくる場合には、3剤併用の化学療法が行われます。クラリスロマイシンと抗結核薬2種類(リファンピシン・エタンブトール)の内服治療です。少なくとも一年半(菌が培養されなくなってから1年間)は毎日継続します。しかし菌が完全に消えることはまれです。そして再発すれば治療を再開します。
治療終了後の再発は頻繁に認められています。また継続する化学療法によって食欲がなくなり体重が減少するなどの体調不良を起こす方もいます。さらに視力障害や肝障害・発疹などの副作用が起こることもあります。そのため最適化学療法期間の設定は今後の課題となっています。またこれらの化学療法に耐性を示すことがあり、そうなると治療は非常に困難になります。
非結核性抗酸菌症と漢方
症状が顕在化しにくく緩徐に進行するという穏やかな病状を呈しやすい一方で、その治療となると難しく、完全に治し切ることが困難であるというのが本疾患の特徴です。そもそも原因菌の増殖が早ければ早いほど、抗菌剤による効果が高く発揮されます。したがって菌の増殖が非常に緩やかな本疾患では、抗菌剤の効果が出にくくなります。
このような病に対して、漢方では西洋医学にはない角度から治療を行うことが可能です。それが本疾患において漢方治療をお勧めできる理由です。この理由を説明するためには、感染症という病態が総じてどのように治療されるかを説明する必要があります。
●「感染」に対する漢方的解釈
感染症には大きく2つの状況が考えられます。
もともと体力があり元気な方でも、感染性の強い菌やウィルスに侵されれば誰しもが感染症を発症します。このような状況では真っ先に毒性の強い菌やウィルスを抑制させることが重要です。そのため、これらの原因に直接効果を発揮することのできる西洋医学は理にかなった治療であり、非常に優れた効果を発揮します。抗菌剤や抗ウィルス剤の登場により、以前は致死的と言われた感染症が回復可能になった歴史的事実から考えても、この恩恵はすばらしいものです。
一方で、感染症にはもう一つの状況が考えれます。菌自体にはそれほど感染力はない。体力・免疫力がある方であれば特に問題となるような菌ではない。しかし体に弱さがあり、そのために免疫力が衰えて、このような弱い菌にまで感染を起こしてしますケースです。体力の無い方、何らかの消耗性疾患にお罹りの方、またご高齢者などに起こりやすい状況です。そして非結核性抗酸菌症はこのようなケースの感染症に属しています。
●非結核性抗酸菌症・弱い菌にまで感染してしまう病
このケースで問題となるのは、いくら原因となる菌を抑制しても病が完治に至らないという点です。すべての感染症で言えることですが、菌が抑制されたとしても最終的に完治にまで至るための根本的な力は、自身が持っている体力に依存しています。平素より体力のある方では、菌さえ抑制させれば自らの力で完治に至ることが可能です。しかし、体力の無い方ではこの力が発揮できないため、いつまでも感染を長引かせて、体力を消耗させつづけます。
したがってこのようなケースでは西洋医学的治療が非常に難しくなります。体力・免疫力という身体の力を評価できる明確な基準がありませんし、これらを鼓舞するための手法も未だ研究段階にあります。ご高齢者の死亡率の上位にはいつも肺炎がありますが、これは感染に対する体力の鼓舞が難しいという西洋医学的治療の弱点をこの病が突くからです。
●体側の弱さを回復させる治療
体力を鼓舞する、免疫力を高める、そして菌に対して犯されにくい体側の状況を作る、このような治療に関しては漢方治療が最も優れていると思います。そもそも感染症における漢方治療は、体側の状態を調節することで菌やウィルスを排除しやすい状況を作るというのが原則です。この原則は今も昔も変わっていません。西洋薬に変わる抗生剤のようなものがあるわけではなく、ただ愚直に長い歴史の中でこの手法を培ってきました。それ故、漢方にはどの程度菌と闘う力を持っているのかを測る経験則や、実際に力を高め引き出すための治療方法がたくさん存在します。
非結核性抗酸菌症はこれらの手法を用いることで、改善に導くことが可能です。感染症のベースとなる治療になりますので、化学療法が出来ず経過観察中の方や、化学療法が副作用のために出来ない方、また化学療法を行っても効果が無いといった方であれば、尚更お勧めすることができます。多くが体力の底上げをする治療になります。したがってある程度長く服用することは必要でしょう。ただし咳や痰・血痰・微熱などの症状のみならず、疲労感や食欲不振・不眠などからだ全体の回復を実感しながら治療を進めていくことが可能です。
参考コラム
まずは「非結核性抗酸菌症」に対する漢方治療を解説するにあたって、参考にしていただきたいコラムをご紹介いたします。本項の解説と合わせてお読み頂くと、漢方治療がさらにイメージしやすくなると思います。
コラム|漢方治療の経験談「非結核性抗酸菌症治療」を通して
当薬局でもご相談の多い非結核性抗酸菌症。日々治療を経験させていただいている中で、実感として思うこと、感じたことを徒然とつぶやいたコラムです。
使用されやすい漢方処方
①麦門冬湯(ばくもんどうとう)
竹葉石膏湯(ちくようせっこうとう)
②人参飲子(にんじんいんし)
③滋陰至宝湯(じいんしほうとう)
④柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう)
⑤肺傷湯(はいしょうとう)
⑥清肺湯(せいはいとう)
⑦葦茎湯(いけいとう)
肺癰湯(はいようとう)
⑧肺癰神湯(はいようしんとう)
外台・桔梗湯(げだいききょうとう)
⑨人参養栄湯(にんじんようえいとう)
黄耆建中湯(おうぎけんちゅうとう)
⑩四君子湯(しくんしとう)
六君子湯(りっくんしとう)
⑪通導散(つうどうさん)
※薬局製剤以外の処方も含む
①麦門冬湯(金匱要略)竹葉石膏湯(傷寒論)
微弱な炎症を長期的に継続させる肺疾患では、肺粘膜の潤いが失われて防御機能が弱まる。いつまでも空咳が続き、一度咳をしだすと止まず、最後にはオエっと胃が持ち上がるような強い咳き込みを生じることがある。麦門冬湯は「大逆上気」と呼ばれるこのような咳に効果を発揮する方剤。非結核性抗酸菌症において咳き込みがいつまでも止まないという状況で用いる場がある。
竹葉石膏湯は麦門冬湯に構成生薬が似る。潤いをつけることで肺気を正す方剤である。ただし竹葉石膏湯は微熱などを介在させる感染症の亜急性期から慢性期において用いる。全身の興奮状態が継続し、熱が津液(潤い)を灼焼している状況において運用する方剤である。麦門冬湯は雑病。竹葉石膏湯は傷寒。似た処方といえどもその適応には明らかな差がある。非結核性抗酸菌症の適応処方として双方とも有名ではあるが、あくまで一時的な症状を改善するための薬方と考えた方がよい。本質的な治療を行うためには他剤に変えるか合方することで対応する必要がある。
長期的な熱を生じて肺の潤いを消耗させていく疾患を古人は「肺痿(はいい)」と呼んだ。そして骨を蒸すような発熱により身体の潤いを消耗していく状態を「骨蒸(こつじょう)」と呼んだ。古人はこれらの病態に対して麦門冬湯や竹葉石膏湯を用いるも、数種の加減を行うことでこれに対応してきた。骨蒸の初期、浅田宗伯は竹葉石膏湯の変方である五蒸湯(ごじょうとう)を用いた。身体の奥底にくすぶる熱と汗とを生じるような状況で用いる方剤である。非結核性抗酸菌症においてこのような熱を生じ続けることは比較的まれではあるが、微熱を発する病態への対応として知っておくべき手段である。
麦門冬湯:「構成」
麦門冬(ばくもんどう):半夏(はんげ):大棗(たいそう):人参(にんじん):甘草(かんぞう):粳米(こうべい):
竹葉石膏湯:「構成」
麦門冬(ばくもんどう):半夏(はんげ):人参(にんじん):甘草(かんぞう):粳米(こうべい):竹葉(ちくよう):石膏(せっこう):
②人参飲子(備全古今十便良方)
小柴胡湯に竹葉と麦門冬とを加えた処方。総じて感染症の亜急性期から慢性期では、小柴胡湯などの柴胡剤を運用するべき時がある。微熱が続き食欲がなく、ややもすると吐き気をもよおして咳が止まない者。小柴胡湯は胃薬でもある。したがって胃腸の弱い者の消耗性の微熱に運用して良いケースがある。
人参飲子:「構成」
柴胡(さいこ):半夏(はんげ):黄芩(おうごん):人参(にんじん):甘草(かんぞう):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):麦門冬(ばくもんどう):竹葉(ちくよう):
③滋陰至宝湯(万病回春)
同じく柴胡剤として継続する微熱に対応する処方として逍遥散がある。特に婦人の更年期以降、内分泌や自律神経の働きを乱れていると、感染症を発しやすく、また治りにくくなる。そのような場において逍遥散およびその変方である滋陰至宝湯は、長引く感染症に広く応用されてきた。
『古今方彙』によると本方は脾胃(胃腸)を健やかにし、心肺を養い、咽喉を潤し、潮熱(夕方に高まる熱)を退け、骨蒸を除き、咳嗽を止める、とある。また『衆方規矩』の労嗽門にて曰く「案ずるに虚労・熱・嗽・汗ある者はこの湯に宜し。~婦人虚労寒熱するに逍遥散にて効なきときはこの湯を与えて数奇あり。」とある。つまり非結核性抗酸菌症において微熱が長引き咳が止まず、寝汗が出て潤いを失い、ある種の消耗状態へと陥っていく者。また更年期にさしかかる婦人にて咳などの症状はあまりないものの、鬱々として胃腸が弱い体質者の非結核性抗酸菌症に用いて良い場合がある。
滋陰至宝湯:「構成」
柴胡(さいこ):芍薬(しゃくやく):甘草(かんぞう):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):当帰(とうき):麦門冬(ばくもんどう):地骨皮(じこっぴ):知母(ちも):貝母(ばいも):陳皮(ちんぴ):香附子(こうぶし):薄荷(はっか):
④柴胡桂枝乾姜湯(傷寒論)
慢性経過する感染症において、微熱が続き身体の潤いが灼焼されて消耗状態を呈するような病を漢方では「骨蒸(こつじょう)」という。この骨蒸に対して、後世方派と呼ばれる流派は滋陰至宝湯を頻用し、その一方で古方派は柴胡桂枝乾姜湯を頻用していた。
本方は骨蒸の初期、つまり微熱が続き寝汗が出て身体羸痩する傾向あるも、未だ食欲の低下など胃腸機能には問題がないという段階で用いる方剤である。大塚敬節先生は結核に本方を応用する場合、黄耆を加えて用いていた。また動悸や不眠・のぼせて頭から汗をかくなどの自律神経の興奮状態を介在させている場合に運用することが多い。婦人の更年期において現れやすい病態であり、微熱や乾咳が続き、症状がなかなか止まないという非結核性抗酸菌症に良い。滋陰至宝湯に比べて適応すると即効性をもって微熱を止める傾向がある。ただし運用にはコツがある。広く用いられる処方というよりは、ピンポイントで適応者がいるという印象がある。
柴胡桂枝乾姜湯:「構成」
柴胡(さいこ):桂枝(けいし):乾姜(かんきょう):括呂根(かろこん):黄芩(おうごん):牡蛎(ぼれい):甘草(かんぞう):
⑤肺傷湯(千金翼方)
「肺痿」が長引くと、骨蒸のような微熱が起こらなくなる代わりに、津液・気血が失われて肺が損傷し、咳や喀血を起こすようになる。肺部の血行循環が乱れて疲労感を呈し、少し動いただけで咳をするようになる。本方はこのような長期慢性化した肺疾患に対して適応する方剤である。
浅田宗伯が「肺痿」の主方と評するように、肺部の血行循環を調え、進行する肺の損傷を回復・予防していく方意を持つ。したがって慢性的に肺に炎症を生じ、肺活動にダメージを与えつづけていく非結核性抗酸菌症においても応用し得る方剤である。また本方の他にも炙甘草湯を用いるケースもある。浅田宗伯曰く「此方は肺痿の主方にて、炙甘草湯に桔梗を加ふるのゆく処とよく似たり。ただし此方は咳嗽甚だしく咳血止まず、臥し得ざる者を主とす。炙甘草湯は、動悸甚だしく労嗽行動すること能わざる者を主とす。」
微熱や咳、喀血などを生じる非結核性抗酸菌症では、江戸時代に行われた「肺痿・骨蒸」の治療方針を知っておくべき時がある。詳しくは臨床の実際を参照してください。
肺傷湯:「構成」
人参(にんじん):阿膠(あきょう):炮姜(ほうきょう):桂枝(けいし):紫菀(しおん):桑白皮(そうはくひ):地黄(じおう):飴糖:
⑥清肺湯(万病回春)
非結核性抗酸菌症において痰を多く発生させて咳をする病態を「痰熱」と捉えて治療する場合がある。気管支拡張型や気管支拡張症を介在させる線維空洞型に多い。本方は比較的勢いの強い咳を発し、痰が黄や緑に色づくような熱傾向が強い場合の慢性炎症期に用いる方剤である。
浅田宗伯は「痰火咳嗽の薬なれども虚火の方に属す。もし痰火純実にして脈滑数なる者は、龔氏は括呂枳実湯を用ふるなり。肺熱ありて兎角咳の長引きたる者に宜し。」と本方の適応を解説している。虚火とは食欲不振や疲労倦怠感など、身体が虚状を呈している状態とは異なる。肺の炎症が長引き、肺部の潤いが失われて血行障害を呈する病態にて、清熱薬だけでは炎症をおさえることが出来なくなった状態を指す。非結核性抗酸菌症では真の虚証を呈することが多いため、本方の盲目的な運用は避けるべきである。
清肺湯:「構成」
桑白皮(そうはくひ):黄芩(おうごん):山梔子(さんしし):桔梗(ききょう):貝母(ばいも):枳実(きじつ):杏仁(きょうにん):茯苓(ぶくりょう):甘草(かんぞう):陳皮(ちんぴ):五味子(ごみし):当帰(とうき):
⑦葦茎湯(金匱要略)肺癰湯(原南陽経験方)
肺の感染によって化膿性炎症がおこり、臭気のある粘稠な痰を出す病態を「肺癰(はいよう)」という。やはり気管支拡張型や気管支拡張症・肺化膿症を介在させる線維空洞型に多く発生する。ぼこぼこと膿性の痰を喀出し、胸痛を起こしたり痰に血が混じる場合もある。抗菌剤が効きにくい場合であっても、漢方にて改善する例の多い病態である。
葦茎湯の主薬である葦茎(いけい)は芦根(ろこん)とも呼ばれ、肺の炎症を去る清熱薬である。そして薏苡仁・桃仁・冬瓜子をもって肺部のうっ血を除き、痰を排除する。肺化膿症において本方を核として様々な加減を行うことで広く運用できる名方である。特に四順湯(しじゅんとう:桔梗・貝母・紫菀・甘草)を合わせて排膿・止咳の効果を強める加減が良く行われる。急性炎症を経ず、徐々に進行して長期化する「肺癰」に適応する場が多い。
また肺癰湯は江戸時代の名医、原南陽により創作された方剤。浅田は肺癰初期に用いて特効ありと解説している。急性炎症期の後、やや炎症の勢いが沈静化するも、いつまでも膿性の痰が無くならないという場で用いる。浅田は炎症の程度が強く、微熱や寒気を呈して胸痛が強いようなら柴胡桔枳湯に蒂藶子を加えて運用している。
葦茎湯:「構成」
葦茎(いけい):薏苡仁(よくいにん):桃仁(とうにん):冬瓜子(とうがし):
肺癰湯:「構成」
桔梗(ききょう):杏仁(きょうにん):括呂根(かろこん):白芥子(はくがいし):貝母(ばいも):生姜(しょうきょう):甘草(かんぞう):
※浅田宗伯は生姜を黄芩に代えて用いている。
⑧肺癰神湯(医宗必読)桔梗湯(外台秘要方)
「肺癰」は肺に起こる化膿性炎症で、「癰(よう:おでき)」の治療に準じて改善を図る。「癰」は炎症が強ければ清熱解毒を主とするが、体力・免疫力が低下しいつまでも化膿を残存させてしまう段階では透托・補托を行う。「肺癰」においても透托・補托をもって対応するべき病態があり、その際に用いられる処方群がこれらの方剤である。
肺癰神湯は肺部の透托・補托に用いられる方剤である。浅田宗伯曰く「肺癰湯を用ひて効なく、虚憊咳血やまざる者に用ふ。」とあるように、清熱・排膿をしばらく行っても止まない膿痰に良い。いわゆる「癰」治療における千金内托散の段階で用いる方剤である。
外台の桔梗湯は同じく浅田が肺癰神湯より一等虚脱する者に良いと指摘する通り、より虚の傾向のある病態に運用するべき方剤である。「肺癰」が長引き、日を経て血気衰弱する者。参耆剤(人参・黄耆を含む方剤)と合わせて用いる手段もある。
肺癰神湯:「構成」
黄耆(おうぎ):桔梗(ききょう):薏苡仁(よくいにん):金銀花(きんぎんか):貝母(ばいも):陳皮(ちんぴ):蒂藶子(ていれきし):白朮(びゃくじゅつ):甘草(かんぞう):生姜(しょうきょう):
外台桔梗湯:「構成」
当帰(とうき):地黄(じおう):甘草(かんぞう):桔梗(ききょう):薏苡仁(よくいにん):敗醬根(はいしょうこん):桑白皮(そうはくひ):木香(もっこう):
⑨人参養栄湯(和剤局方)黄耆建中湯(金匱要略)
非結核性抗酸菌症は肺機能を徐々に減弱させていく疾患であるが、咳や痰などの症状を伴わない場合も多い。先に上げた処方群はあくまで症状が存在している状態に適応する。したがって症状が現れていない場合は、これらとは別に肺機能全体を広く高める薬能をもって対応する必要がある。
人参養栄湯は十全大補湯の方意を持ち、より肺機能を高めるための加減を施された処方である。さらに黄耆建中湯も肺気虚と呼ばれる肺の機能低下に適応する方剤。これらは肺の免疫機能を高めるために広く用いられる方剤である。ただしこれらの処方を一律的に運用するだけではあまり効果はない。肺機能のみならず、より全身的な状態を勘案することで「虚」の本質を見極めて方剤を選択する必要がある。
人参養栄湯も黄耆建中湯もともに「虚労(きょろう)」と呼ばれる一種の疲労・消耗状態に至る流れの中で運用するべき方剤である。そして人参養栄湯はあくまで十全大補湯に胚胎し、地黄を必要とするべき段階に属する。また黄耆建中湯は小建中湯に胚胎し、内の緊張のみならす外部の緊張状が顕在化している状態に用いるべき方剤である。これらの鑑別は各漢方家の考え方によって異なるものの、無症候性の病ではこういった本質的な人体の捉え方に対する造詣が特に問われてくる。
人参養栄湯:「構成」
黄耆(おうぎ):桂枝(けいし):人参(にんじん):甘草(かんぞう):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):当帰(とうき):芍薬(しゃくやく):地黄(じおう):遠志(おんじ):陳皮(ちんぴ):五味子(ごみし):
黄耆建中湯:「構成」
黄耆(おうぎ):桂枝(けいし):甘草(かんぞう):芍薬(しゃくやく):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):膠飴(こうい):
⑩四君子湯(太平恵民和剤局方)六君子湯(医学正伝)
慢性経過し、身体の虚状が強い段階の肺疾患においてしばしば運用されるのが人参剤である。四君子湯は「補気」の大剤。疲労感が強く、少し動いただけで息切れし、肌もくすんだ黄色を呈し唇の色も薄い、貧血傾向のある者に奏効する方剤である。肺気を補う時は黄耆を加えて用いることが多い(これを大四君子湯という)。また喀血などの症状を呈する場合でも「気虚」に属するものがある。四君子湯の変方として「扶脾生脈散(ふひしょうみゃくさん)」が有名である。
そして肺の弱りは脾胃(消化管)の弱りに帰結する。肺が苦しくなると食欲がなくなる、常に胃もたれがあり少ししか食べられないといった胃腸の弱りを持つ方の肺疾患では、胃腸薬である六君子湯にて肺機能が高まるということが良くある。肺疾患を改善するために胃腸症状を改善しておくことは非常に重要である。便秘や下痢・腹満や腹痛・胃もたれや胃痛などの症状を胃腸薬にて改善すると、同時に心肺機能が高まってくるということは臨床的に良く起こることである。
四君子湯:「構成」
人参(にんじん):甘草(かんぞう):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):
六君子湯:「構成」
人参(にんじん):甘草(かんぞう):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):半夏(はんげ):陳皮(ちんぴ):
※扶脾生脈散:人参・黄耆・当帰・芍薬・麦門冬・五味子・紫菀・甘草(咳血が止まない者は白芨を加える)
⑪通導散(万病回春)
非結核性抗酸菌症において「瘀血(おけつ)」という解釈をもって治療に当たらなければいけない時がある。「瘀血」とは一種の血行障害にて、特に静脈血のうっ血や組織の線維化・瘢痕化・またはこれらに至る流れを「瘀血」と捉えて治療する。例えば気管支拡張症を合併している場合では、病変部への肺動脈が閉塞し、これに変わって気管支動脈が増殖してくることがあるが、これによって血痰や喀血が起こることがある。この場合「瘀血」と捉えて治療を行うことで止血されることがある。代表的な駆瘀血剤に桂枝茯苓丸があるが、駆瘀血作用が非常にマイルドであるため、長期慢性化した瘀血に対しては薬能が不十分であることが多い。通導散や大黄牡丹皮湯などの強い駆瘀血剤まで見据えて、駆瘀血作用の強弱をコントロールしながら治療を行う必要がある。
通導散:「構成」
当帰(とうき):枳殻(きこく):厚朴(こうぼく):陳皮(ちんぴ):木通(もくつう):紅花(こうか):蘇木(そぼく):甘草(かんぞう):大黄(だいおう):芒硝(ぼうしょう):
臨床の実際
<非結核性抗酸菌症における漢方治療>
まず非結核性抗酸菌症ではいくら菌を叩こうとしても完治に至ることは困難です。特異的に菌を死滅させる抗菌剤は漢方にはありません。しかし菌を抑制しようとする力は、体がもともと持っています。その力を高めることで、自らの力をもって菌が抑制できる環境を作りあげるのが漢方治療です。
したがって漢方ではまず身体の消耗、いわゆる「虚」に対して配慮します。疲労感が強い・体重が減少してきている・食欲がないなどの「虚」の症状が明らかである場合だけでなく、それほど疲労感を感じていなくても「虚」に属している方もいます。その状態を正確に見極め、「虚」に配慮して免疫力を向上させるというのが、本疾患において最も行われやすい治療です。
また長期化する肺疾患では、血行状態を調えることも重要です。免疫力の発動を担う白血球は血中の成分であり、血液にのって運ばれて初めて働くことができます。したがって「血虚(けっきょ)」や「瘀血(おけつ)」と呼ばれる病態に対応する手法を選択し、血行を促す治療を平行します。
このように「虚」や血行循環障害に対して配慮することが基本ですが、実際に症状を発生させている場合は、その症状を緩和させる治療を行います。咳や痰・血痰(喀血)などに対して、咳を止め・痰を消し・出血を止める薬物をもって対応し、治療に当たります。
<目次>
1.症状を止める治療
ⅰ)咳に対して
ⅱ)痰に対して
ⅲ)血痰・喀血に対して
2.「虚」への対応
3.「瘀」への対応
1.症状を止める治療
ⅰ)咳に対して
身体に継続的・長期的に感染を起こしながら消耗を深めていく病は過去にも存在しています。結核です。江戸時代から昭和初期にかけて、結核治療は漢方においても非常に塾考が重ねられました。その時用いられていた手法を総じていえば、肺に起こる慢性的な炎症を沈静化させつつ、肺に潤いをつけて、体力を回復させるというものです。肺は潤いを常とし、潤うことで自らの機能を保っている臓です。慢性化する炎症では、肺の潤いが失われていくことで肺の機能が乱れ、同時にからだ全体の陰分(潤い)が消耗し免疫力を弱めていきます。
非結核性抗酸菌症は結核とは異なりますが、長期的な感染により肺の潤いを失いつつ体力を消耗させていくという点で類似しています。したがって、漢方にて培われてきた結核治療の要綱と対応処方とを応用することができます。漢方ではこの病態を「肺痿(はいい)」や「骨蒸(こつじょう)」などと呼びます。また「労咳(ろうがい)」や「結胸(けっきょう)」などと称されることもあります。総じて身体に微熱が続き、肺の潤いが失われながら進行していく肺疾患に属しています。
適応方剤は有名なところで言えば、麦門冬湯や竹葉石膏湯です。しかしこれらの処方だけでは咳を止めることが難しいケースが多いため、多くの処方が編み出され、運用されてきました。人参飲子や秦艽扶羸湯、また滋陰至宝湯や加減瀉白散、さらに柴胡桂枝乾姜湯などを活用することで、咳へと対応していきます。
●浅田宗伯の「肺痿・骨蒸」治療
江戸から昭和にかけて大流行した結核は、長引く微熱と咳・喀血などを主とする病です。したがって漢方でいう所の「肺痿」の病治を応用して対応していました。浅田宗伯は『勿誤薬室方函口訣』において「肺痿」の治療の要綱を述べている箇所があり、ここではそれを簡単にご紹介したいと思います。
「肺痿」とは肺部に熱(炎症)が長期的に継続することで肺の津液・気血を消耗させていく病です。主に結核のような長期慢性化しやすい感染症により起こると考えられています。「肺痿」では、はじめ炎症の勢いが強い段階では微熱や往来寒熱という熱を発生させます。この熱は寝汗を生じさせることがあります。まるで骨を蒸すように深い所から湧き出る熱という意味で「骨蒸(※)」と呼ぶこともあります。肺の損傷が深まると喀血(咳血)を生じ、さらに長期化して体力・免疫力が低下していくと熱が退く代わりに「労咳・労嗽」と言われる労作時に発現する咳を起こすようになります。浅田宗伯はこのような「肺痿」の流れに対して、各々適応する処方を以下のように述べています。
※骨蒸は肺疾患のみならず肝炎などの消化管の炎症や産褥熱、時に更年期障害におけるものなどが含まれていた可能性があります。
まず「肺痿」の初期「骨蒸」を発し始めた段階では、竹葉石膏湯の変方である「五蒸湯」もしくは「麦煎散」を用いて対応します。また身体痩せて羸痩の状が強くなれば「聖剤・人参養栄湯」を用い、この時やや熱状強ければ「秦艽扶羸湯」を選用します。ここまでは明らかな熱状を伴う状況ですが、さらに虚状を呈し咳血などの出血が主になると「肺傷湯」や「寧肺湯」、さらに熱状が無くなると「炙甘草湯加桔梗」や「却労散」を使うというのがその方針です。これらは熱証に属する肺痿の流れですが、それとは別に寒性に傾く肺痿もあります。「補肺湯」や「甘草乾姜湯」が適応します。時に「柴胡桂枝乾姜湯」を応用していたとも考えられます。
「肺痿・骨蒸」の治剤としては、後世方派では「逍遥散」もしくは「滋陰至宝湯」が、古方派では「柴胡桂枝乾姜湯」が有名ですが、浅田は臨床経験から上のように分類して治療を行っていたようです。これらの手法は同じく長期的に肺機能を失調させる非結核性抗酸菌症において、知っておくべき手段だと言えるでしょう。
※「五蒸湯・ごじょうとう」:竹葉・石膏・黄芩・知母・葛根・茯苓・人参・甘草・粳米・地黄
※「麦煎散・ばくせんさん」:柴胡・当帰・茯苓・白朮・甘草・石膏・大黄・地黄・常山・乾漆・鼈甲・小麦
※「秦艽扶羸湯・じんぎょうふるいとう」:柴胡・半夏・人参・甘草・生姜・大棗・秦艽・地骨皮・紫菀・烏梅・当帰・鼈甲
※「聖剤人参養栄湯・せいざいにんじんようえいとう」:柴胡・桑白皮・貝母・桔梗・枳実・杏仁・茯苓・人参・甘草・五味子・阿膠
※「寧肺湯・ねいはいとう」:桑白皮・五味子・阿膠・麦門冬・人参・甘草・茯苓・白朮・当帰・川芎・芍薬・地黄(『勿函』には人参を去ると記載あり)
※「却労散・きゃくろうさん」:五味子・阿膠・黄耆・当帰・芍薬・地黄・人参・甘草・茯苓・大棗・生姜
※「補肺湯(千金)・ほはいとう」:桂枝・乾姜・桑白皮・五味子・款冬花・麦門冬・粳米・大棗
ⅱ)痰に対して
痰がたくさん出るタイプの非結核性抗酸菌症があります。気管支拡張型のものや、気管支拡張症が絡んでいる線維空洞型に散見されます。この場合には肺を潤す(潤燥)とともに、痰を消し排出させやすくする(化痰)という治療が必要になります。薏苡仁・石膏・桔梗・貝母・枳実・冬瓜子などの化痰薬を配合する処方をもって対応することが一般的です。
気管支拡張症や肺化膿症などのように、膿性の痰がでて微熱や胸痛を起こしている状態を漢方では「肺癰(はいよう)」といいます。皮膚膿瘍(おでき)などに用いる解毒・排毒という手法を肺に応用します。非結核性抗酸菌症においても膿性の痰や、濃く粘稠度の高い痰を出す場合にはこの手法が用いられます。
痰咳は古くから研究されてきたため、たくさんの適応処方が存在します。清肺湯・清金化痰湯・柴胡桔枳湯・柴陥湯などを始め、葦茎湯・四順湯・肺癰湯・回春桔梗湯・外題桔梗湯・呂貝養栄湯・聖剤人参養栄湯など、非常に多くの処方が創作されてきました。これらは肺部に起こる炎症の強さによって使い分ける必要があります。肺熱の程度・痰の質や量・病の経過時間や痰咳の勢いなどを見極めながらこれらの薬方を選択してきます。
●浅田宗伯の「肺癰」治療
浅田宗伯は「肺痿・骨蒸」のみならず、「肺癰」についてもその治療方針を現わしています。気管支拡張症や肺化膿症などのように肺部に化膿性炎症を生じる「肺癰」は、その治療方法も「肺痿」とは区別して行われていました。山本巌先生が『東医雑録』の中で解説されている部分を参照にしながら、その治療方針を示してみたいと思います。
「肺癰」は肺部の化膿性疾患ですから、漢方における「癰(よう:おでき)」治療を基本とします。発症初期、発熱悪寒を生じる時期では「発表」を行い、微熱が継続し残存する炎症のために勢い強く化膿を生じる時期では清法や下法などの「清熱解毒」を主とする。さらに熱状が落ち着くも膿性の痰が多く喀出される時期では「透托」を、そして熱は下がったがいつまでも肺の機能が回復せず痰が止まないという場では「補托・活血」を行います。
「発表」の段階では他の肺疾患(気管支炎など)と同様で、「麻黄湯」や「小青竜湯加杏仁石膏」などを用います。また発熱があるも悪寒が無くなり呼吸困難を呈する者では「麻杏甘石湯加桔梗(尾台榕堂の加減)」が適応します。ただし非結核性抗酸菌症においては、このような「発表」の時期はほとんどありません。亜急性期にかかる微熱の段階、つまり「清熱」を主とする段階から着目していく必要があります。浅田宗伯は微熱や往来寒熱を生じ、膿性の痰が出て咳とともに胸痛を起こす場合には「柴胡桔枳湯加蒂藶子」を、そして熱候が収まると「肺癰湯」を用いています。さらに日を経て体力を消耗し咳血が止まない者では「透托」が必要です。「肺癰神湯」に切り替えます。さらに一等虚の状が強ければ「補托・活血」の方剤として「外台・桔梗湯」を用いています。一方で、急激な炎症を起こすというよりは、徐々に慢性経過していく「肺癰」もあります。その場合では微熱や胸中甲錯(皮膚に潤いがなくなりカサカサとしている状態)を目標として「葦茎湯」(清熱・排膿・駆瘀血)を選用しています。また咳嗽が強い時はこれに「四順散」合わせています。
※「柴胡桔枳湯」:柴胡・半夏・黄芩・甘草・生姜・栝楼仁・枳実・桔梗
ⅲ)血痰・喀血に対して
慢性の消耗性肺疾患では、乾いた咳や濃く粘稠な痰を継続させていると、咳とともに痰に血が混ざることがあります。漢方ではこのような咳血に対しても対応する手法があり、仙鶴草(せんかくそう)・白芨(びゃくきゅう)・阿膠(あきょう)などの肺部の出血を抑える止血薬をもって治療に当たります。
麦門冬湯加地黄・阿膠・黄連はその代表です。江戸時代の名医、浅田宗伯が「肺燥」とよばれる肺の乾燥状態にともなう出血に対して用いた有名な加減です。また百合固金湯・寧肺湯・肺傷湯・却労散・補肺湯・扶脾生脈散などを選用します。これらは「陰虚(いんきょ)」や「気血両虚(きけつりょうきょ)」といった一種の消耗状態に適応する方剤です。継続する炎症を抑えることのできない疲労状態を改善しながら、血行を調え止血を図ります。さらに慢性的に継続する出血に対しては、血を止めるよりもむしろ血行を促すことがあります。いわゆる「瘀血」に属する出血で、各種駆瘀血剤を用いて鬱血を除くことで止血を図ります。「瘀血」については後の項目も参照してください。
2.「虚」への対応
「虚」とは肺の炎症や損傷を回復する力の弱りを指します。非結核性抗酸菌症は強力な感染力を持った菌によって発症する病ではありません。むしろ弱い菌に対しても感染を長引かせてしまう体の弱さに起因していることが多い疾患です。したがって本疾患では「虚」を補うことで肺の機能を高め、自らの力で回復しやすい状況へと向かわせていく治療が主体となります。
●「補肺薬」とは
「虚」により肺の機能が減弱している状態を漢方では「肺虚」と呼びます。そして「補肺薬」と呼ばれる処方群をもってこれに対応します。「肺の機能を補う」と言うと、感覚的に理解しやすいとは思いますが、では現実的になにを回復させているかというと、肺の潤いと血行循環を回復します。「補肺薬」と呼ばれる一連の処方群には、人参や甘草といった陰液(身体の潤い)を補う薬物や、当帰や黄耆(この2味を「補血湯」という)といった血を補い血行を促す薬物が含まれています。つまり肺に潤いをつけ血行循環を促すことで、肺が本来もっている柔らかでしなやかな活動を取り戻し「肺虚」を回復するわけです。
人参養栄湯・十全大補湯・補中益気湯・黄耆建中湯・四君子湯など、漢方には補肺薬がたくさんあります。ただしこれらの処方はただ一律的に服用しているだけではあまり効果が出ません。これらは虚を補う一連の処方群ではありますが、それぞれに薬能が異なり、適応する「虚」の状態にも違いがあります。そしてその細かな運用の的確さが、薬効発現に如実に反映されてきます。さらにエキスか煎じ薬かの剤型の違いや、加減や合方といった細かな配慮によっても、薬効発現に大きな違いが出てきます。
●「肺虚」から「脾胃の虚」へ
肺の「虚」はより全身的な「虚」へと向かうにつれて、結局は「脾胃(ひい:消化機能)」の失調に帰結していきます。逆に言えば平素から消化管の不調や消化機能の弱さを持つ方では、「肺虚」が起こりやすく、継続しやすい傾向があります。故に胃腸薬である六君子湯や半夏瀉心湯・小柴胡湯や柴胡桂枝湯、そして大柴胡湯に至るまで、的確に適応させればすべて肺の機能を高めることにつながります。肺疾患という局部的な病態に惑わされず、全身的な配慮をもって治療を行うことが重要です。
●「陰証」について
「肺虚」や「脾胃の虚」など、「虚」には各部の虚が存在します。しかし時により重要な指標となるのが、大きく全体として、生命力という意味で体を観た時に判断される「虚」の解釈です。この「虚」には構造があり、段階があります。これを「陰証(いんしょう)」といいます。
これらは細部ではなく全体を観るという漢方哲学の原則に照らし合わせた時に初めて見えてくる尺度です。そしてこの解釈と理解との正確さが、「虚」を改善する上での腕前を大きく左右させます。例えば先に上げた補中益気湯・十全大補湯・四君子湯などを使っても効果が現れないという場合は、これらの方剤では対応しきれないほど「虚」を深めている可能性があります。それを見極め、正しく治療を捉えるための視点が「陰・陽」です。少し難しいかもしれませんが、歴代の漢方家たちはこの「陰証・陽証」の鑑別に非常に悩みました。そして同時に深い理解をもって対応することで難治性の疾患を改善してきました。
その一旦を簡単に説明しましょう。通常「陰証」とは、生命力が減弱し身体の新陳代謝が衰えて、生きるための熱源を弱めているような状態と解釈されています。(一方で「陽証」とは生命力が充実し病と闘う力も充分にあり、かつ激しい闘病反応を起こすことが可能という状態です。)生命力の弱りを示す「陰証」では身体が冷えて熱を発するができず、身を横たえ気持ちも沈むという状態になります。そのため「陰証」に対しては乾姜(かんきょう)や附子(ぶし)といった熱薬を用いることが一般的です。
しかし明らかな発熱を伴い、咳や客痰にも勢いがあるという一見「陽証」に見えるような状態であっても、実は「陰証」に陥っているということがあります。肺の炎症所見が顕著で、病態に勢いがあるという場合に、乾姜や附子などの熱薬を使うことは非常に怖いものです。熱薬によって炎症が強くなってしまう可能性があるからです。しかし病態に勢いがあったとしても、「陰証」に陥っているのであれば、熱薬を用いなければ回復させることができません。したがって「陰・陽」の弁別は漢方家にとってキモであり、非結核性抗酸菌症のような消耗性疾患では、特にその判断が重要になります。
「虚を補う」といえば一言ですみますが、実は「虚」を補うということは簡単ではありません。ただ補剤を用いるというだけでは効果が無くて当たり前です。「虚」の程度や性質・段階まで含めた正確な弁別が行われて初めて回復できるのが「虚証」です。そして歴代の漢方家たちが真剣勝負の中で培ってきた経験側を理解することが、「虚」を回復するために必要不可欠です。
3.「瘀」への対応
非結核性抗酸菌症において「瘀血(おけつ)」という解釈をもって治療に当たることがあります。「瘀血」とは一種の血行障害です。特に静脈血のうっ血や組織の線維化・瘢痕化・またはこれらに至る流れを「瘀血」と捉えて治療します。非結核性抗酸菌症では、痰に血が混じるなどの血痰を生じているケースや、線維空洞型などの難治性の病態において主に捉えられやすい病態です。特に気管支拡張症を合併している場合では、病変部への肺動脈が閉塞し、これに変わって気管支動脈が増殖してくることがあります。これらは血痰・喀血の原因になり、「瘀血」と捉えて治療を行うことで出血が止まることがあります。
「瘀血」を除く処方群を駆瘀血剤(くおけつざい)といいます。桂枝茯苓丸はもっとも有名な駆瘀血剤ですが、その他にも多くの処方が存在します。特に桂枝茯苓丸は非常にマイルドな駆瘀血作用を有する処方です。したがって瘀血を去る薬能が充分でないことが多く、その場合はより強い駆瘀血作用を持った薬方を選択します。桃核承気湯や通導散、大黄牡丹皮湯などがその代表です。これら強い駆瘀血作用を持った処方には、大便の通じを促す薬能があります。「下法」と呼ばれるこの薬能は、強力に肺部の血行障害を改善する時に有効です。大腸と肺とは昔から関連する臓器として考えられてきました。実際に咳や痰を発してさらに便秘がちという方が「下法」をもって通じを促すと、症状が急速に緩和されるということがあります。ただし非結核性抗酸菌症のような「虚」の病態を帯びやすいような疾患では、強引に「下法」を行うと体調を悪化させることがあります。したがってこれらの処方を用いる場合には、薬量や合方を検討しながら細心の注意をもって行うことが重要です。