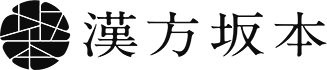アトピー性皮膚炎について
アトピーとは「奇妙な」という意味のギリシャ語に由来しています。本人の家族や親せきなどに共通しておこる不思議な反応をアトピーと名付けたのが始まりです。つまりアトピーとはアレルギー反応を起こす物質によって湿疹や喘息などを起こしやすい体質のことを指し、これをアトピー素因と言ったりもします。
アトピー性皮膚炎とは
アトピー性皮膚炎とはこのような敏感な皮膚状態のために発症する皮膚炎です。乳児から大人まで幅広く発症します。強い痒みを伴いやすく、季節的に増悪・寛解を繰り返して慢性の経過をたどりやすいのが特徴です。諸々の治療を行っても簡単には治癒しない湿疹をアトピー性皮膚炎と呼んでいる場合もあります。なぜこのような湿疹を起こしてしまう体質になるのか、真の原因は不明です。
●治療の問題点と漢方治療
急性期では、滲出性で痂皮を伴う発疹、つまりじくじくとした汁が出てカサブタを伴う発疹が出現します。特に乳児などの子供ではこのような発疹が生じやすい傾向があります。慢性経過すると皮膚が硬くなって苔癬化し、鱗屑が厚くなると乾燥してひび割れたりします。痒みが強く、かつ痒みを感じやすくなるため、掻きむしることでこれらはどんどん悪化していくという悪循環に陥ります。
主にステロイドの外用薬にて痒みと炎症を抑えるという治療が行われます。炎症をコントロールするという意味で、ステロイドの外用剤は非常に有効ですが、アトピー性皮膚炎は皮膚炎を生じやすい体質によって発症する疾患ですので、一時的な解決にしかなりません。スキンケアやアレルゲンとなっている飲食物の排除なども大切ですが、これらをしっかりと行ってもなかなか思うように改善していかないというケースもしばしば見受けられます。
アトピー性皮膚炎の漢方治療は、それぞれの漢方家によってさまざまな考え方があると思います。アトピー性皮膚炎はここ数十年の間に急増してきた疾患です。古典から治療方法を導き出す漢方は、こういった新しい病に対しては未だ治療方法が一定していないというのが現実です。しかし腕の確かな先生であれば、こういう新しい病こそを改善することができます。各漢方家の腕前によって治療成績が左右されやすい疾患だといえるでしょう。
参考コラム
「アトピー性皮膚炎」に対する漢方治療を解説するにあたって、参考にしていただきたいコラムをご紹介いたします。本項の解説と合わせてお読み頂くと、漢方治療がさらにイメージしやすくなると思います。
コラム|アトピー性皮膚炎 1・2
アトピー性皮膚炎はここ半世紀の間に急増してきた疾患です。古典から治療方法を導き出す漢方では、こういった新しい病に対しては未だ治療方法が確率していないという現実があります。しかしだからこそ、アトピー性皮膚炎に対する漢方治療は目覚ましい変化を遂げてきました。今までの治療とその現実的な効果、そしてこれからどのように変化していくのか。過去・現在・未来に渡るアトピー性皮膚炎治療の実際をご紹介いたします。
→□アトピー性皮膚炎 1 ~どういう治療が行われてきたのか・漢方治療の変遷~
→□アトピー性皮膚炎 2 ~漢方治療の現状と新しい試み~
コラム|自己免疫疾患・アレルギー性疾患 ~原因不明の炎症・その漢方治療~
現代では原因不明の炎症を生じる病が数多く存在しています。アトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患や、関節リウマチなどの自己免疫疾患、また潰瘍性大腸炎やクローン病などがこれに属しています。日本でもこれらの疾患に対して、昭和時代の漢方家が多くの治験を残してきました。ただし今まで繰り返し行われてきた手法では、その治療成績に限界があると感じています。そこで、今まで漢方はどのように対応してきたのか、そして今後どのように対応するべきなのかということを、一つの見解として解説していきたいと思います。
→□自己免疫疾患・アレルギー性疾患 ~原因不明の炎症・その漢方治療~
コラム|漢方治療の経験談「アトピー性皮膚炎治療」を通して
当薬局でもご相談の多いアトピー性皮膚炎。日々治療を経験させていただいている中で、実感として思うこと、感じたことを徒然とつぶやいたコラムです。
使用されやすい漢方処方
①消風散(しょうふうさん)
②荊防敗毒散(けいぼうはいどくさん)
③袪風敗毒散(きょふうはいどくさん)
④黄連解毒湯(おうれんげどくとう)
⑤温清飲(うんせいいん)
⑥三物黄芩湯(さんもつおうごんとう)
⑦小建中湯(しょうけんちゅうとう)
⑧補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
⑨十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)
⑩駆瘀血剤(くおけつざい)
※薬局製剤以外の処方も含む
①消風散(外科正宗)
湿疹治療の代表方剤。「風湿」と呼ばれる皮膚病に適応し、水疱やビランなどの湿潤傾向が強く、痒みの強い皮膚炎に用いられる。また「瘡疥(そうかい)」といって厚い痂皮を生じて木の皮のようにぽろぽろと剥がれ落ちる乾燥性の強い皮膚炎に適応する。つまり湿性が強く、滲出液が外にあふれ、それが熱によって乾き、表皮に乾燥状を呈するという状態に用いる。基本処方の一つであり、炎症の程度によって清熱剤を加える必要がある。
消風散:「構成」
石膏(せっこう):知母(ちも):荊芥(けいがい):蝉退(せんたい):防風(ぼうふう):木通(もくつう):苦参(くじん):蒼朮(そうじゅつ):胡麻(ごま):牛蒡子(ごぼうし):当帰(とうき):地黄(じおう):甘草(かんぞう):
②荊防敗毒散(万病回春)
おでき治療の代表方剤であるが、同時に湿疹に対しても有効。水疱よりも膿疱を形成しやすく、ぽつぽつとした発疹を生じる皮膚炎に適応する。炎症初期の病巣を消散させる目的で用いる。鱗屑を厚く形成したり、湿潤傾向が強い場合には単独では効果が弱い。他剤との合方や加減を検討するべきである。
荊防敗毒散:「構成」
柴胡(さいこ):前胡(ぜんこ):川芎(せんきゅう):防風(ぼうふう):荊芥(けいがい):連翹(れんぎょう):羌活(きょうかつ):独活(どくかつ):茯苓(ぶくりょう):桔梗(ききょう):甘草(かんぞう):薄荷(はっか):枳殻(きこく):金銀花(きんぎんか):
③袪風敗毒散(寿世保元)
荊防敗毒散と消風散とを合わせたような処方。化膿性炎症を基本にそこから滲出性炎症を介在させる場に用いる。炎症を抑える力が弱いため黄連解毒湯などを合わせる必要がある。地黄や麻黄などの胃に負担のある生薬が入っておらず、薬性は軽い。胃腸の弱い現代人の湿疹に用いやすい方剤である。
袪風敗毒散:「構成」
柴胡(さいこ):前胡(ぜんこ):川芎(せんきゅう):荊芥(けいがい):連翹(れんぎょう):羌活(きょうかつ):独活(どくかつ):白姜蚕(びゃくきょうさん):牛蒡子(ごぼうし):蝉退(せんたい):芍薬(しゃくやく):甘草(かんぞう):薄荷(はっか):枳殻(きこく):蒼朮(そうじゅつ):
④黄連解毒湯(肘後備急方)
清熱薬として有名な本方は、各種皮膚病の強い炎症状態に広く応用される。アトピー性皮膚炎では十味敗毒湯や荊防敗毒散と合わせて用いられる機会が多い。血管拡張性の炎症、つまり患部の赤味や充血が強い場合には黄連解毒湯を加えないと効果が薄い。また清熱薬としては石膏も重要である。炎症にて患部が腫れ、ガサガサと粉を吹くような皮膚面に対して大量に用いる。山田業廣は『椿庭経方弁』にて石膏の薬能を「発表・清熱・滋陰」と要約している。
黄連解毒湯:「構成」
黄連(おうれん):黄芩(おうごん):黄柏(おうばく):山梔子(さんしし):
⑤温清飲(万病回春)
黄連解毒湯と四物湯とを合方したもの。もともと「血崩(けっぽう)」と呼ばれる性器からの出血に用いる方剤であるが、黄連解毒湯の清熱作用と四物湯の滋潤作用を併せ持つことから皮膚病に広く応用されるようになった。特に一貫堂医学にて広く運用され、柴胡清肝散・荊防敗毒散・竜胆瀉肝湯などの原型となる。本方は乾燥性で白い粉をふいて痒みがひどく、かき破って出血したりザラザラしたりという状態のアトピー性皮膚炎に用いる、とされている。
温清飲:「構成」
黄連(おうれん):黄芩(おうごん):黄柏(おうばく):山梔子(さんしし):当帰(とうき):川芎(せんきゅう):芍薬(しゃくやく):地黄(じおう):
⑥三物黄芩湯(金匱要略)
もともと「煩熱(はんねつ)」と呼ばれる熱感に用いられる処方であるが、アトピー性皮膚炎に応用されることがある。内包する苦参は痒み止めで、アトピー性皮膚炎の痒みを抑える効果がある。単剤で用いるよりも、他剤と合方されることが多い。
三物黄芩湯:「構成」
地黄(じおう):黄芩(おうごん):苦参(くじん):
⑦小建中湯(金匱要略)
アトピー性皮膚炎の本治薬として用いる。昭和時代に古方派の先生方が小建中湯加荊芥・土骨皮という形で好んで用いていた。黄耆を加える時もある。一律的に頻用すると内包する温薬にて炎症を悪化させることがあるため注意を要する。「虚労」と呼ばれる疲労状態に適応する。
小建中湯:「構成」
桂枝(けいし):芍薬(しゃくやく):甘草(かんぞう):生姜(しょうきょう):大棗(たいそう):膠飴(こうい):
⑧補中益気湯(内外傷弁惑論)
アトピー性皮膚炎の本治法として用いられる。もとは中島随象先生がアトピー性皮膚炎に有効であるとし、弟子の山本巌先生がこの運用を広めた。六君子湯や補中益気湯などの補気剤で改善するアトピーは確かに存在する。これらの処方は胃腸機能を回復し、免疫機能を安定させる。
補中益気湯:「構成」
当帰(とうき):黄耆(おうぎ):人参(にんじん):甘草(かんぞう):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):白朮(びゃくじゅつ):陳皮(ちんぴ):柴胡(さいこ):升麻(しょうま):
⑨十全大補湯(太平恵民和剤局方)
赤くビランを伴い、痒みよりも組織の修復が悪いアトピー性皮膚炎に用いて良い場合がある。皮膚の栄養状態悪く、ビランから汁が止まず、いつまでも皮膚がもとに戻らない状態。千金内托散や帰耆建中湯を用いても良い。痒みが強く炎症が強いアトピー性皮膚炎では悪化させることがあるので注意。
十全大補湯:「構成」
当帰(とうき):川芎(せんきゅう):芍薬(しゃくやく):地黄(じおう):桂枝(けいし):黄耆(おうぎ):人参(にんじん):甘草(かんぞう):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):
⑩駆瘀血剤
皮が厚くザラザラと硬く、苔癬化した皮膚には駆瘀血剤を用いる手法がある。通導散・桂枝茯苓丸・桃核承気湯・桃紅四物湯などから専用する。単剤もしくは合方して用いられる。皮膚の肥厚だけでなく、色素の沈着や脱失などにも用いる。
臨床の実際
まず第一に、アトピー性皮膚炎では食事の不摂生をあらためる必要があります。ストレスでも悪化することがあります。しかし現実的に生活の中でストレスを完全にコントロールすることは不可能です。食事は気をつけることができるはずです。どんな治療を行っても、食生活が乱れていれば改善へと向かうことはできません。
第二に、睡眠不足は皮膚症状を必ず悪化させます。皮膚は寝ている間にしか修復されないからです。食事と睡眠、これは基本中の基本です。私の経験では、むやみやたらに食べ、睡眠時間が極端に少ない生活を送られている方では、アトピーがなかなか完治していかない印象があります。
生活上これらをできる範囲で気を付けている方でも、また規則正しい生活をおくられている方でも、アトピー性皮膚炎がなかなか改善しないという方は当然いらっしゃいます。アトピー性皮膚炎は的確に治療できれば必ず改善していく病でもあります。漢方にてアトピーをどう捉え、どう治療していくのか、その概要を以下に解説してきたいと思います。
<アトピー性皮膚炎治療の実際>
アトピー性皮膚炎はそもそも湿疹の範疇に属します。炎症が表皮に起こり、痒み・多様性・点状状態を発生させるという湿疹の要素を満たしています。したがってアトピー性皮膚炎の漢方治療は湿疹治療を基本とします。
湿疹治療は「標治」と呼ばれる現在起こっている皮膚の炎症を抑える治療と、「本治」つまり皮膚症状を起こす体質自体を改善する治療とを分けて行います。皮膚症状が強く生じている場合には「標治」で炎症を鎮め、炎症が落ち着いたら「本治」に移行し炎症を生じにくい体質にしていく、というのが基本です。「本治」は炎症が未だ強い状態で行うと、効果がないばかりか症状を悪化させることがあります。したがって「標治」を十分に行うことが重要です。ただし「標治」をいくら行っても炎症が抑えられず、むしろ「本治」から入ることで炎症が治まるということもあります。アトピー性皮膚炎の治療は、この「標治」と「本治」とを明確に区別し、かつどちらが最適かを的確に判断することから始まります。
1.アトピー性皮膚炎の「標治」
今までの湿疹治療を基本にすると、以下のように処方を運用することが一般的です。
〇急性期、滲出性炎症が甚だしくじくじくと汁を染み出す段階では消風散を基本とする。炎症が酷ければ黄連解毒湯を合方する。
〇また皮膚が乾燥して痂皮が生じ、皮がやや厚くなって小丘疹が一面にみられる場合は荊防敗毒散や十味敗毒湯を基本とする。炎症が酷ければ黄連解毒湯や石膏剤を合方する。
〇慢性期にて皮膚苔癬化が甚だしく、皮膚が肥厚していれば温清飲の加減に駆瘀血剤(通導散や桂枝茯苓丸など)を合方する。
このように示すと、アトピー性皮膚炎の標治がこれだけで充分であるように見えますが、現実的には不十分です。
●現行治療の問題点
アトピー性皮膚炎はこのような治療方法にて改善しきれないケースがたくさんあります。消風散や荊防敗毒散、温清飲などを運用しても難治性のアトピー性皮膚炎にはどうしても限界があると感じます。これらの方剤は江戸・明治・大正・昭和と脈々と続いてきた皮膚疾患治療の代表方剤です。しかしアトピー性皮膚炎は近年になって急増傾向にある新しい疾患です。昔ながらのやり方を今一度見直す必要があると思います。
●現行治療がなぜ効かないのか
消風散や荊防敗毒散は「発表(はっぴょう)」と呼ばれる薬能をもって皮膚病を改善する方剤です。そもそも皮膚面におきる発疹は、体にとって害のあるものを外に出そうとする反応によって起こります。これらの方剤はその勢いを促し、皮膚面にて激しい闘病が起きる前に排出を優位に進めて病巣を消散させる薬で、これを「発表」といいます。発疹患部の炎症は外に出ようとする時に強まり、その反応が解除されると鎮まります。「発表」は外に出ようとする力をスムーズに発動させることで、このような炎症の波を早期に終息させる手法です。したがって一時的な皮膚炎であれば「発表」が有効です。また例え慢性的に継続する皮膚炎であっても、患部の炎症が出た後に十分に引き、その上でまた発疹が出るというような炎症の波があれば、「発表」を継続していくことで改善へと向かいます。
しかし、炎症の波がほとんど無いかあっても僅かで、一定かつ継続して皮膚に炎症を生じ続けるという状態になると、「発表」が効かなくなります。外に出すのを助けたとしても、ある段階以上には炎症が治まらず、一定の炎症度合いが継続するためです。このような炎症像がアトピー性皮膚炎では非常に多いのです。
また炎症が継続すると、痂皮や鱗屑を生じて皮膚がカサカサと乾燥してきます。この時もし炎症に波があり、炎症自体に落ち着く傾向があるのなら、滋潤薬と呼ばれる当帰や地黄によって乾燥を防げます。温清飲はまさにそういう処方で、炎症を抑える黄連解毒湯と皮膚を滋潤する四物湯という方剤で構成されています。しかし炎症に落ち着く傾向なく、一定して生じているのであれば、乾燥している原因は継続する熱です。したがって滋潤薬をいくら使っても乾燥は取れませんし、むしろ滋潤薬で血行が促され炎症が悪化することさえあります。
患部の炎症に波がなく、ある一定の活発さを保ったまま継続して炎症を生じ続けようとする。これがアトピー性皮膚炎の中でも難治とされるものの特徴であり、今までの漢方治療を困難にさせている原因です。難治性アトピー性皮膚炎の標治を実際に成功させるためには、この継続して生じ続ける炎症をとにかく抑えなければなりません。痂皮や鱗屑や皮膚肥厚の改善も、炎症を抑えることができて初めて実現されます。
●「温病」について
「温病(うんびょう)」という概念があります。「温病」とは熱(炎症)が継続し、人体の陰分(体液)を灼焼し尽くすまで燃え続けるという病です。つまり炎症の波をあまり起こさず、一定・継続して生じ続ける病を指しています。この病態の概念は清代・中国にて呉鞠通(ごきくつう)という人物によって大成されました。そして呉鞠通は自著「温病条弁(うんびょうじょうべん)」の中で病態解釈の理論とその治療方法を示しています。
難治性のアトピー性皮膚炎の多くが、この「温病」に属しています。特に温病中の「湿熱(暑温・伏暑・湿温)」の範疇に属し、これらの治療理論を応用することで難治性アトピーの炎症を抑えることができます。日本では「傷寒論(しょうかんろん)」の研究が多くなされてきた一方で、「温病条弁」はあまり研究されてきませんでした。しかし「温病」の理論は、現代の難治性炎症性疾患において必ず知っておかなければならない理論です。特にアトピー性皮膚炎ではその必要性が非常に高いと思います。
附)アトピー性皮膚炎と「下法・和法」
ちなみに活発さを保ったまま継続している皮膚の炎症に対しては「下法(大黄剤により排便を促すことで炎症を去る方法)」や「和法(柴胡剤により毒を和す方法)」を使うこともあります。このうち「下法」は一時的にアトピー性皮膚炎の炎症を抑えられる場合があります。しかし炎症を十分に抑えることができるかというと、経験上非常に疑問です。これらの手法は炎症を生じる勢いが強いというよりも、一旦生じた炎症がおさまりにくいという状態に適応する手法です。しかしアトピー性皮膚炎は炎症を起こそうとする勢いが止まないという状態にあると考えられます。したがって下法や和法をもって炎症を終息させようとしても、生じ続けようとする勢いが止まないうちは、炎症が止みません。また「発表」が比較的皮膚の浅い部分に生じる炎症に用いる方法であるのに対して、「下法」や「和法」は比較的深い部分に生じる炎症に用いる傾向があります。つまり「下法」や「和法」が用いられる炎症は主に真皮を中心としたものであり、そのため毛包炎や皮膚膿瘍などの化膿性疾患に用いられやすい手法です。一方でアトピー性皮膚炎は、主に表皮という浅い場所で表在性の炎症を起こす疾患です。「下法」や「和法」とは病位が異なるため、的確に効かせることが難しいのだと思います。
2.アトピー性皮膚炎の「本治」
アトピー性皮膚炎は「温病」の理論に基づいた標治を的確に行い、皮膚の炎症をしっかりと抑えれば、多くの場合は薬によって本治を行わなくても完治に至ることが可能です。標治を漢方薬で行い、本治は食生活の改善によって行う、このやり方が最もスタンダードな治療方法です。
ただし中にはいくら食生活の改善を行っても、一旦治まった炎症が季節の変わり目などに悪化してしまうというケースもあります。またいくら標治的な治療を行っても炎症が治まらず、むしろ漢方薬で本治を行うことで初めて炎症が治まってくるという方もいらっしゃいます。アトピー性皮膚炎は皮膚自体が過敏で刺激に反応しやすいという内的な要素が強く関与します。そのため本治の手法もしっかりと把握しておく必要があります。
●本治薬と「脾胃」
小建中湯は昭和時代の古方派によってアトピー性皮膚炎に頻用された方剤です。通常は痒み止めの薬能を持つ生薬などを加え、小建中湯加荊芥・土骨皮(もしくは黄耆建中湯や桂枝加黄耆湯に荊芥・土骨皮)という形で使われます。本来は「血痺虚労」と呼ばれる病態に用いる処方で、この病態に適合するアトピー性皮膚炎であれば本治のみで炎症を抑えていくことができます。
補中益気湯や六君子湯もアトピー性皮膚炎の本治としてしばしば使われます。特に補中益気湯は中島随象先生がアトピー性皮膚炎に使用し、それを弟子であった山本巌先生が広めたものです。経験的にアトピーに効くという口伝のような運用だったそうです。大黄を加えて用います。確かに子供を中心として補中益気湯にて改善するアトピー性皮膚炎があります。
本治薬の多くが、結局は「脾胃(ひい:消化機能)」を改善する薬に帰結します。アトピー性皮膚炎の成因は未だ不明とされていますが、経験的には消化機能との関連が深いと思います。消化管は食事を人体にとって有害でないものに変化させた上で、体内に栄養を送り込みます。昔に比べて不自然な飲食物が増え、消化管が敏感に反応せざるを得ない状況がこの病の急増に関与しているのではないかと想像します。
●本治法を選択するべきアトピー性皮膚炎
本治治療は特に子供のアトピー性皮膚炎に効果的だと感じます。子供の場合は標治を行わなくても、本治的な治療のみで炎症が治まりやすい傾向があります。どちらかと言えば、赤ちゃんから乳児期のお子様には補中益気湯が、幼児期や小児期のお子様には小建中湯が適応しやすいと感じます。お子様のアトピー性皮膚炎は漢方治療が大変有効です。大きくなった時にアトピーを残さないためにも、早い段階で治療を行うことをお勧めします。
●本治法の乱用はアトピーを悪化させる
ただし「本治」は一律に行って良い治療ではありません。どのような炎症状態であっても本治的手法をもって対応するというのは間違いです。なぜなら改善しないばかりか、炎症を悪化させることもあるからです。重要なのは「標治」と「本治」とを明確に区別して治療することだと思います。「標本同治」といってこれらを同時に行うやり方もあります。ただし区別して治療した方が良いと思います。改善が明らかに早いと感じるからです。もし標治をせず、本治を行うのであれば、それなりの理由がなければいけません。本治法と標治法との両者を熟知した上で、最も良い手法を選ぶというのが、良い治療だと思います。