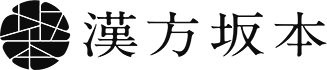喘息・気管支喘息・小児喘息について
喘鳴(ぜんめい)を伴う呼吸困難を主とした症候群を喘息といいます。このうち気道(気管支)の粘膜に慢性的な炎症が起こることで喘息を発生させる病が気管支喘息です。
西洋医学的治療によってコントロールしきれない気管支喘息が、漢方薬によって改善へと向かうという解説は、ネットや本などに散見されるところです。麻杏甘石湯や小青竜湯など、喘息治療に効くとされる漢方薬もたくさん列挙されています。ただし、具体的にどのように治療を行うのか、ということに関しての解説はあまり見ません。そこでここでは実際の漢方治療の特徴と、その現実的な効果とを解説してみたいと思います。
気管支喘息とは
まずは気管支喘息について簡単に解説していきます。気管支喘息とは気道に慢性的な炎症が起こることで空気の通り道が狭くなる病です。咳が止まらなかったり、息を吐き出すことができず息苦しくなる病です。通常であれば影響を受けないような刺激に対して、気道が敏感に反応してしまうために慢性的な炎症が継続します。増悪(ぞうあく)といって炎症が酷くなると、気管支の平滑筋が痙攣し、気道粘膜に浮腫が起こって腫れ、沢山の痰が分泌されて気道を塞ぎ、呼吸が困難になります。これを喘息発作といいます。完全に気道が塞がれると呼吸ができなくなります。そのため、ひどいと命に関わる危険な状態に陥ることもあります。
●気管支喘息の症状と「咳喘息」
気管支喘息の主な症状は「咳」「喘鳴(ゼロゼロといった呼吸音)」「呼吸困難」の3つです。季節の変わり目など、温度や湿度に急激な変化がる時に悪化しやすく、また体力が無いときや風邪が引き金となって悪化することもあります。さらに喘鳴や呼吸困難がなく、咳だけが継続する場合を「咳喘息」といいます。喘息のごく軽症に属しますが、これを放っておくと喘鳴や呼吸困難が生じて重症化することがあります。風邪の後に咳だけ残っているという方の中には、軽度の喘息である可能性もあり、病院でも喘息とは気づかれにくく、見落とされやすいものです。
●大人の喘息と小児喘息
気管支喘息というと子供の病というイメージがありますが、決して子供だけがかかる病ではありません。40代60代を中心に大人でも発生させることがあります。子供の時喘息だった方のみならず、大人になって初めて喘息になるという方もいます。成人喘息の70~80%は大人になって初めて起こると言われています。
お子様の喘息の場合は、成長過程で体力がついていく中で自然と寛解へ向かっていくことがあります。一方で成人の喘息は放っておいて良くなるというものではありません。さらに大人の喘息の方が重症度が高いことが多く、ほとんどのケースで生涯にわたっての治療が必要になります。
●西洋医学的治療
そもそも気管支喘息は、発症の誘因や生じてる病態の機序はわかっていても、なぜそのような病態が生じてしまうのかという根本的な原因が未だに分かっていません。したがって気道の炎症を去る、気道を広げて呼吸を楽にさせるという対症治療を根気よく行い続けるしかありません。
基本的には発作治療薬(リリーバー)と長期管理薬(コントローラー)とを使い分けます。発作時には気管支拡張薬(β₂刺激薬)を使用し、気管支の平滑筋を弛緩させてとにかく気道の通りを確保します。最近では気道の炎症を抑えるステロイドとの合剤を用いることが一般的です。それでも呼吸機能が回復しない場合では、ステロイドの内服治療が行われることもあります。一方で長期管理に用いられるのが吸入ステロイド薬です。微量のステロイドを吸い込み、気道の炎症を継続的に抑える薬として使用します。気管支喘息は症状が収まっている時であっても気道に炎症が継続しています。したがって発作を予防するために、継続的にステロイドの吸入を行うことが一般的です。
気管支喘息と漢方
先述のように、気管支喘息はなぜそのような病が生じてしまうのかという根本的な原因が分かっていません。ダニやホコリ・ペットの毛という喘息を誘因するアレルゲンをきっかけに悪化しますが(これをアトピー型という)、これらは本来であれば炎症を起こすはずのない微弱な刺激です。また感染や粉塵・タバコの煙などで起こるタイプの喘息(非アトピー型)も、本来であれば気道の慢性炎症を起こすはずのないものです。どうしてこのような微弱な刺激で慢性的な炎症が起こってしまうのか、その原因がわからず、そこに対応することもできていないというのが現状です。
故に気管支喘息は完治することのない病として認識されています。とにかく炎症をコントロールし、症状が起きていない状態をいかに継続させるかというのが治療のメインになります。ただし本質的な気管支喘息の原因は「気道の過敏さ」にあります。微弱な刺激に対して影響を受けてしまうという体質の問題が根底にあるわけです。
●漢方治療の特徴「微弱な刺激に過剰反応しにくい体を作る」
漢方治療が狙うのは、まさにその体質に対するアプローチです。漢方では病の本質を治療する「本治(ほんち)」という手段があり、これによって気管支に炎症を起こしにくい状態へと導く治療を行います。はっきり申し上げれば、西洋医学にて解明できていない病の原因が漢方ではわかっている、というわけでは決してありません。漢方においてもなぜ微弱な刺激で炎症が起きてしまうのか、それを根拠をもって説明できるわけではありません。ただし、手段がないということではありません。ある状態においてこのような漢方薬を用いると喘息が起きにくくなるという経験則があり、それを応用することで微弱な刺激に反応しにくい体質へと導きます。そして実際の臨床においても、漢方薬を的確に選択し運用することで、確かに喘息が起こらない状態へと向かっていきます。
この経験則は長年にわたる漢方家たちの集積であるため、それを知らないで一律的に使用するだけでは改善することはできません。しかしこの経験則を掴み、それを基盤にして的確な治療を行うと、吸入ステロイド薬を使用していても繰り返していた発作が起こらなくなるということが実際にあります。そしてステロイドの吸入回数が減り、漢方薬だけでコントロールできるようになり、最終的にはあらゆる薬剤に頼らなくてもコントロールが可能になるということが現実に起こります。
●漢方治療の特徴「発作を治める治療を助ける」
気管支喘息の発作は重症化すると気道を完全にふさぎ、命にかかわる呼吸困難を発生させることがあります。したがって発作時は吸入薬をもって気道の通気を確保することは絶対です。しかし発作を短期間に何回も繰り返し、何度も吸入薬を使用する状態になると、吸入薬の効き目が悪くなったり、吸入薬の副作用にて動悸や手の震えなど他の問題を生じることがあります。
漢方薬は発作時であっても即効性をもって気道の炎症を治める手法があります。これを「標治(ひょうち)」といいます。現在生じている症状をまず抑えるという治療で、これを行うと喘息が早期に終息する傾向が出てきます。この場合、吸入薬と併用することで効きにくくなった吸入薬の効果が引き出され、さらに副作用が予防できるようになります。
最も適した治療
西洋医学では発作の段階と長期管理の段階とでは異なる治療を行うことが一般的ですが、それは漢方においても同じです。気管支喘息における漢方治療では、「標治」と「本治」とを分けて治療を行います。特に漢方治療の場合、喘息自体を生じにくい体質へと変化させるという意味において、西洋薬以上の効果を上げることが少なくありません。ただし、これは漢方薬の方が優れているとか、漢方であれば完治できるとか、そういう意味ではありません。完治が難しい病であるからこそ、西洋薬と漢方薬とがそれぞれ明確な役割をもって治療することが望ましい、ということです。
気管支喘息において最も適した治療は、西洋医学と東洋医学との併用です。そして一番重要なことは、それぞれに専門の医療機関におかかりになることです。長引きやすい・完治させることができないと言われている病ではありますが、西洋医学と東洋医学との良いところを利用することで、比較的迅速に改善へと向かい、喘息だということを意識することのない生活を送ることが可能になります。
参考症例
まずは「気管支喘息」に対する漢方治療の実例をご紹介いたします。以下の症例は当薬局にて実際に経験させて頂いたものです。本項の解説と合わせてお読み頂くと、漢方治療がさらにイメージしやすくなると思います。
症例|71歳男性・約2年前から続くこじれた気管支喘息
西洋薬(吸入薬)が手放せず、寒くなると特に酷くなる気管支喘息。息苦しさと消耗との背景に、治療上無視のできない重要なポイントがありました。正確な見極めが求められる気管支喘息治療、その具体例をご紹介いたします。
症例|17歳男の子・入試を控えた大切な時期に発症した咳喘息
テスト勉強を頑張った結果、体調を崩してしまった高校生。空咳が止まず、夕方に微熱が起こると咳がますます酷くなります。頑張り続ける体に必要なもの、その見極めが改善への決め手でした。お子さまの喘息、その治療方法の具体例をご紹介いたします。
症例|3歳男の子・治りきらない咳喘息にて体力を失った男の子
平素からのアレルギー体質にて咳喘息を発症し、肺への治療を行うも一向に改善へと向かわなかった男の子。喘息は肺の病という固定観念を捨て、おからだ全体を観ることが必要なケースでした。心配に思うお母さまと男の子との闘病の歴史。小児喘息治療の現実を、具体例をもってご紹介いたします。
参考コラム
次に「気管支喘息」に対する漢方治療を解説するにあたって、参考にしていただきたいコラムをご紹介いたします。参考症例同様に、本項の解説と合わせてお読み頂くと、漢方治療がさらにイメージしやすくなると思います。
コラム|漢方治療の経験談「気管支喘息治療」を通して
当薬局でもご相談の多い気管支喘息。日々治療を経験させていただいている中で、実感として思うこと、感じたことを徒然とつぶやいたコラムです。
コラム|【漢方処方解説】苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
立ちくらみの治療薬として有名な苓桂朮甘湯は、気管支喘息にも多く用いられる漢方薬です。ただし本方は気管支喘息の特効薬ではなく、ある体質的傾向に従って使用されることで初めて効果を発揮できる処方です。山本巌先生は、この傾向を「フクロー型体質」と呼びました。苓桂朮甘湯の使い方を詳しく解説していきます。
※具体的な治療方法をお知りになりたい方は、処方解説を飛ばし「臨床の実際」をご参照ください。
使用されやすい漢方処方
①越婢加半夏湯(えっぴかはんげとう)
②麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)
③小青竜湯(しょうせいりゅうとう)
小青竜湯加石膏(しょうせいりゅうとうかせっこう)
④厚朴麻黄湯(こうぼくまおうとう)
射干麻黄湯(やかんまおうとう)
⑤定喘湯(ていぜんとう)
⑥頓嗽湯(とんそうとう)
⑦麦門冬湯(ばくもんどうとう)
⑧半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
柴朴湯(さいぼくとう)
⑨大柴胡湯(だいさいことう)
柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)
⑩苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
真武湯(しんぶとう)
⑪平胃散(へいいさん)
五積散(ごしゃくさん)
⑫六君子湯(りっくんしとう)
⑬黄耆建中湯(おうぎけんちゅうとう)
⑭甘草乾姜湯(かんぞうかんきょうとう)
人参湯(にんじんとう)
⑮通導散(つうどうさん)
⑯苓甘姜味辛夏仁湯(りょうかんきょうみしんげにんとう)
⑰蘇子降気湯(そしこうきとう)
沈香降気湯(じんこうこうきとう)
⑱喘四君子湯(ぜんしくんしとう)
喘理中湯(ぜんりちゅうとう)
※薬局製剤以外の処方も含む
①越婢加半夏湯(金匱要略)
気管支喘息の急性発作期、呼吸困難が強く生じている状態に用いる方剤である。出典の『金匱要略』では「肺張(はいちょう)」の主方として取り上げている。喘息発作とともに強く呼吸促拍し、顔面が浮腫んで張れを伴う者。本方は麻黄・石膏・甘草の薬対をもって浮腫を去り、気道の閉塞を解除して速やかに呼吸困難や咳を止める薬方である。
越婢加半夏湯:「構成」
麻黄(まおう):石膏(せっこう):生姜(しょうきょう):大棗(たいそう):甘草(かんぞう):
②麻杏甘石湯(傷寒論)
本方も気管支喘息の急性発作期に適応する。越婢加半夏湯と同じく麻黄・甘草・石膏の薬対を有する。気道の炎症を抑え、平滑筋の緊張を緩和させ、気道粘膜の浮腫を去ることで急激に起こる呼吸困難を改善する薬方である。
越婢加朮湯は「肺張」を主として顔面の腫れが目標となる。一方で本方は「汗出でて喘」つまり頭から汗をかくなど、水がむしろ抜ける傾向がある。急性発作期、小青竜湯に移行する気配のある者が越婢加半夏湯。白虎加人参湯および麦門冬湯加石膏に移行する気配あれば麻杏甘石湯。
麻杏甘石湯:「構成」
麻黄(まおう):石膏(せっこう):甘草(かんぞう):杏仁(きょうにん):
③小青竜湯(傷寒論)小青竜湯加石膏(金匱要略)
気管支喘息を発症しやすい体質の一つとして、浮腫を生じやすい水分代謝異常がある。本方は身体に水気をはらみ、粘膜の浮腫を生じやすい体質者に適応することが多い。急性発作にて呼吸苦を起こしてすぐに気道の分泌が亢進し、ゼロゼロといった喘鳴を生じて稀薄な痰を喀出する者。顔面の浮腫とともに過剰な水があふれる、水が外に出ていくタイプの「肺張」である。小青竜湯加石膏が適応する。
小青竜湯は花粉症などのアレルギー性鼻炎に用いる薬として有名だが、むしろ気管支喘息治療において無くてはならない方剤である。「寒喘(かんぜん)」と呼ばれる気管支喘息に適応し、また加減を施すことで急性期から亜急性期、寛解以降の長期管理まで含めて幅広く適応させることができる。
小青竜湯:「構成」
麻黄(まおう):桂枝(けいし):芍薬(しゃくやく):甘草(かんぞう):半夏(はんげ):細辛(さいしん):乾姜(かんきょう):五味子(ごみし):
小青竜湯加石膏:「構成」
麻黄(まおう):桂枝(けいし):芍薬(しゃくやく):甘草(かんぞう):半夏(はんげ):細辛(さいしん):乾姜(かんきょう):五味子(ごみし):石膏(せっこう):
④厚朴麻黄湯・射干麻黄湯(金匱要略)
『金匱要略』に「肺萎肺癰咳嗽上気病」という項目がある。漢方の聖典として古い歴史を持つ書物である。この項目では肺病に対する病態を述べており、現在においてもなお気管支喘息治療に有効な方剤が掲載されている。
厚朴麻黄湯は小青竜湯加石膏に似て、発作が発生して後、気道の分泌が亢進し始め喘鳴や喀痰を伴う状態に適応する方剤である。厚朴という気管支の痙攣を緩和させる気剤が含まれている点が特徴。浅田宗伯は小青竜湯よりも降気(呼吸促拍や咳嗽を止める薬能)の力が優れると解説している。顔面の浮腫など「肺張」の傾向なく、呼吸促拍や咳の状が強い者。浅田はお金持ちでうまい物をたくさん食べ過ぎ、腹満して咳する者には大黄を加えて効ありと解説している。知っておくべき手段である。
射干麻黄湯もやはり急性発作の後、気道分泌が進んで喘鳴を伴う場で使用する方剤である。射干は清熱解毒薬に属し気道の炎症を去る薬能がある。また紫菀・款冬花は止咳平喘薬に属し、肺気を利して咳や呼吸促拍を平定する薬能を持つ。どちらかと言えば発作期以降、喘鳴が継続している亜急性期、および感染などにてやや解毒を必要とする場において用いる機会がある。
厚朴麻黄湯:「構成」
麻黄(まおう):石膏(せっこう):厚朴(こうぼく):半夏(はんげ):杏仁(きょうにん):乾姜(かんきょう):細辛(さいしん):五味子(ごみし):小麦(しょうばく):
射干麻黄湯:「構成」
麻黄(まおう):射干(やかん):紫菀(しおん):款冬花(かんとうか):半夏(はんげ):生姜(しょうきょう):細辛(さいしん):五味子(ごみし):大棗(たいそう):
⑤定喘湯(摂生衆妙方)
発作後呼吸促拍し、気道粘膜の分泌が高まり多量に痰を喀出するも、痰質が白濁粘稠で時に黄色や緑色に色づく病態を「痰熱」という。感染などが関わる気管支喘息において発生しやすい。痰熱には黄芩や桑白皮などの清肺熱薬と、桔梗か栝楼仁などの化痰薬を配合する必要がある。
本方は「痰熱」に対する麻黄剤として、粘稠な痰を喀出するとともに呼吸促拍・咳嗽上気の状が強い場合に適応する。呼吸困難の状が強く、口渇など気道の燥熱が強い場合は石膏が必要。本方に石膏を加えるか、五虎二陳湯加黄芩・桑白皮・桔梗・栝楼仁などを用いる。
痰熱は長引くと呼吸困難よりも痰咳が主となる。慢性化する咳喘息にこの病態があるが、多くは喘息というよりも気管支炎や肺炎という形でくる。こうなると止咳薬や平喘薬はあまり効かない。清熱化痰を重く用い痰を去らなければ咳が止まらない。清肺湯や清金化痰湯、括呂枳実湯や柴胡桔枳湯加減が必要になる。
定喘湯:「構成」
麻黄(まおう):桑白皮(そうはくひ):黄芩(おうごん):半夏(はんげ):款冬花(かんとうか):蘇子(そし):杏仁(きょうにん):銀杏(ぎんきょう):
⑥頓嗽湯
気管支喘息では気道狭窄後に気道の粘膜分泌が亢進し喀痰をみるが、痰の発生よりも肺の熱状が強いと、咳をしても痰がなかなか切れない・痰が切れずに苦しいといった状態に陥ることが多い。気道や口腔が乾燥し、粘膜に潤いが無くなり、少しの刺激で咳を発しやすい。多くが咳喘息という形で残るこの状態は「肺熱」「燥痰」「肺燥」という流れに乗る病態である。
頓嗽湯は「肺熱」を解除する方剤。調べたところ出典は不明。大塚敬節先生が百日咳に効があると提示し、細野史郎先生より伝を受けたと解説している。薬方の意を組めば、肺に起こる炎症を鎮めることを主とし、残存する痰を化す薬能を持つ。「肺熱」から「燥痰」にかけて、咳喘息や気管支炎などの止まない咳に運用する。また本方を柴朴湯と合して滲咳湯と呼ぶ。慢性化する気管支喘息に柴朴湯を用いるも、薬能がやや緩いという場において用いやすい方剤である。
頓嗽湯:「構成」
石膏(せっこう):桑白皮(そうはくひ):黄芩(おうごん):山梔子(さんしし):前胡(ぜんこ):桔梗(ききょう):甘草(かんぞう):(紫蘇子・杏仁・茯苓)
⑦麦門冬湯(金匱要略)
咳の治療薬として有名。粘膜の乾燥を呈し、少しの刺激で気道が敏感に反応し咳をする者。気道に潤いをつけることで肺気を降ろす薬方である。「燥痰」から「肺燥」に至る病態に用いる場がある。多くは咳喘息という形でいつまでも咳が止まない者。咳治療薬として有名で頻用されている傾向があるが、的確に用いなければ当然効果はない。「大逆上気、咽喉不利」というのが最大の目標。一旦咳をしだすと止まらず、痰が切れるまでせき込み、顔が赤く火照って最後はオエーっと胃が持ち上がりえづく者。適応すると比較的即効性をもって咳を止めることのできる薬方である。
咳喘息に本方を応用する場合、いくつかの加減をもって対応する必要がある。急性発作から亜急性期にかけて、喘鳴や客痰は無いが咳込みが強いという場においては麦門冬湯加石膏。また亜急性期において半夏厚朴湯を合わせる手法や、五味子・桑白皮を加える手法もある。さらに粘膜の損傷より咳血を生じる場合は地黄・阿膠・黄連を加える。
本方以外にも麦門冬剤は長引く咳に用いるものが多い。竹葉石膏湯は麦門冬湯加石膏に似るが、より一層熱症状を醸して首回りや頭に汗をかき、夕方から夜間にかけてせき込みが強まり寝れないという者によい。また麦門冬飲子はより深く陰分を補う方剤。故に平素より糖尿病などの傷陰の気配があって咳喘息が止まないという者に適応しやすい。
麦門冬湯:「構成」
麦門冬(ばくもんどう):半夏(はんげ):大棗(たいそう):人参(にんじん):甘草(かんぞう):粳米(こうべい):
⑧半夏厚朴湯(金匱要略)柴朴湯(本朝経験方)
半夏厚朴湯は心療内科領域において頻用される気剤ではあるが、同時に気道の緊張を緩和させ喘息を予防改善するための要薬でもある。有名な適応症状である「咽中炙臠(いんちゅうしゃれん:喉にあぶった肉が張り付いているような不快感)」とは、咽もとの緊張より発するものである。単独で用いるというよりも、多くが他方剤と合わせる形で用いられることが多い。また半夏厚朴湯には数種の類方がある。蘇葉を枳実に変え、甘草を加えたものを順気剤という。蘇葉を蘇子に、生姜を乾姜に変え、甘草を加えたものを寛中湯という。さらに寛中湯から甘草・厚朴・蘇子を去り、枳実と木香とを加えたものを治喘一方という。ともに気管支喘息に運用する場があり、病態にしたがって各々を選択する。
気管支喘息の長期管理薬として頻用されている処方に柴朴湯がある。半夏厚朴湯に小柴胡湯を合わせた本方は、特に子供の気管支喘息に運用して良い場合が多い。ただし一律的に用いてもあまり効果はない。小柴胡湯のみならず柴胡桂枝湯に半夏厚朴湯を合わせてみたり、半夏厚朴湯ではなく寛中湯を合わせてみたりとった臨機応変な対応が求められる。
半夏厚朴湯:「構成」
半夏(はんげ):茯苓(ぶくりょう):生姜(しょうきょう):厚朴(こうぼく):蘇葉(そよう):
柴朴湯:「構成」
半夏(はんげ):茯苓(ぶくりょう):生姜(しょうきょう):厚朴(こうぼく):蘇葉(そよう):柴胡(さいこ):黄芩(おうごん):人参(にんじん):甘草(かんぞう):大棗(たいそう):
⑨大柴胡湯・柴胡桂枝湯(傷寒論)
これらの方剤は「肝気鬱結(かんきうっけつ)」と呼ばれる自律神経の緊張・興奮状態を緩和させる方剤。気管支喘息ではその発症の原因に自律神経の乱れが関与しているケースが多い。これらは気道の閉塞を改善・予防するとともに喘息を生じにくい体質へと移行させていく薬能を持つ。実際の運用にあたっては、気管支喘息用に加減や合方を施すことが一般的である。半夏厚朴湯やその類方、通導散や大黄牡丹皮湯などの駆瘀血剤を合方することが多い。どのような病でも言えることだが、これらの疎肝剤を的確に運用することは漢方治療の基本である。大柴胡湯や柴胡桂枝湯のみならず逍遥散・抑肝散・四逆散などの一連の疎肝剤は、類似する処方といえども適応病態が異なる。体質的にどの薬方が最も合うかを見極めることが肝要である。
大柴胡湯:「構成」
柴胡(さいこ):半夏(はんげ):黄芩(おうごん):芍薬(しゃくやく):枳実(きじつ):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):大黄(だいおう):
柴胡桂枝湯:「構成」
柴胡(さいこ):半夏(はんげ):黄芩(おうごん):人参(にんじん):甘草(かんぞう):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):桂枝(けいし):芍薬(しゃくやく):
⑩苓桂朮甘湯(金匱要略)真武湯(傷寒論)
漢方では古くから身体の水分代謝異常を考察してきた歴史がある。飲んだ水が全身を巡らず、肺や皮膚・四肢などに溜まり漏れる病を「飲病(いんびょう)」という。また漏れた水が外に張り出す病を「水気」という。苓桂朮甘湯は「飲病」の一種「痰飲」の適応方剤として、また真武湯は「水気」の適応方剤として提示されており、これらは広く身体の水分代謝異常に用いる方剤である。
気管支喘息ではその発症の原因に、このような水分代謝異常が関与していることが多い。炎症に対して気道の浮腫を生じやすい体質を形成する。苓桂朮甘湯はこのような体質を改善する薬として、喘息治療に運用する場が多い。また真武湯はより陰証、つまり新陳代謝の低下が介在している場合に運用する。両者には陰陽・虚実の違いがある。そこを見極めて選用する必要がある。
苓桂朮甘湯:「構成」
茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):桂枝(けいし):甘草(かんぞう):
真武湯:「構成」
茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):生姜(しょうきょう):附子(ぶし):芍薬(しゃくやく):
⑪平胃散・五積散(和剤局方)
水分代謝異常に対するもう一つの解釈として「湿証」と呼ばれる病態がある。水の循環が乱れる原因の一つに胃腸機能の乱れがあり、胃腸が湿気っぽくなると、外の湿気に対しても身体の水分代謝を乱しやすくなる。特に山河の多い日本では、湿気を浴びて腹を壊して下痢をしたり、関節の痛みを生じたりする者が多い。日本後世方派はこのような「湿証」に対して平胃散という回答を出し、広く運用するようになった。
平胃散は下痢や腹の張りといった腸の機能を回復するための方剤である。消化管の水分代謝を促し、平滑筋の緊張を去る。この薬能は気道の浮腫や気道平滑筋の緊張を呈する気管支喘息に対しても合致し、喘息の長期管理薬として運用することができる。ただし多くのケースで平胃散単独よりもその加減方が用いられる。五積散はその代表である。小青竜湯のように発作を軽減する薬能を併せ持つことから、「標本兼治」つまり喘息を抑える薬能と発作を起こしにくい体質へと向かわせていく治療とを同時に行うことができる。
平胃散:「構成」
蒼朮(そうじゅつ):厚朴(こうぼく):陳皮(ちんぴ):大棗(たいそう):甘草(かんぞう):生姜(しょうきょう):
五積散:「構成」
蒼朮(そうじゅつ):陳皮(ちんぴ):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):半夏(はんげ):当帰(とうき):厚朴(こうぼく):芍薬(しゃくやく):川芎(せんきゅう):白芷(びゃくし):枳殻(きこく):桔梗(ききょう):乾姜(かんきょう):桂枝(けいし):麻黄(まおう):甘草(かんぞう):大棗(たいそう):
⑫六君子湯(医学正伝)
胃腸薬として有名な本方は、気管支喘息の長期管理薬として効果的な方剤である。「脾胃(ひい)の虚」と呼ばれる消化管の弱りに対して適応する。胃腸機能の弱りは免疫力を下げ、身体の水分代謝を悪化させることから気管支喘息発症の原因に関与すると考えられる。実際に本方を長服していくことで、症状が軽快するとともに吸入薬なしで発作をコントロールできるようになる傾向がある。発作を起こしたり症状が悪化すると、食欲がなくなりものを食べられなくなる者。平素より少食で胃もたれしやすく、貧血の傾向がある者。本方をもってこのような弱さが軽減されてくる者は、同時に喘息が収まりやすく、かつ起こしにくくなる。
六君子湯:「構成」
人参(にんじん):甘草(かんぞう):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):生姜(しょうきょう):大棗(たいそう):陳皮(ちんぴ):半夏(はんげ):
⑬黄耆建中湯(金匱要略)
「虚労(きょろう)」という一種の疲労状態に用いる方剤。疲労とともに自律神経が乱れ、身体が過緊張状態に陥りやすくなる病態の流れを「虚労」という。気管支喘息の長期管理期において、発作がなかなか起こらなくならない・根詰めて頑張りすぎると咳が止まらなくなるといった時に、この「虚労」の状態に陥ってるケースがある。そのような場合に本方を服用すると、身体がリラックスして良く眠れるようになると同時に咳が起こらなくなる。基本的には数種の加減を施すことで対応する。特に肺に弱りのある者は気道に炎症が起こりやすく、上気(咳や呼吸苦)が起こりやすくなる。半夏を加えて上気を納め、気の消耗を止める。
黄耆建中湯:「構成」
黄耆(おうぎ):桂枝(けいし):芍薬(しゃくやく):甘草(かんぞう):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):膠飴(こうい):
⑭甘草乾姜湯(金匱要略)人参湯(傷寒論)
水分代謝異常はその状態が深まると「冷え」に帰結する。身体冷えて血行循環が悪く、そのため水が巡らず浮腫みを生じる。甘草・乾姜を基本とした方剤群は身体を温めて血行循環を促し、内在的な浮腫を去ることで気管支喘息を改善する。喘息に頻用される小青竜湯も広く見ればこの構成を骨格にもつ処方の一つである。
甘草・乾姜の2味で構成される甘草乾姜湯は、気管支喘息の発作に著効することがある。平素より冷え性で首や胸回りが冷えて寒気を嫌い、冷えるとトイレに何度も行き小便を多量に出すという者。冬になると夜間喘息が起こり、首回りが寒くて寝れず、夜間尿のために何度も起きるという者。就寝前に甘草乾姜湯を服用しておくと、身体が温まり喘息を起こすことなく熟睡できるようになる。また特に胃腸が冷えやすく、冷飲食で胃痛や下痢を起こすという者では人参湯を長服すると良い。身体が温まり食欲が増し元気が出てくるとともに、喘息の発作が起こらなくなる。
甘草乾姜湯:「構成」
乾姜(かんきょう):甘草(かんぞう):
人参湯:「構成」
乾姜(かんきょう):甘草(かんぞう):人参(にんじん):白朮(びゃくじゅつ):
⑮通導散(万病回春)
気管支喘息は通常、気道の狭窄が起きても可逆的である(気管支拡張薬などで気道が広がる)。しかし炎症のコントロールがうまく行かない状態が長期的に継続すると、気道の壁が厚く・硬くなり、気道の狭くなった状態で固まってしまうことがある。これをリモデリングという。この状態、もしくはこの状態に至るまでの過程を「瘀血(おけつ)」とみなし、本方のような駆瘀血剤をもって気管支喘息の長期管理を図る手段がある。
また発作期においても本方のような駆瘀血剤が持つ「下法(げほう:大便の通じを促すことで炎症を早期に改善させる手法)」という効能を用いることがある。浅田宗伯・湯本求真・山本巌先生など、多くの臨床家が喘息発作に対する下法の重要性を示唆している。本方のような駆瘀血剤のみならず、大柴胡湯や防風通聖散も下法を行う方剤であり、これらの運用によって麻黄・石膏にて止まない発作が鎮圧されることがある。
通導散:「構成」
当帰(とうき):枳殻(きこく):厚朴(こうぼく):陳皮(ちんぴ):木通(もくつう):紅花(こうか):蘇木(そぼく):甘草(かんぞう):大黄(だいおう):芒硝(ぼうしょう):
⑯苓甘姜味辛夏仁湯(金匱要略)
本方は小青竜湯と並び、気管支喘息に運用されやすい方剤。しかし著効させるためには立方の意図から病態を的確に掴むことが必要である。
本来、本方は小青竜湯服用後の副作用に対して作られた方剤である。麻黄剤による「発陽(はつよう)」過剰により、のぼせ・動悸・手足の痺れなどを生じた際に用いるべき方剤群の一つ。これは明らかに麻黄が心臓に負担を強いたために起こる症状で、本方は心臓の機能を是正しつつ肺気を平する薬能を持つ。したがって気管支喘息における本方の運用は、麻黄剤を使うことのできない心臓の弱りを持つ方に対して意義がある。麻黄を必要とする人では麻黄剤を用いなければ発作は止まない。そのような方ではいくら本方を用いても効果が現れない。しかし麻黄剤を使いにくいケースにおいて本方は有意義な効果を発揮する。発作時は大黄を加え「下法(げほう)」をもって肺気を鎮降させ、長期管理においては本方をもって服用を継続すると良い。
気管支喘息において、心機能に弱りがあるかどうかは必ず確認するべきことである。これは西洋医学でも東洋医学でも変わらない原則である。漢方では古くから麻黄が使えない「喘」、つまり心機能の弱りを介在させる「喘」に対して如何に対応するかという考察が積み重ねられてきた。本方のみならず以下にあげる処方群は、心機能の弱りを持つ者の喘に対応するために考案されたものである。
苓甘姜味辛夏仁湯:「構成」
茯苓(ぶくりょう):甘草(かんぞう):乾姜(かんきょう):五味子(ごみし):細辛(さいしん):半夏(はんげ):杏仁(きょうにん):
⑰蘇子降気湯・沈香降気湯(太平恵民和剤局方)
心機能の弱りを介在させる「喘」に運用し得る薬方として、降気湯類という一連の処方群がある。これらは胸に鬱滞する水・気を降ろすというもので、心機能の弱りにより発する呼吸困難やゼロゼロといった喘鳴、痰のからまる咳を起こす者に適応する。これらの処方群は浮腫の程度に合わせて選用する。
浮腫が強い場合は七味降気湯加減が良い。茯苓や木通といった利水薬を配合し、喘息以外にもうっ血性心やネフローゼなどの腎性浮腫にも用いられてきた。蘇子降気湯はどちらかと言えば呼吸苦よりも喘鳴と咳嗽(せき)の治療薬である。以前心疾患にかかり、手術などの処置によって問題は無くなったものの、喘鳴や咳嗽が続いて痰切りの薬や咳止めが効かないという者に奏効することが多い。沈香降気湯は気剤の総目として、胸が詰まり喘を発する者に適応する方剤。浅田宗伯がそう称するほど、広く運用し得る薬方である。宗伯は左金丸(黄連・呉茱萸)を合する時は降気の力最も強とす、と解説している。呉茱萸をもって止めるべき「喘」というものは確かにある。胸満衝逆に対する呉茱萸の運用は、九味檳榔湯加呉茱萸・茯苓や桑白皮湯など、脚気衝心が流行した江戸時代の医家たちによって研究されてきた。
蘇子降気湯:「構成」
桂枝(けいし):甘草(かんぞう):厚朴(こうぼく):陳皮(ちんぴ):紫蘇子(しそし):半夏(はんげ):生姜(しょうきょう):前胡(ぜんこ):当帰(とうき):大棗(たいそう):
沈香降気湯:「構成」
沈香(じんこう):香附子(こうぶし):縮砂(しゅくしゃ):甘草(かんぞう):
⑱喘四君子湯・喘理中湯(万病回春)
気虚の代表方剤である四君子湯の加減。胃腸が弱く、疲労してすぐに体がだるくなり、面色がくすんだ黄色味を帯びるか又は白く、貧血の傾向があって気力がわかない。これを「気虚」という。本方はこのような気虚にて「短気(呼吸が浅く、呼吸の幅が狭い。呼吸困難の一種。)」を起こしている者に適応する。
気管支喘息において気虚を呈する者であれば、六君子湯や補中益気湯にて足る。喘四君子湯を運用する意図は、降気湯の方意を内包している点にある。つまり気虚を呈するとともに、心機能に弱り有り、胸部に浮腫を生じて喘急しやすい者。また気虚のみならず「陽虚」を呈する者であれば喘理中湯を用いる。理中湯との違いはやはり降気湯方意の有無。胸部に水蓄しやすい状態を目標にして運用するべき方剤である。
喘四君子湯:「構成」
人参(にんじん):甘草(かんぞう):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):厚朴(こうぼく):陳皮(ちんぴ):紫蘇子(しそし):桑白皮(そうはくひ):縮砂(しゅくしゃ):木香(もっこう):陳皮(ちんぴ):沈香(じんこう):
喘理中湯:「構成」
乾姜(かんきょう):甘草(かんぞう):桂枝(けいし):厚朴(こうぼく):紫蘇子(しそし):沈香(じんこう):木香(もっこう):縮砂(しゅくしゃ):橘皮(きっぴ):
臨床の実際
ここからは、漢方にてどのように気管支喘息を捉え、改善していくのかを具体的に解説していこうと思います。気管支喘息に効果があると言われている漢方薬をただ一律的に服用しているだけでは改善へと向かうことはできません。喘息を的確に改善できる先生方は、病態を把握し弁別する手法を必ず持っています。その一旦をここで示してみたいと思います。
<気管支喘息における漢方治療の実際>
漢方ではゼロゼロといった喘鳴を伴う呼吸困難を「哮喘(こうぜん)」といいます。重症の呼吸不全から命を落とすこともあったこの病は、漢方においても古くから研究が積み重ねられてきました。区別するべき病態や適応する方剤も多岐にわたりますが、哮喘治療は大きく2つの段階に分けて行います。
●発作時と長期管理時とで治療を分ける
西洋医学的治療と同じように、漢方においても発作時の治療と長期管理時の治療とでは手法が変わります。発作時ではとにかく気道に起こる炎症を抑え、気道の通気を確保する必要があります。体質云々よりも先ず現在起こっている症状を抑える、これを漢方では「標治(ひょうち)」といいます。一方で発作の頻度・程度ともに落ち着いている状態では、発作を起こさないような状態へと導いていく必要があります。病の本質的治療を行うという意味で、これを「本治(ほんち)」といいます。
一般的に気管支喘息では「標治」に用いる薬方と「本治」に用いる薬方とが異なります。まずはこの違いを意識することが大切で、段階を踏んだ治療を行うことが重要です。その方が漫然と漢方治療を行うよりも、多くのケースで即効性が高いからです。「漢方薬には即効性がある」と解説しておられる先生方であれば、この2つは必ず区別して治療を組み立てているはずです。
ただし「標治」と「本治」とは微妙に重なる部分もあり、発作を改善できる方剤を長期服用することで体質が変化し、発作が起きなくなるということもあります。この辺りは各患者さんの状態によって治療手法が異なるところです。大切なのは各個人に合わせて最も良い治療計画を組み立てることで、常道を理解し時に臨機応変にそれを変化させることで、最も効果を発揮しやすい方法を選択していきます。
1.気管支喘息における漢方治療の「標治」
発作時、気道の炎症が強くなると気管支の平滑筋が緊張して痙攣し、気道の粘膜に浮腫が起こって腫れ、痰が分泌されて気道を塞ぐことで呼吸が困難になります。したがって西洋医学においては気管支拡張薬(β₂刺激薬)で気道の緊張を緩め、ステロイドで炎症を抑える治療を行います。ただし発作が何度も繰り返されるようになると、これらの吸入薬が効きにくくなります。またこれらの吸入薬の連用は動悸や手の震えといった副作用を起こすことにもつながります。
漢方における「標治」つまり発作時治療は、これらの吸入回数を増やさないという意味で非常に有意義です。常用量の吸入では発作が収まらないといういう場合では、西洋医学的な内服治療へと移行する前に漢方薬の併用を検討するべきです。漢方薬を的確に選択することができれば即効性もあります。重要なのは何よりも的確に選択できるかどうかです。
●漢方における発作治療の基本
発作治療に用いられる漢方処方には共通して以下のような薬能を持つ生薬が組み合わされています。
〇気道の炎症を抑える:石膏・桑白皮・知母・黄芩など
〇気道平滑筋の緊張を緩和させる:麻黄・厚朴・芍薬など
〇気道粘膜の浮腫を去る:麻黄・杏仁・蘇子・細辛・茯苓など
〇興奮を収めて咳を止める:半夏・款冬花・百部など
発作における呼吸困難の原因は、気道の炎症と気管支平滑筋の緊張、さらに気道粘膜の浮腫です。西洋医学にて解明されたこの病態が、古人に分かっていたわけではありません。しかし漢方では経験的にこれらに対応する手段が発見されていました。そして上記のように発作時の病態に対して現代医学でも矛盾なく対応し得る方剤が作られてきました。
漢方における発作治療の基本は、これらの生薬を総合的に含む処方をもって対応するという点と、あと一つ、炎症の段階や種類・程度に合わせて薬方を選択するという点です。漢方では炎症初期の最も勢いの強い状態を「熱喘(ねつぜん)」といい、さらに「寒喘(かんぜん)」・「痰熱(たんねつ)」・「燥痰(そうたん)」という病態に弁別することが基本になります。
1)発作初期
喘息の発作が強く起こる時は、気道の炎症が強まるとともに、気管支平滑筋が緊張し、かつ気道に強い浮腫が生じることで気道が狭くなり、ヒィーヒィーといった呼吸困難(息が吐けない状態・呼気性の呼吸困難)を生じます。また発動初期では気道の炎症性浮腫が先に起こり、粘液分泌はしばらく経ってから高まります。そのため初期は痰があっても気道の熱のために白濁粘稠で、客痰はほとんど起こりません。痰が少なく喘鳴もあまりない。呼吸困難が主でとにかく息苦しい。この状態を漢方では「熱喘」といいます。
「麻黄・石膏」の組み合わせをもって対応します。石膏で炎症を取りつつ、麻黄で平滑筋の緊張を緩和させるとともに粘膜の浮腫を去ります。越婢加半夏湯・麻杏甘石湯などを用いることが一般的です。呼吸困難とともに顔が腫れて浮腫んでいる場合は越婢加半夏湯を用います。浮腫むというよりは、頭から脂汗が出て水が抜けていく者では麻杏甘石湯を用います。
2)痰の発生から炎症の継続
急性発作以降、呼吸促拍が継続していくと、気道分泌が亢進して痰が発生し、ゼロゼロといった喘鳴を生じてきます。この時発生する痰は、炎症の程度や質によってさまざまに変化します。漢方ではどのような痰が発生してくるかによって病態を弁別することが一般的です。
また急性から亜急性に移行するにしたがって、炎症が継続するものの、炎症が強まろうとする勢い自体は自然と落ち着いてきます。強力に呼吸困難を生じるというよりは、そこまで至らない程度の咳や息苦しさを断続的に発生させやすくなります。このような段階になると喘息発作治療の要薬である「麻黄」の適応から外れることがあります。麻黄は「発陽」といって、生体が異物を外に出そうとする勢いの強い状態に同調することで初めて薬能を発揮させます。したがってこの反応が落ち着いてきた段階ではむしろ清熱を主とするべきで、麻黄によって陽を発するとおさまりつつあった炎症の勢いが再度活発になってしまうことがあります。この反応は特に「痰熱」や「燥痰」と呼ばれる病態において見られることがあり、注意が必要です。
●「熱喘」から「痰熱」へ
急性発作期からしばらく時間が経つと、粘液分泌が亢進してた痰沫を吐くようになります。その時強い炎症のために分泌された痰が灼焼され、濃く粘稠な痰を喀出する病態を「痰熱」といいます。粘稠な痰を吐くと同時に、白濁から黄色・緑色に痰が色づくこともあります。非アトピー性、特に感染により起こるものや粉塵を吸い込むことで発症する場合に見受けられるケースですが、多くは慢性化した咳喘息、もしくは喘息というよりも気管支炎や肺炎にて見られる病態です。この場合、石膏と同時に黄芩などの清熱薬や桔梗や栝楼仁などの化痰薬を配合する必要があります。定喘湯や五虎二陳湯加減を用いることが一般的です。
また亜急性期に移行し、呼吸困難はそれほど強くないが、濃く固まった痰を多く吐き、痰を出すために咳が続いているという状態では麻黄は用いません。清熱化痰を主として治療を行います。すなわち、清肺湯や清金化痰湯・栝楼枳実湯などを用いて気道の炎症を去り、痰の発生を抑制します。
●「熱喘」から「燥痰」へ
急性発作期を過ぎて後、痰の分泌が亢進する段階になったものの、痰が過剰に喀出されるというよりも痰が詰まってなかなか切れず、むしろ粘膜が焼かれて乾燥状態が主として現れてくることもあります。痰がコロッと塊のような形状になり、いくら咳をしても痰が切れず、やっと切れたかと思うとバチンと胸が痛むという方もいます。また痰はほとんどなく、ただ空咳が続いて止まないという方もいます。慢性化すると気道に傷がついて痰に血が混じるということもあります。これらの病態は呼吸困難というよりは咳嗽が主で、時に「咳喘息」という形で症状を長引かせます。強い炎症が肺に起こっていますので、清熱が主となり、痰の発生している場合では化痰を行います。そして同時に潤燥と言われる粘膜に潤いをつける薬物を配合して治療を行う必要があります。また亜急性期において燥の状態を強く介在させている場合では、利水薬である麻黄は使いません。むしろ燥を助長させてしまうこともあるため、他の手段を用いて咳を止めます。
「熱喘」から「燥痰」へと移行する気配があるものの、未だ気道の炎症性浮腫のために呼吸困難や咳をしている場合では麻杏甘石湯が適応します。白虎加人参湯を加えることもあります。その後、気道の浮腫が去り呼吸困難は収まったものの、逆に気道の乾燥感が強くなって咳が続き、塊のような痰が見られる場合には、やはり痰熱と同じように清肺湯や清金化痰湯を用います。これらの薬方には麦門冬などの滋潤薬も配合されているため、ある程度の乾燥状態にも適応することができます。しかし痰がほとんどない場合では清熱と潤燥が主となります。頓嗽湯合瀉白散や麦門冬湯加石膏を用います。
「燥」の状態は炎症が慢性経過するほどに生じやすくなってきます。特に感染初期に大量に汗をかいた方や、もともと陰分(身体の潤い)の少ない方、また糖尿病などが背景にある方ではさらに生じやすくなります。慢性経過する乾燥性の咳嗽を止める手段は漢方では多く研究されてきた所で、適応する方剤も多種に及びます。竹葉石膏湯や麦門冬飲子などが有名です。また「燥」を伴う熱はより深く粘膜を傷つけ、血痰を生じさせることがあります。その場合では寧肺湯などの止咳・止血薬を用いることもあります。
●「寒喘」
気管支喘息において最も頻発する病態は「寒喘」です。サラサラの希薄な痰が多量にでる・寒冷の刺激で発作が強まる・寒さを嫌う・冷え性がある、という方を「寒喘」と捉えることが多いのですが、「寒喘」とは冷えという要素のみならず、本質的には身体の血行不良を生じやすい体質がこの病態の形成に関与しています。
もともと血行を促す力が弱い方は、充分な免疫機能を発揮できなくなります。主に免疫の役割を担うものは白血球です。そして白血球は血液に乗って運ばれ、必要部位に到達してはじめてその働きを全うします。したがって血行不良を持つ方は免疫機能を充分に発動させることが難しくなり、外的刺激に対して炎症を起こしやすく、また炎症をおさめにくくなります。また血行の弱りは身体の水分循環を低下させ、至るところに内在的な浮腫を生じさせます。すなわち気管支喘息において気道粘膜の浮腫が起こりやすくなり、また多量の痰を発生させやすくなります。血行が弱ければ当然冷えやすくなります。寒冷により発生し、寒性に属する病態という意味で「寒喘」と言われていますが、本質的には血液循環の弱さを持つ方が生じる病態であり、そのような体質を持つ方では気管支喘息が発症しやすくなります。
通常、気管支喘息の急性発作期では呼吸困難が主で、痰の発生はしばらく経過した後に高まります。しかし「寒喘」を発生させる方ではすぐに痰の分泌が高まり、呼吸困難とともにゼロゼロ・ヒューヒューといった喘鳴を直ちに発生させます。強力な炎症が生じる前に痰が伴いますので、痰はあまり灼焼されずサラサラで希薄な質となります。この場合に頻用される処方が小青竜湯加石膏や厚朴麻黄湯です。
「寒喘」は長期化した場合であっても小青竜湯を適宜加減することで対応することができます。小青竜湯加附子、小青竜湯去麻黄加杏仁など、多彩な加減方をもって対応されます。小青竜湯は花粉症の治療薬として有名ですが、実際には気管支喘息において非常に重要な方剤です。また一部血行不良が強い方では麻黄附子細辛湯や桂姜棗草黄辛附湯、真武湯などをもって対応する場合があります。
3)気を付けるべき病態「心機能の弱り」
気管支喘息の急性期から亜急性期にかけて、呼吸困難を主として咳や喘鳴が頻発しているケースでは、先ずは「麻黄」を使うことができるか、というのが一つのポイントになります。「麻黄」は使わないといけない時にはこれがないと効きません。また迅速な効果を発揮するための要薬でもあります。ただし、使ってはいけない時に使うと効果がないばかりか副作用を起こすことがあります。このような麻黄禁忌の病態として重要なのが「心機能の弱り」です。
●心機能の弱りと喘息
心機能が弱ると呼吸困難が発生します。そして心機能の急激な弱りから喘息を発生させる疾患を心臓性喘息といいます。気管支喘息に使うβ₂受容体刺激薬は、心機能の弱りを助長させるため、心臓性喘息では絶対に使いません。つまり気管支喘息と心臓性喘息とは、病態・治療方法がまったく異なるため、西洋医学においても慎重に弁別されています。
漢方においても麻黄は心機能に負担をかけることがありますので、心臓の弱りが介在している場合では麻黄剤を使用するべきではありません。喘息に心機能の弱りが関与していないか、これは西洋医学と同じように漢方においても必ず気を付けなければいけないポイントです。時に問題となるのは、西洋医学的に心機能の弱りが無いと判断され、気管支喘息の治療を行っている場合であっても、若干の心臓の弱りを介在させている場合がある、ということです。特に吸入薬を長期使用していても症状が十分にコントロールされていない難治性の喘息においてこのケースが散見されます。気管支喘息と診断されているからといって麻黄剤をむやみに使用すると、喘息を悪化させるのみならず、心臓に負担をかけて心不全を悪化させることがあるため慎重に弁別する必要があります。
漢方では古くから麻黄の使えない喘息に対してどのように対応するか、という考察が積み重ねられてきました。それに対する回答の一つが苓甘姜味辛夏仁湯であり、また各種降気湯の類です。また江戸時代に流行した脚気衝心と呼ばれる急激な心不全に対応するための手法が、この場合に応用できます。このような肺にとどまらない全身的な病態への対応が、喘息の改善にむけて非常に重要になってきます。(詳しくはうっ血性心不全をご参照ください。)
2.気管支喘息における漢方治療の「本治」
気管支喘息を発症させる根本的な原因は未だに分かっていません。何らかの理由で気道が過敏に反応しやすい状態を形成していることが理由だと考えられています。発作が鎮まりほとんど症状が無い状態であっても、微弱な刺激に反応して気道に炎症が継続しつづけています。そのため吸入ステロイド薬をいつまでたっても手放せず、病院でも使い続けないといけないと説明されることが多いようです。
気管支喘息治療を根本的に解決するには時間がかかります。これは漢方においても同じです。しかし吸入薬を使っていても症状がコントロールできない方や、吸入薬を手放したい方にとって、漢方治療が非常に有意義な効果を上げることが多々あります。漢方では病の本質を治療していく手法を「本治(ほんち)」といいます。気管支喘息は未だに原因不明の病ではありますが、漢方には肺のみではなく、人体をより広く観るという手法があり、そのような視点をもって病態を把握すると、明らかに病める部分が見えてきます。そしてそこにアプローチして治療を行うと、喘息の症状が着実に改善され、ゆくゆくは吸入薬が無くても症状や発作が全く起こらないという状態まで導くことができます。
漢方の視点から見た時、気管支喘息の根本病態は、自律神経の乱れ・水分代謝失調・胃腸機能の弱り・血行障害という4点に帰結してくる傾向があります。そしてこれらを漢方特有の概念に置き換えるならば、以下のような病態として解釈されます。
〇気滞および肝気鬱結(かんきうっけつ)
〇痰飲(たんいん)・湿証
〇脾胃(ひい)の虚
〇瘀血(おけつ)
漢方においてはこれらの失調を是正することで、気管支喘息を根治に近づけていきます。
1)気滞および肝気鬱結
ここでいう「気」とは、空気を吸い・吐くという肺の機能・活動と捉えて良いと思います。気管支は平滑筋という筋肉によってその状態を維持していますが、これは自律神経の働きによって調節されています。したがって緊張や興奮といった交感神経の緊張状態を継続させている方では、気道が過敏に反応しやすい状況を形成してしまい、気管支喘息を発症させる原因を形成していると考えられます。
ストレスを受け緊張すると喘息を発しやすい、イライラしたり寝つきが悪いと喘息が発症する、などの訴えを持つ方の中にこのような「気滞」つまり自律神経の緊張状態を介在させているケースがあります。気管支平滑筋の緊張を去る「厚朴」や「芍薬」、同時に気道粘膜の浮腫を去る「紫蘇葉」「紫蘇子」「陳皮」といった気剤を用いることが一般的です。また緊張や興奮を生じやすい体質のベースとして「肝気鬱結」というある種の緊張状態を継続させている方もいます。用いられやすい方剤としては半夏厚朴湯を筆頭に小柴胡湯との合方である柴朴湯や、柴胡桂枝湯・大柴胡湯・逍遥散がありあます。それぞれ適応する病態にはポイントがあり、それを見極めながら方剤を選用します。
肺の緊張状態は、胃活動の不調と関連します。そして多くのケースで気管支喘息の根本病態が胃に帰結してきます。これらの方剤は総じて胃・肺の緊張を解除する薬であり、心下(胃部)の状態を勘案しながら薬方を選択することが一般的です。
2)痰飲・湿証
●「痰飲」
漢方では「飲病(いんびょう)」という概念があります。飲んだ水が身体を巡らず、ある部分に漏れ・溜まってしまうという病です。広く水分代謝異常を生じる病に応用される概念ですが、気管支喘息においてもこの「飲病」、特に飲病中の「痰飲」として解釈すべき病態があります。
最も頻用される方剤は苓桂朮甘湯です。気管支喘息の本治において使用されますが、効果を発現するためには各種の加減をもって対応する必要があります。身体が浮腫みやすい・気圧の変化によって発作が起こりやすいといった症状は、水分代謝異常を持つ方に頻発します。苓桂朮甘湯は身体に蓄積した浮腫を去り、血行を促し自律神経の安定を図る効能があります。朝起きると体がだるい・午前中に頭が重い・立ちくらみ・動悸・息苦しさなどを生じるものの、夕方から夜間にかけて元気になるといったエンジンのかかりにくい方に適応することの多い方剤です。その他、本方は心臓の負担を軽減する薬能も持ち合わせています。したがって気管支喘息と心臓性喘息の両者に運用することができ、その意味でも使いやすい方剤であると言えます。
「痰飲」に属するものは、気管支喘息において最も頻度が多いという印象です。素体に「痰飲」があり、発作時に「寒喘」を発症するというケースが最も典型的だと思います。「痰飲」に属する喘息では、苓桂朮甘湯の他にも真武湯を用いるべき病態がり、この辺りは陽気の状態を見極めて薬方を選択していきます。
●「湿証」
また身体の水分代謝異常を「湿証」と解釈することもあります。どちらかと言えば日本、特に後世方派と呼ばれる流派において頻用された解釈で、平胃散を基本に組み立てた処方をもって対応します。平胃散は下痢などに使われる腸の薬で、消化管の水分代謝を促す作用があります。また厚朴や陳皮といった理気薬を配合し、平滑筋の過緊張状態を緩和させる薬能も併せ持ちます。気管支喘息においては平胃散を加減し、五積散という形で運用されることが一般的です。五積散は小青竜湯と対比されることが多く、身体を温め血行循環を促すことで「寒喘」に適応する方剤です。発作時の平喘のみならず、長服することで喘息を生じにくい体質へと向かわせることもでき、その意味で「標本兼治」を施す薬だと言えます。
3)脾胃(ひい:消化機能)の虚
漢方では胃腸機能の弱りが病の本質であるという考え方が古くから存在します。現在、身体の免疫と腸内細菌との関連が注目されていますが、実際に下痢をしやすい・食欲が無くなりやすいといった胃腸機能の弱さを持つ方に、気管支喘息などのアレルギー性炎症が発生しやすい傾向があります。そして何度も発作を繰り返し、なかなか喘息がコントロールできないという場において、漢方薬をもって胃腸機能を是正すると、たちまち喘息が起こらなくなるということが良く起こります。気管支喘息の長期管理において、漢方では数々の手法がありますが、結局のところは胃腸の弱りを正すということに帰結してくる印象があります。
咳や呼吸苦の頻度が高まったり、発作が起こったりすると、決まって食欲がなくなる。また普段から少食で食べると胃もたれしやすく体力が無い、という方では脾胃の虚を疑います。六君子湯の加減などを用いて対応すると、胃腸の不快感が改善されるとともに、喘息が起こりにくくなります。また長期的に服用を続けると体力がついて気持ちも活発になり、体が強くなって風邪などを引かなくなります。特に小児喘息において脾胃の虚を改善しておくことは非常に重要です。病気にかかりやすいという体質自体が、劇的に改善することが多いからです。
●脾胃の虚と「虚労」
胃腸機能の弱りとともに疲労感が顕著な場合は、補中益気湯や小建中湯などが用いられます。特に小建中湯は「虚労(きょろう)」と呼ばれる自律神経の乱れを伴う疲労状態に適応する方剤です。人は疲労すると自律神経の緊張や興奮がおさめにくくなり、筋肉の緊張や痙攣をおこしやすくなります。小建中湯の骨格である桂枝加芍薬湯は、このような緊張を緩和させる主剤であり、小建中湯や黄耆建中湯という形で加減を施して運用すると、緊張や疲労が取れるとともに比較的速やかに喘息の症状が起こらない状態へと向かっていきます。
これらの方剤には使い方があり、それぞれの特徴を掴みながら的確に運用することが重要です。疲労と聞けば補中益気湯を出す、子供をみれば小建中湯を出す、食欲がないと聞けば六君子湯を出すといった一律的な用い方では、これらの方剤の本当の薬能を発揮させることはできません。それぞれの薬方には作られた意味があります。これを解釈しているかどうかで運用に明らかな違いが出てきます。
●脾胃の虚と「冷え」
脾胃の活動が弱り、さらに腹中の血行が弱まると、消化管に「冷え」が生じてきます。そしてその冷えは肺も同時に冷やし、それによって気管支喘息を生じやすい体質を形成させます。冷たいものの飲食でお腹を冷やすとすぐに腹痛・下痢する。普段から冷え性で特に首回りや胸回りが寒い。冬は常に首になにか巻いていないと居られない。眠る時はタオルを首に巻いていないと寝付けないなど。このような症状を持つ方は、消化管と肺に冷えがある方です。
単純に漢方薬をもって肺と消化管を温めると、喘息が速やかに解消されます。服用後すぐに体がポーっと温まる感覚を受け、それと同時に息苦しさや咳が解消されます。漢方において「肺中冷」と呼ばれる病態で、甘草乾姜湯を基本に処方を組み立てます。甘草と乾姜の2味からなるこの処方だけでも、急性発作を即効性をもって収めることがあります。肺の冷えは胃腸の冷えに関連します。したがって冷えると胃が痛くなりやすい、冷えて下痢しやすいといった方では、甘草乾姜湯の変方である人参湯が適応します。
4)瘀血
気管支喘息は、気道の狭窄が可逆的である(狭くなるがβ₂刺激薬によって広くもなる)というのがその定義です。もし不可逆的ならば慢性閉塞性肺疾患(COPD)のように肺に構造上の異常があります。ただし気管支喘息においても長期的にコントロールしにくい状態が継続すると、度重なる炎症によって気道の壁が厚く硬くなり、気道が狭くなった状態で固まってしまう「リモデリング」という状態に陥ることがあります。こうなると治療が難しく、気道がもとの状態には戻らないと言われています。
この状態、もしくはこの状態に至る過程を「瘀血」と捉え、駆瘀血剤をもって治療を施すという手法があります。山本巌先生が示された手法で、防風通聖散合通導散に半夏・厚朴・枳実・葛根という形で使うと解説されています。通導散のような駆瘀血剤には大黄・芒硝といった便通を促す薬が配合されています。通じをつけることで炎症を去って興奮を落ち着け、血行循環を促すわけです。これを「下法(げほう)」といいます。
「下法」を行うと即効性をもって炎症を去ることができます。喘息の発作を高頻度で繰り返している方では、通常は麻杏甘石湯や小青竜湯などを用いますが、この「下法」をもって対応するという手段があります。通導散や大黄牡丹皮湯などの駆瘀血剤のみならず、大柴胡湯によって下すこともあります。また浅田宗伯は厚朴麻黄湯に大黄を加えて効ありとし、さらに湯本求真は喘息発作は下さないと止まらないという意味の見解を示しています。麻杏甘石湯や小青竜湯ではおさまらない喘息発作に対して、一つの手法として知っておくべきだと思います。
3.西洋薬との併用について
先に述べたように、気管支喘息において最も良い治療は西洋医学と東洋医学との併用だと考えます。しかしいつまでも吸入薬を使用することに抵抗があるという方も多く、そのお気持ちも強く納得するところです。特にステロイドという薬には副作用が強いというイメージがありますので、躊躇されている方も多いと思います。
●吸入ステロイド薬の正しい知識
西洋医学的治療を行わなくてすむよう、漢方治療を行いたいという方では、漢方薬のみで症状がコントロールできるよう努めます。そして同時に、吸入薬の正しい知識を持っておくことも大切です。吸入ステロイド薬は微量のステロイドを吸い込み、気道の炎症を抑える薬です。気管支拡張剤(β₂刺激薬)が比較的素早く効き目を発揮するのに比べて、ステロイドの吸入は微量であるためにそれほど即効性はありません。したがってある程度炎症が落ち着き、長期的管理が必要となるケースにおいて主として使用されます。吸入ステロイド薬は副作用が強いというイメージがありますが、現実的には微量かつ気道に直接効果を発揮するため、内服薬などに比べればずっと副作用の心配は少なくてすみます。また吸入ステロイド薬の登場により、発作を未然に防げるようになり、喘息にて命を落とすケースが年々減少傾向にあることを考えれば、非常に有意義な治療薬であると言えます。
私見では漢方薬を併用していれば、それほど怖がることなく吸入薬を続けた方が良いと思います。漢方薬にて体調が良くなれば、そのうち吸入薬を使い続けることなく症状がコントロールできるようになるからです。そして効きにくくなった吸入薬が速やかに効くようになり、全体としての治療期間も短くてすむようになります。
ただし吸入ステロイド薬は気道に直接作用することのできる薬ですが、鼻腔や副鼻腔・咽喉などの上気道にはどうしても付着します。使用後のうがいが非常に重要ですが、もともと慢性副鼻腔炎や慢性咽頭炎がある方では、ステロイドの長期使用によってどうしても免疫力が下がり、これらの病が治りにくくなります。当薬局でも吸入ステロイドの長期連用により喘息は落ち着いているが副鼻腔炎がひどいという方がしばしば来局されます。その場合はステロイドの吸入回数を減らしていくために、漢方薬をもって喘息と副鼻腔炎とを同時に改善していきます。このように上気道に合併症がある場合においては、漢方治療を優先的にお試しになるべきだと思います。
関連する記事
アレルギー性鼻炎・血管運動性鼻炎
副鼻腔炎・蓄膿症・後鼻漏
非結核性抗酸菌症(肺MAC症)
アトピー性皮膚炎
うっ血性心不全・心臓性喘息