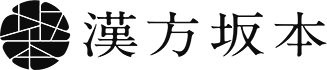自律神経失調症について
自律神経失調症とは
自律神経失調症とは正式な「病名」ではなく、自律神経が乱れることで不快な症状を起こしている「状態」を指します。自律神経とは自分の意志では動かせない部分を、自動的に、自律して動かしてくれている神経です。からだ全体の活動を統括している神経ですので、病であれば何らかの自律神経の乱れが必ず関与しているといっても過言ではありません。したがって自律神経失調症という診断は結局何をいっているかわからないことになりますが、しかしそれでも実際にはよく診断名として使われています。自律神経は乱れているが、その原因がわからないということが多いからです。
●未だ不明な部分が多い巨大なネットワーク
自律神経は非常に複雑なネットワークの中でその働きが調節されています。あまりに複雑なため、自律神経がどうして乱れているのかが分からない場合では、それをどのように調節したらいいのか、という具体的なことが未だにはっきり分かっていません。原因としてストレスということが良く言われます。日常のストレスにより自律神経が乱れることは確かです。しかしストレスが原因だと言われても、ストレスのまったく無い生活を送ることは現実的に不可能です。したがって自律神経失調症は根本的な治療が難しく、なかなか治りにくいという印象があります。
自律神経失調症と漢方:なぜ漢方薬で自律神経を調えることができるのか
しかし東洋医学的にみると、自律神経症状が継続してしまうことには原因があります。それはストレスといった外的な要因ではなく、自律神経症状を起こしてしまう方の体に問題があることが多いのです。漢方ではその原因を突くことで自律神経の乱れを解除します。すると不快な症状が改善されてくるだけでなく、ストレスで乱れやすかった自律神経が乱れにくくなるという状態にまで変化していく傾向があります。
●「全体を見る」とは?
このような手法は、人体の細かな働きを知ることができなかった時代だからこそ培われた手法だと言えます。細部ではなく、あくまでからだ全体を見たからこそ、自律神経の乱れを正すコツを見つけることができたのです。
例えば、咳が続いている人に咳止めを出した。そしたら咳が止まると同時に興奮がスッと治まり、頭痛や耳鳴り・めまいや肩こりも一緒に治った。また下痢が続いている人に下痢止めを出した。そしたら下痢が治ると同時にホッと安心し、緊張が取れてぐっすり眠れるようになった。このような経験から、肺の働きを正すと興奮が落ち着くことや、胃腸の機能を正すと緊張が取れるというコツを知ってきたわけです。現代では細部の状態が以前にくらべてわかるようになりました。だからこそ、めまいを肺の薬で治そうとか、不眠を胃腸の薬で治そうという発想は絶対に出てきません。全体を見ることで初めて知ることの出来た手法が、漢方にはあるということです。
●関連と繋がりを重視する医学
そもそも自律神経は自分で動かせない部分すべてを統括している神経です。すなわちからだ全体をつないでいる神経だというこです。ということは、身体各部のそれぞれの働きが関連しているというのは、ごく当然のことだとも言えます。漢方治療を行うと、まさか胃薬で不眠が治るとは思わなかったとか、便通を良くする薬を飲んだらイライラが治まったとか、想像もしていなかった体の関連にしばしば驚かれる方が多くいらっしゃいます。繋がりの中で症状を理解するからこそ、自律神経の安定を図ることが可能なのです。
参考症例
まずは「自律神経失調」に対する漢方治療の実例をご紹介いたします。以下の症例は当薬局にて実際に経験させて頂いたものです。本項の解説と合わせてお読み頂くと、漢方治療がさらにイメージしやすくなると思います。
症例|不安感を中心にたくさんの症状に悩まれている50歳女性
不安感がずっと継続し、その他さまざまな症状でお悩みの患者さま。生活を諦めたくなるような辛さから、漢方治療をお求めになられました。たくさんの症状の中からどのように処方を選択していくのか。決め手となる本質と、治療の道のり。自律神経の失調がどのように改善されていくのか、その具体例をご紹介いたします。
症例|不安感を伴う高血圧と動悸・心の病と診断された62歳男性
血圧が高くなると同時に、のぼせ・火照り・動悸・耳鳴り・不眠など、様々な症状に苦しまれていた患者さま。内科にて血圧の薬を処方されるも改善されず、心療内科を紹介され抗不安薬や抗うつ薬にて治療されるも改善されていません。心の病と体の病、両者を備える病態に対して漢方治療にてどのようにアプローチしていくのか。自律神経失調症治療の具体例をご紹介いたします。
症例|15歳の女の子・過呼吸から派生した突然のアクシデント
中学生から高校生への過渡期、過呼吸と立ちくらみに悩まれていました。漢方治療を行うことで症状が改善していく中、想像もしていなかったアクシデントが起こります。臨機応変の対応が求められる漢方治療、その具体例を思い出深い症例よりご紹介いたします。
症例|突然の呼吸苦・強い不安を伴う過換気症候群
39歳男性、一カ月前からの胸苦しさが徐々に悪化し、突然呼吸が出来なくなり救急搬送されました。病院の検査では問題なし。過換気症候群の診断を受けてからも、いつくるか分からない発作に不安を募らせていました。このような病態に対して漢方ではどのように対応してくのか。そして西洋医学と東洋医学との違いは何か。具体的な症例を示しながら解説していきます。
症例|突然起こる動悸・運転中の恐怖心にお悩みの36歳男性
運転中、何もないのに突然恐怖心が起こり、心臓が飛び出るのではないかと思うほどの動悸に苦しまれていた患者さま。内向きな性格のためか気疲れしやすい性格で、日常的にも緊張状態が続いていました。性格と身体、漢方治療において本当に治さなければいけないもの。強い動悸を伴うパニック障害・不安障害に対する漢方治療の具体例をご紹介いたします。
症例|こじれた酒さ様皮膚炎へのアプローチ
顔面部の炎症を治すためにあらゆる治療を行ってきた患者さま。なかなか改善してくれない面部の症状。不安にさいなまれてのご来局でした。当薬局で取った手法は「体を温め、緊張を去る」こと。皮膚の炎症を去るために、体の中から治療する、その実例をご紹介いたします。
症例|生活の中で埋もれやすい月経前の不調
お忙しい生活を送られ、当たり前のこととして受け止めてきた月経前のイライラ・不眠・食欲増進。身体のある部分の強い緊張状態がその原因でした。PMSを改善していくために、そして美を維持していくために、漢方治療でどのようにアプローチしていくのか。その具体例をご紹介いたします。
症例|過労により眠れなくなった70歳女性
ブドウ農家にて現役で働く患者さま。空を見上げ腕をあげ続けるキツイ仕事の中、体重が減少するとともに、不安感が強まり眠ることが出来なくなってしまいました。オーバーワークによる不眠、疲労と自律神経との関係。眠る力を呼び戻すための手法を、具体的な治療を通してご紹介いたします。
参考コラム
次に「自律神経失調」に対する漢方治療を解説するにあたって、参考にしていただきたいコラムをご紹介いたします。参考症例同様に、本項の解説と合わせてお読み頂くと、漢方治療がさらにイメージしやすくなると思います。
コラム|「漢方と自律神経」
自律神経とは何か?そして自律神経を東洋医学ではどう捉えるのか?。これらの疑問をなるべく分かりやすく解説いたします。「気」などの言葉をなるべく使わず、イメージとして捉えやすくして頂くというのがこのコラムの目的です。
コラム|「漢方と精神症状」
不安・焦り・恐怖・怒り。これらの精神症状は、確かに的確な漢方治療によって改善することの多い症状です。ただし「怒り」=「肝の失調」といったように、短絡的な五行理論では正しい処方を導くことができません。心の症状をどのように把握するべきなのか。現実的な漢方治療を解説していきます。
コラム|自律神経失調症・パニック障害 ~漢方薬による治り方とその具体像~
現在、さまざまな症状を併発する自律神経失調症では、漢方治療に多くの期待が寄せられています。しかし服用したけれでも効かなかったという方も多くいらっしゃいます。それは、この病特有の治し方・治り方の特徴を理解せずに治療していることが多いためです。漢方にて自律神経がどのように改善に向かうのか。治療のポイントとその治り方の具体像とをご説明いたします。
→□自律神経失調症・パニック障害 ~漢方薬による治り方とその具体像~
コラム|自律神経失調症の特徴とその厄介さ
身体面だけでなく精神面にも症状を発現させる自律神経失調症。心身伴に影響を及ぼすのがこの病の特徴であり、この病の厄介さでもあります。「自律神経失調症が治る」とはどういう状態を指すのか。私が経験として感じることをご説明いたします。
コラム|漢方治療の経験談「自律神経失調症治療」を通して
当薬局でもご相談の多い起立性調節障害。日々治療を経験させていただいている中で、実感として思うこと、感じたことを徒然とつぶやいたコラムです。
→漢方治療の経験談「自律神経失調症治療」を通して
→漢方治療の経験談「自律神経失調症治療」を通して 2
コラム|漢方治療の実際 ~自分に合った漢方薬を探されている方へ~
自分に合った漢方薬を見つけたい・・。漢方薬が広く認知されてきた昨今、病や症状を治すために自分に合った漢方薬を探されている方は多いと思います。お体にあった漢方薬を選択することは、病を改善していくための必須条件ではあります。しかし必須条件はそれだけではありません。改善というゴールにたどり着くためには、様々な条件をクリアしていかなければならないのです。病を改善していくためには何が必要なのか。漢方治療の具体像を詳しくお伝え致します。
→〇漢方治療の実際 ~自分に合った漢方薬を探されている方へ~
コラム|漢方治療の実際 ~本当に効くのか?実際に治している先生方の共通点~
漢方薬は本当に効くのでしょうか?そもそも気を調えるとか、血を調えるとか、漠然とし過ぎていてよくわかりません。漢方治療に何となく一歩踏み出せないという方の理由、その多くが煎じ詰めるとこの疑問に行きつくのではないでしょうか。今回のコラムではこのような疑問に対して、私自身が思う、率直な回答をお示ししたいと思います。そして様々な先生方にお会いする中で気づいたこと。実際に病を治されている先生方に共通したある考え方をご紹介したいと思います。
→〇漢方治療の実際 ~本当に効くのか?実際に治している先生方の共通点~
コラム|漢方治療の実際 〜気や血・漢方特有の言葉に隠された落とし穴〜
東洋医学ではそれを説明する際に独特な用語が使われます。「気」や「血」、「陰・陽」といった用語は、漢方薬をお調べになる際に必ず目にする言葉ではないでしょうか。パニック障害の漢方治療においても、いたる所で頻繁に用いられてはいますが、実はこれらの言葉には大きな「落とし穴」があります。現実的に症状を改善していくために必要な知識とは何なのか。漢方治療を詳しくお調べになっている方にこそ、見て頂きたい内容です。
→○漢方治療の実際 〜気や血・漢方特有の言葉に隠された落とし穴〜
コラム|【漢方処方解説】半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
心療内科・精神科領域において最も有名と言っても過言ではない半夏厚朴湯。「咽が詰まって息苦しい」など、咽に生じる違和感に対してファーストチョイスで使用されています。ただしこの薬はその適切な使い方を掴むことが非常に難しい処方で、ただ一律的に使用されているだけでは、ほとんどの場合効果がありません。このような難しい処方がなぜ頻用されているのでしょうか。半夏厚朴湯の特徴とともに解説してみたいと思います。
→【漢方処方解説】半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)・前編
→【漢方処方解説】半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)・後編
コラム|【漢方処方解説】桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)
心療内科や精神科領域の病に対して使用される機会の多い処方・桂枝加竜骨牡蛎湯。特にパニック障害や自律神経失調症など、不安感や焦燥感(あせり)を伴う病で頻用されています。ただしこの処方は一般的な解説をもって理解することが非常に難しい処方です。そこで本方の薬能を分かりやすく知って頂くために、あえて今までにない処方解説を講じてみたいと思います。「実感」から「理解」へ。本方の現実的な薬能をご紹介いたします。
→【漢方処方解説】桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)・前編
→【漢方処方解説】桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)・後編
コラム|【漢方処方解説】柴胡加竜骨牡蛎湯加減(さいこかりゅうこつぼれいとう)
柴胡加竜骨牡蛎湯はパニック障害や自律神経失調症など、動悸や不安感を伴う疾患に頻用されている処方の一つです。さまざまな所で解説されている有名処方ではありますが、正直に申し上げると、飲んでみたけどあまり効果を感じられなかったとおっしゃる患者さまが多い処方でもあります。とういうのも、本方はその運用方法がいまいち分かりにくいのです。実際はある状態に驚くほどの効果を発揮する処方ですので、その運用の妙を解説していきたいと思います。
→【漢方処方解説】柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
コラム|【漢方処方解説】帰脾湯・加味帰脾湯(きひとう・かみきひとう)
心療内科系の漢方薬として有名な帰脾湯・加味帰脾湯。薬局では「心脾顆粒」という名称でもしばしば販売されています。「体の弱い人の精神症状」に対して、第一選択的に使われている傾向があるものの、本当にこれだけの情報で使ってしまって良いのでしょうか。飲んだけれども効かなかったという方のために、本方の適応病態を詳しく解説していきます。
→【漢方処方解説】帰脾湯・加味帰脾湯(きひとう・かみきひとう)
コラム|【漢方処方解説】柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)
漢方では、一つの処方が多くの領域にまたがって、一見全く関係ないように思われる疾患に運用されることが良くあります。今回解説する柴胡桂枝湯もその一つです。この処方はシンプルな構成でありながら、広くさまざまな病に応用することができます。今回の解説では、この処方についてやや深く掘り下げて解説していくとともに、この不思議さの秘密を紐解いていきたいと思います。
コラム|【漢方処方解説】半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)
胃腸薬として有名は半夏瀉心湯。ただしこの処方は処方構成がやや複雑なために、その効果を理解しにくい傾向があります。体を冷ます寒薬と、温める温薬とが同時に入っている。しばしば寒熱錯雑と解説されていますが、使い所としては要領を得ません。そこで今回は敢えて簡単に解釈することで、この薬の効能を分かりやすく示していきたいと思います。
使用されやすい漢方処方
①半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)
②香蘇散(こうそさん)
③分心気飲(ぶんしんきいん)
④苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
⑤四逆散(しぎゃくさん)
⑥大柴胡湯(だいさいことう)
⑦柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)
⑧逍遥散(しょうようさん)
⑨抑肝散(よくかんさん)
⑩柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)
⑪桂枝湯加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)
⑫桂枝湯(けいしとう)
⑬甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)
⑭甘草瀉心湯(かんぞうしゃしんとう)
⑮温胆湯(うんたんとう)
⑯帰脾湯(きひとう)
⑰六君子湯(りっくんしとう)
⑱桃核承気湯(とうかくじょうきとう)
※薬局製剤以外の処方も含む
①半夏厚朴湯(金匱要略)
心療内科領域・精神科領域に用いられる方剤として有名。最も有名な適応は「梅核気(ばいかくき)」と呼ばれる咽に何か詰まったようで苦しいという症状である。おそらく昭和に大塚敬節先生が頻用していたことをきっかけに、広く用いられるようになったのではないかと思う。自律神経失調症や不安障害・パニック障害において、咽もとの苦しさを伴う者に頻用される。しかし私見では的確に運用することは実は難しい処方である。少なくとも、精神疾患に対して単独かつ一律的に運用しても効果が上がることは少ない。
本方は梅核気を絶対目標とする処方ではなく、身体に備わるある種の緊張感を去る薬方である。特に胸部(胃から肺)の緊張による動悸・息苦しさ・胸がつまって苦しくなるなどの症状に対して効果を発揮しやすい。またそこから派生して、めまいや眼瞼の震え・時に顔面神経痛など、首から上の症状に効果を及ぼすことがある。本方は不安感や焦り、過剰な几帳面さやイライラ、時に抑うつ状態などの精神症状に対しても用いられるが、こういった精神症状の中にも緊張感を含んでいることが目標になる。重く抑うつされた緊張感というか、底の方で反発しようとしている緊張感というか、そのような印象の精神症状を厚朴で緩め、紫蘇葉で発散させる方剤である。本方を単独で用いて著効させるやり方よりも、他剤に合方して用いることが多い。
本方の基本骨格は小半夏加茯苓湯という「痰飲(水分代謝異常)」を治す方剤である。体内の水分は発散されたり保持されたりを繰り返しているが、ある種の緊張感は発散を抑制し、保持を強めて身体内に水を貯める。つまり精神の乱れを持つ方の中には、身体に水を蓄積または偏在させている場合がある。漢方では水の蓄積や偏在を「水毒」とか「痰飲」という。古人は掴みどころのない精神疾患では水毒を考えろという口訣を残している。
半夏厚朴湯:「構成」
半夏(はんげ):生姜(しょうきょう):茯苓(ぶくりょう):厚朴(こうぼく):紫蘇葉(しそよう)
②香蘇散(太平恵民和剤局方)
半夏厚朴湯と並び、自律神経の乱れに頻用される方剤。その薬能は良い意味で「軽い」。気分が晴れない・鬱々としてやる気が起きないというような抑うつ状態を、軽く心地よい香りで発散させるという方剤である。胃から胸に詰まった気を通す薬能を持ち、六君子湯などの胃薬と合わせて用いられることも多い。香りが命の方剤であるため、煎じ薬では長く煎じると薬能を失う。香りを消さない程度に煎じ、香気を服用するというのが本方の主眼である。軽い薬能を持つ方剤ではあるが、効果が弱く効きが悪いということではない。気持ちが沈むと胸が詰まったり、胃もたれしやすくなったり、食欲がなくなったりするといった者では、本方で軽く胃気を疎通すると素早く気持ちが晴れるということも多い。特にもともと胃腸の弱い方や高齢者など、身体的にも精神的にもどこか弱さを持つ方に効果的な薬である。
底に鬱する緊張感が強いために、それが外にも波及して表れてくるのが半夏厚朴湯だとしたら、本方は底に緊張感が鬱するも、外にでるほどの強さがないというのが目標になる。本方の運用に非常に長けておられる花輪壽彦先生は『漢方診療のレッスン』においてその適応を以下のような口訣としてまとめておられる。「(香蘇散適応者は)心理的葛藤が内向し鬱々悶々としている。身体表現がへたで精神的な息詰まりを上手に開放できない傾向がある。(中略) 香蘇散証にはすべてどこか悲哀感か萎えた感じがある。」また同時に半夏厚朴湯との鑑別を示されている。「(半夏厚朴湯適応者は)心理的葛藤を身体表現にして開放する。精神的に息詰まると、「弱い」ところ・「敏感」なところに不快な症状として具体的に現れる。(中略)厚朴を必要とする人はどこか「硬さ」がある。筋肉の緊張とか顔の表現という意味でも、精神的な意味でも。」
香蘇散:「構成」
香附子(こうぶし):紫蘇葉(しそよう):生姜(しょうきょう):陳皮(ちんぴ):甘草(かんぞう):
③分心気飲(太平恵民和剤局方)
半夏厚朴湯や香蘇散は気剤と呼ばれている。胃部から胸部にかけて鬱した気を疎通するという方剤である。そして本方は気剤の総司としてこれらの処方の良いとこ取りをしたような方剤。心胸間に詰まった気を分け散らすという意味を以て分心気飲という。
胃や肺は自律神経の乱れによる過剰な興奮や緊張をしずめるための要所である。気持ちが沈んだ時や恐ろしい思いをした時に、人は胸に手を当てる。また食べ過ぎた時など胃がつまった直後に、自律神経が乱れて動悸や息苦しさが強まるということは臨床的に良くあることである。本方や半夏厚朴湯・香蘇散という処方は簡単に言えば胃薬であり、消化管の機能を改善することで胸部に起こる自律神経の乱れを取り去る方剤である。
本方は多種類の生薬を少量ずつ配合しているという点が一つの特徴になっている。一般的には少数の生薬によって構成されている方剤は切れ味が良く(効き目が早い)、多種類の生薬で構成されているほど的(まと)が広い(多くの症状に広く適応する)と言われている。少数生薬で構成されている半夏厚朴湯や香蘇散と比べると、本方は確かに様々な症状を包括して治療する時に用いられる傾向がある。ただしこの辺りの運用は各先生方の経験による所が大きい。各先生によって運用にクセのようなものがあり、特に精神症状の改善を目的とする場合ではそのクセが出やすいと感じている。
分心気飲:「構成」
桂枝(けいし):芍薬(しゃくやく):甘草(かんぞう):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):桑白皮(そうはくひ):大腹皮(だいふくひ):青皮(せいひ):陳皮(ちんぴ):羌活(きょうかつ):半夏(はんげ):茯苓(ぶくりょう):木通(もくつう):燈心草(とうしんそう):紫蘇葉(しそよう):
④苓桂朮甘湯(傷寒論)
立ちくらみやめまいの治療薬として有名であるが、気持ちが落ち込みやすいとか、やる気が起きず出かけたくないといった抑うつ状態に対して用いられる機会が多い。山本巌先生の言葉を借りれば「フクロ―型」の体質をもつ者。朝が弱く起きるのが困難で、午前中の体調は悪いが、夜間になるとエンジンがかかりはじめ、午前中の体調不良が嘘のように無くなる者。夜間元気になる分、なかなか寝付けず、そのためさらに朝が弱く布団の中にだらだらといたがる者。学生時代朝礼で脳貧血を起こし倒れるような者。立ちくらみやめまいを起こしやすく色白で浮腫みの傾向がある者。こういった体質を持つ方の自律神経失調症に効果を発揮する。
茯苓・桂枝・甘草を内包している処方群(苓桂剤)は自律神経を安定させる薬能を持つ。苓桂朮甘湯や茯苓甘草湯・茯苓沢瀉湯などは緊張して動悸し息苦しく、血の気が引くような感覚があるといった症状を目標に用いられることが多い。したがって自律神経失調症のみならず不安障害・パニック障害・心臓神経症などに応用される。苓桂剤は一味一味の生薬の意味が非常に重要であり、そこを的確に当てはめることが出来るかどうかで即効性が変わってくる。
苓桂朮甘湯:「構成」
桂枝(けいし):甘草(かんぞう):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):
⑤四逆散(傷寒論)
心療内科・精神科領域の漢方治療において、四逆散を基礎とする一連の処方群は無くてはならない存在である。本方は「肝気鬱結(かんきうっけつ:肝鬱とも言う)」と呼ばれる自律神経の過緊張状態を緩和させる薬能を持つ。特に胃や腸などの消化管における過緊張を和らげる場合に用いられることが多い。
東洋医学では肝は怒りと関連が深いと言われている。「肝鬱」の特徴はイライラを主体とした怒気である。思いがけず強い口調を発してしまったり、些細なことで怒りやすかったり、必要以上に人に当たりたくなるといった精神状態を発生させやすい。緊張状態は我慢の状態から派生する。やりたいことができない、言いたいことが言えないといった我慢の状態は、思っていることを外に発散させないように、体に力を入れて緊張している状態である。四逆散類が適応となる「肝鬱」では、この我慢・緊張の状態から内圧が高まり、我慢できなくなった怒気が興奮と伴に突発的に発散されるという印象がある。故にイライラを発生していない時でも、眉間にしわが寄っていたり、腕を組み黙々と考えているような、硬い印象を身にまとっていることが多い。
人の我慢と緊張とは胃に出る。胃壁が荒れるとか胃炎が起きるとかいうことではなく、胃の活動が悪くなり、みぞおちに自覚的な詰まりを感じる。その詰まりは人によって胃もたれであったり、痛みであったりと様々である。古人はこのみぞおち(心下)の詰まりの度合いを見ることで、身体の緊張を測った。そしてその程度に合わせて四逆散の類方を選択したのである。
四逆散:「構成」
柴胡(さいこ):芍薬(しゃくやく):甘草(かんぞう):枳実(きじつ):
⑥大柴胡湯(傷寒論)
四逆散の類方。体格が充実していて、便秘傾向のある者(実証)に適応すると解説されていることが多い。しかし本方適応の「実」とは、体格の充実度ではない。胃部(心下)の詰まりの度合いが実しているのである。
「心下急、鬱々微煩」というのが本方最大の目標。みぞおちが硬く詰まり、顎を引いて下を向き、鬱々とした緊張感を発している状態である。胃部に強い緊張感を持つこのタイプは、それだけ緊張できる、つまりそれだけ我慢できるということである。したがって内に高まる内圧が強く、発された時の怒気も硬く強い。消化管に強く結実を起こす傾向があるため、便秘しやすく、時に胆石などを生じることもある。確かに太りやすいタイプに多いが、細い方であっても本方の適応者が少なくない。
大塚敬節先生が最も頻用した処方は大柴胡湯であったと聞く。強い薬、便秘の方の下剤というイメージが先行しているが、必ずしもそうではない。加減や合方を施すことで、広く運用できる処方だと考えている。
大柴胡湯:「構成」
柴胡(さいこ):半夏(はんげ):黄芩(おうごん):芍薬(しゃくやく):枳実(きじつ):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):大黄(だいおう):
⑦柴胡桂枝湯(傷寒論)
小柴胡湯と桂枝湯との合方。本方も柴胡・芍薬・甘草を基本とした四逆散の類方である。本方適応者に起こる胃部症状を「心下支結」という。心下が急する大柴胡湯の所見に比べて、結実が穏やかであることが特徴である。心下に起こる緊張感が緩い分、内圧が高まらないうちに弱い怒気が漏れやすい。したがって発する怒気にも大柴胡湯のような硬い印象が少なく、腰が据わらない感覚を伴うことが多い。
本方は加減することによって非常に広い精神症状を包括して治療することのできる方剤でもある。桂枝湯の方意・四逆散の方意を含むだけでなく、半夏散及湯や小半夏湯、また茯苓を加えれば苓桂剤の方意を持つことになる。大塚敬節先生の弟子であられた相見三郎先生は、本方の運用に非常に長け、多くの精神障害をほとんど柴胡桂枝湯一本で切り回しておられたとのことである。ただし相見先生の用いる柴胡桂枝湯は、人によって異なる加減が常に細かく施されていた。まさに本方の運用を掌上に把握されていたのであろう。
柴胡桂枝湯:「構成」
柴胡(さいこ):半夏(はんげ):黄芩(おうごん):人参(にんじん):甘草(かんぞう):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):桂枝(けいし):芍薬(しゃくやく):
⑧逍遥散(太平恵民和剤局方)
PMSや更年期障害の代表方剤であると同時に、自律神経の安定を図る際にも頻用される処方。逍遥とは「うつろいゆく」という意味で、その時々で訴える症状が色々と変化する者に適応する、と解説されていることが多い。確かにそのような傾向はあるが、実際の臨床においてはこのような曖昧な目標は決め手にならない。
逍遥散は元来、一種の消耗性の発熱性疾患に用いられていた。身体に緊張・興奮の状態が継続し、それにより血を消耗して自律神経の乱れがいつまでも解除されないような病態である。本方は血の消耗を回復することで興奮を落ち着け、緊張を去るという薬能を持つ。その本質は胃腸薬であり、芍薬・甘草・生姜・茯苓・白朮が核となり、柴胡を加えることで四逆散の類方としての性質が生まれる。興奮してイライラしやすいといった怒気をはらむ精神状態に頻用されるが、本質には胃腸の虚があり、緊張が強く結実するタイプではない。したがって発する怒気は鋭いが軽く、吹けば動く動揺感がある。
逍遥散:「構成」
当帰(とうき):芍薬(しゃくやく):白朮(びゃくじゅつ):茯苓(ぶくりょう):柴胡(さいこ):甘草(かんぞう):生姜(しょうきょう):薄荷(はっか):
⑨抑肝散(保嬰撮要)
本方は自律神経失調や脳神経疾患(脳血管障害後遺症やパーキンソン病、アルツハイマー)などへの適応が有名である。四逆散の類方として怒気を含む精神症状に多用されている。
本方の運用を得意とした先哲に和田東郭がいる。そして和田東郭は本方の適応を「多怒・不眠・性急」と端的に示している。寝つきが悪くイライラしやすい者。我慢ができず少しの刺激ですぐに怒気を発する者。鋭い怒気を発するが、どこか根がなく、むしろ怒気に振り回されてしまっている者に適応する印象がある。緊張は血の流れを結滞する。本方は結ばれた血脈を通じることで、手足・頭部といった末端にまで血行を促す薬能を備えている。逍遥散と似た処方ではあるが、逍遥散が血の消耗に対して用いる方剤である一方で、本方は血脈の結鬱に用いる。したがって逍遥散が顔を赤くして起こるという者に適応するのに対して、本方は青筋を立てて怒るという者によい。内風をしずめる釣藤鈎を含むところも本方の特徴。怒気は風にて巻き上がると頭でこじれる。怒気とともに頭痛や耳鳴り、卒倒するようなめまい感を伴うこともある。黄連を加える時もある。東郭は本方にかならず芍薬を加えて用いていた。
他の四逆散類と同じく、本方も胃部(心下)の緊張状態を緩和させることで怒気を静める方剤である。「心下に気聚りて痞する気味あり」。浅田宗伯の指摘である。
抑肝散:「構成」
当帰(とうき):川芎(せんきゅう):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):甘草(かんぞう):柴胡(さいこ):釣藤鈎(ちょうとうこう):
⑩柴胡加竜骨牡蛎湯(傷寒論)
自律神経の過敏・興奮状態に適応する処方。自律神経失調症のみならず、動悸・呼吸のしづらさ・胸苦しさを主とする心臓神経症や不安障害にも運用する場が多い。自分でもどうしてしまったんだろうと感じるほどに、心身ともに強い過敏状態に陥ってしまったときに用いる方剤である。一つのことが気になりだすと止まらず、焦り、不安になっていてもたってもいられなくなる。少しのことで驚きやすく、動悸して息苦しい。小さな物音が気になって眠れない。横になっても身の置き所がなく、手足がはばったく重い。甚だしいと手足に力が入って上手く動かせず、胸脇部が苦しく体をよじって伸ばしたくなると訴える。動悸や息苦しさ以外にも、頭痛・耳鳴り・めまい・不眠・不安感・焦燥感・イライラなど様々な症状を出現させる病態に適応する。実はそのまま服用してもあまり効果がない。上手く使うには合方も含めてコツがいる処方である。体格充実した者に適応するという解説もあるが、私見では体格は関係ない。とにかく「胸満煩驚(きょうまんはんきょう)」という病態に陥っているかどうかが運用のカギとなる。
柴胡加竜骨牡蛎湯:「構成」
柴胡(さいこ):半夏(はんげ):人参(にんじん):黄芩(おうごん):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):桂皮(けいひ):茯苓(ぶくりょう):竜骨(りゅうこつ):牡蛎(ぼれい):大黄(だいおう):
⑪桂枝加竜骨牡蛎湯(傷寒論)
柴胡加竜骨牡蛎湯と同じように自律神経の過敏・興奮状態に適応する処方。心臓神経症や不安障害にも運用することが多い。動悸や胸苦しさ・耳鳴りやフワフワ浮くようなめまい・不安と焦りが強くじっとしていられない・寝つきが悪くて眠りが浅く、夢を見やすいなど。適応症候だけを並べれば柴胡加竜骨牡蛎湯と類似しているが、両者では運用に明らかな違いがある。
本方適応の主眼は「虚労(きょろう)」である。自律神経の乱れを伴う一種の疲労状態で、本方は虚を補い疲労を回復させながら自律神経の安定を図る。柴胡加竜骨牡蛎湯の主眼は「胸満煩驚」である。あくまで強い自律神経の過敏さに適応する。両者の違いを虚・実と解説するものも多いが、体格の大小や正気の虚実によってのみ判断できるものではない。桂枝加竜骨牡蛎湯の虚は「虚労」の虚であり、柴胡加竜骨牡蛎湯の実は過敏・興奮状態の極まりを指す。
総じて竜骨牡蛎剤の目標は、自律神経の不安定さである。精神症状としては不安や焦り、落ち着きのなさというのが最大の目標になる。その他、ソワソワする、フワフワする、不安で恐ろしい、居ても立っても居られない、一つの場所でじっとしていられないなど。上に浮揺する陽気を、竜骨牡蛎の重みで鎮めるのである。
桂枝加竜骨牡蛎湯:「構成」
桂枝(けいし):芍薬(しゃくやく):甘草(かんぞう):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):竜骨(りゅうこつ):牡蛎(ぼれい):
⑫桂枝湯(傷寒論)
最も基本にしてあらゆる方剤の創始。基本処方としての性質が極めて強いため、実際の臨床においては軽視されている傾向がある。しかし本方は自律神経の乱れを平定させる要薬であり、その加減方は広く自律神経失調症に適応する。桂枝加桂湯、桂枝去桂湯、桂枝加芍薬湯、桂枝加竜骨牡蛎湯などはその代表である。自律神経失調といえば「肝鬱」や「気滞」がすぐに連想され、四逆散の類方や香蘇散・半夏厚朴湯などが用いられやすい。しかし本方を理解し上手に運用すると、どのような薬方でも治らなかった症状が驚くほど素早く改善することがある。簡にして妙、そして東洋医学思想の集約でもある。本方を使用するかしないかは別としても、桂枝湯を深く理解している先生ほど臨床に強い、という傾向があるように思う。
桂枝湯:「構成」
桂枝(けいし):芍薬(しゃくやく):甘草(かんぞう):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):
⑬甘麦大棗湯(金匱要略)
桂枝湯類を自律神経失調に用いる場合、気薬である桂枝や柔肝に働く芍薬の薬能が主として取り上げられやすい。しかし実際には大棗・甘草といった甘味の薬物が持つ向精神作用も大きな役割を担っている。
本方は大棗・甘草・小麦という甘味をもつ薬物のみで構成された処方。出典の『金匱要略』では「臓躁(ぞうそう)」といってヒステリー性神経症のような状態への適応を示唆している。甘味で取れる精神症状というものがある。印象として説明することは難しいが、少なくとも怒気といった攻撃性の強い興奮状態ではない。「悲傷し哭を欲する」という弱さ故に発される訴えを、甘味を以てホッと安心させるというような印象である。ヒステリー性神経症に適応しやすい。その他自律神経失調症や子供の夜泣き・ひきつけに応用される。
※ヒステリー性神経症
ヒステリー性神経症とは本人自身が気づいていない心理的な問題(欲求や願望の抑圧など)のために、身体がその自己防衛の発露として意識や運動・知覚などの障害を引き起こすものをいう。例えば友人や家族の前に出る時に限って歩けなくなったり、視力や聴力が失われてり、声が出なくなったりする。このような症状によって、手厚い看護を受けたり、一身に心配を受けたり、学校や職場に行かなくてもすむようになる。心理的な問題が症状へと転換されることで、気づかないうちに自己防衛を図り心理的な問題を解決しようとしている、というものである。歩けなくなったり、視力や聴力が失われたりといった身体症状として発露されるものを転換型といい、ある期間の記憶を失ったり夢中歩行を起こしたりして人格統合が失われる状態を解離型、また子供返りを起こす退行型などがある。ヒステリーとはもともと古典ギリシャ語で「子宮」を意味する。女性に特有の疾患として考えられていたが、実際には性別関係なく起こるものである。
甘草小麦大棗湯:「構成」
甘草(かんぞう):大棗(たいそう):小麦(しょうばく):
⑭甘草瀉心湯(金匱要略)
「心下痞硬」という胃の詰まりを中心に胃腸症状を改善する本方は、同時に「孤惑(こわく)」という精神症状を改善するための薬方でもある。イライラしつつも不安感を伴い、目を閉じようとしても興奮して眠れない。半夏瀉心湯中の甘草を増量した処方であるが、黄連・黄芩でカバーできない興奮を甘草の甘味を以て落ち着けるという処方である。
本方は胃気を和すことで興奮を落ち着けることを主とし、黄連・黄芩にて「心火」と呼ばれる興奮の火を沈静化させる薬能を持つ。さらに小半夏湯の方意を持ち、「痰飲」を治すことで水分代謝の失調を伴う独特な精神症状にも対応する薬能を持っている。精神症状の改善に積極的に用いられている傾向はそれほどない。しかし柴胡剤や気剤といった常道だけで解決できない自律神経失調は確かにあり、常に頭に入れておかなければならない方剤である。
甘草瀉心湯:「構成」
半夏(はんげ):乾姜(かんきょう):黄芩(おうごん): 竹節人参(にんじん):大棗(たいそう):甘草(かんぞう):黄連(おおれん):
⑮温胆湯(三因極一病証方論)
駆痰剤として「痰熱内擾(たんねつないゆう)」という病態に運用される方剤。「痰熱内擾」とは胃・胆で発生した水分(痰)が上逆して精神を乱す、と中医学では説明されているが非常に分かりにくい。シンプルに言えばある腫の胃薬で、甘草瀉心湯のように胃気を和すことで身体の興奮を鎮める薬方。平素から食欲あり、便秘しやすく不眠に陥り、情緒が不安定になって物音に驚きやすくなるもの。めまいを起こすものもいる。黄連や酸棗仁を加えることが多い。胃気を和す薬方の適応者に総じて言えることだが、精神症状を前面に訴える方では胃と精神状態とが関連しているとは思っていないため、胃の不調を自分からはあまり訴えない。しかしよくよく聞くと、平素から胃もたれを生じやすかったり、明らかな食生活の乱れが介在している場合が多い。
本方はどこまでも体質的な処方で、適応する者には壮年期に動脈硬化による高血圧や脳血管障害などを起こしやすい傾向がある。本来は飲水(飲み水)が身体内に貯留することで起こる飲病(痰飲病)の流れの中で生じる病態。継続する興奮は上部に熱を持たせ、貯留した陰液の消耗を招いて血脈の不利を起こす。竹筎温胆湯や釣藤散の祖方であり、あまり頻用されてはいないが重要な方剤である。
温胆湯:「構成」
半夏(はんげ):茯苓(ぶくりょう):生姜(しょうきょう):陳皮(ちんぴ):枳実(きじつ):甘草(かんぞう):竹筎(ちくじょ):
⑯帰脾湯(薛氏医案)
中医学では本方の適応病態を「心脾両虚(しんぴりょうきょ)」という。心は神(精神)を蔵して血を主り、脾(消化機能)は思を主り血を統摂する。故に思慮過度や疲労によって心と脾とが障害されると、食欲不振や疲労倦怠感などと伴に、不眠や健忘などが起こるという理屈である。疲労感を伴う自律神経失調や神経性食思不振症などに応用されることが多い。
通常、人は労働やストレスによって消耗すると、疲労を感じて眠気が起こり、寝ることで体力を回復させる。しかしある種の消耗は、体力を回復させようとする力自体を疲弊させる。労働やストレスによる興奮が継続して眠気が起こらず、興奮のスイッチが切れなくなる。本方は身体の疲労を回復させようとする力を補うことで興奮のスイッチを解除し、精神の乱れを平定させる薬方である。
近年、本方が内包する「遠志」に注目が集まっている。物忘れなどに効くとされ、遠志を含む製剤が認知症に広く応用されるようになった。今後の臨床成績に期待する所であるが、本方の主とした薬能はその骨格となる四君子湯であり、さらにそこから派生する人参・黄耆・当帰の薬対による所が大きいと思う。遠志ばかりに気を取られて「参耆・帰耆」の意味合いを疎かにしたままでは、いくら遠志剤を用いても効果を期待できないのではないかと思う。
帰脾湯:「構成」
人参(にんじん):黄耆(おうぎ):当帰(とうき):甘草(かんぞう):茯苓(ぶくりょう):白朮(びゃくじゅつ):大棗(たいそう):生姜(しょうきょう):木香(もっこう):酸棗仁(さんそうにん):竜眼肉(りゅうがんにく):遠志(おんじ):
⑰六君子湯(医学正伝)
脾胃気虚(消化機能の弱り)に対する代表方剤である本方は、向精神作用を持つ薬方でもある。食欲が無いか、あっても少食ですぐにお腹いっぱいになるという者、また胃もたれしやすく常に胃の存在感があるという者に本方を用いると、抑うつ的だった精神状態がさっぱりとして、すぐれなかった気分が前向きになってくるということがある。胃気を和したことで自律神経が整い、からだが楽になったことでこころが安定したのである。
帰脾湯や六君子湯のように、正気をおぎなう補剤は自律神経を安定させる薬能を持つ。「虚」の回復が精神状態を安定させるということは良くあることで、虚弱体質者や高齢者では知っておくべき手法の一つである。
六君子湯:「構成」
半夏(はんげ):茯苓(ぶくりょう):生姜(しょうきょう):陳皮(ちんぴ):甘草(かんぞう):白朮(びゃくじゅつ):人参(にんじん):大棗(たいそう):
⑱桃核承気湯(傷寒論)
代表的な駆瘀血剤の一つ。「下法(げほう:大便の通じを促すことで鬱血を去る手法)」によって瘀血を駆逐する点が特徴。下法は血行循環を促すと同時に、身体の興奮状態を沈静化させる薬能も持つ。故に狂(きょう)の如くと言われる精神症状や、不眠などにも応用される。のぼせて顔が赤く、焦りや苛立ちが常にあり、便秘して踏ん張るも乾燥した便が少ししか出ず、いきむと卒倒して倒れてしまうんじゃないかと不安になり、精神的に狂いそうになるという者。即効性をもって便が開通し、排便されると同時に気持ちがスッと楽になるという者が多い。出産後や閉経後の女性に多く、一旦このような症状が出たら、しばらく服用を続けた方が良い。
精神症状を改善するにあたって、「瘀血」は非常に重要な病態である。未だ不明な部分の多い病態ではあるが、血行循環と精神とは切っても切り離せない関わりがあるものだと考えられる。本方の他にも通導散や芎帰調血飲第一加減などを運用する機会が多い。
桃核承気湯:「構成」
桂枝(けいし):甘草(かんぞう):桃仁(とうにん):大黄(だいおう):芒硝(ぼうしょう):
臨床の実際
「こころ」の病と「からだ」の病
自律神経失調症は、不安感や焦燥感、イライラや落ち込みなど、様々な精神症状を伴います。しかし自律神経とは末梢神経、つまり脳ではなく体の動きを調節する神経に属します。つまり「こころ」というよりは「からだ」の問題であることが多いのです。心療内科や精神科領域の病は主に「こころ」の病に属します。ただしこの領域の病がすべてこころだけの病かというとそうではなく、「こころ」の失調が主になるものと、「からだ」の失調が主になるものとに分かれます。その中で、自律神経失調は動悸や息切れ、耳鳴りやめまいなど、「からだ」に何らかの不快な症状が生じている状態を主とした病に属しています。
●自律神経失調症は主として「からだ」の病である
そもそも自律神経失調症は、「身体的な病気が検査では見つからないのに、自律神経の乱れによって症状が生じている」という状態を指しますが、さらに「明らかな精神障害が認められないこと」という条件を加えて定義されています。すなわち双極性障害(躁うつ病)や統合失調症など、こころの症状が主となっている病とは区別されています。そして漢方薬は、自律神経失調症のように、からだの失調を主としている病と相性が良いと思います。
漢方は「からだ」の改善から「こころ」の安定を導く
漢方では「脳」という部位の考察が非常に希薄です。その変わりに、脳が認識している人の感情というものを、人体(五臓)がつかさどっていると考えてきました。肝が「怒り」を、心が「喜び」をといって、感情を各五臓に配当し、怒りが収まらないのは肝が失調しているからだというように人体を把握しようとしたわけです。正直に言えば、これらの配当が臨床的にすべての場合において有効かというと、必ずしもそうとは言えません。また「脳」という神経の中枢を定義していないことは、現代医学、特に精神科から言わせれば落ち度としか言えないと思います。
しかしこの漢方の独特な性質が本当に示すところは、漢方が「からだ」から「こころ」へとアプローチしていく医学だということです。痛みや息苦しいなどの「からだ」の症状があれば、誰でも不安になったり、焦ったり、イライラしたりします。漢方薬で「からだ」の症状を取ってあげると、自分の体を縛り付けていた見えない縄が外れて、心がスッと楽になるということは、臨床的に実際にあることです。
●心身一如:「からだ」が誘発する「こころ」の乱れ
東洋医学が本質的に伝えてきたことは、肝が怒りをつかさどるとか、心が喜びをつかさどるとか、そういうこと以前に、「からだ」と「こころ」を二つに分けないという認識です。人間は自分で考えている以上に「からだ」が「こころ」の乱れを誘発させるという考え方です。そのため漢方では「からだ」の不調を去るための薬方が多く作られてきました。そして「からだ」を改善させることで「こころ」の安定を図り、精神症状を緩和させていくという手法を用います。したがって自律神経失調症や心身症のように、「からだ」の不調に重きを持つ病に対して相性が良いのです。
●「こころ」の病に対して
一方で、こころの疾患の中には、「からだ」よりも「こころ」の乱れに重きを持つものがあります。統合失調症や双極性障害(躁うつ病)・中等症から重症のうつ病などは、こころの乱れが主体になりやすい病です。これらの病でも自律神経の乱れは起こります。そのため「からだ」の不調が起こる場合には漢方治療も有意義です。しかしこれらの病は、体(末梢神経)というよりは脳(中枢神経)の乱れを介在させます。したがって必ず西洋医学的な治療をベースとした上で、漢方はその補助としての役割を担うことが望ましいと思います。
どちらにしても、こころの病というものは未だに分かっていないことが多い疾患です。それは、西洋医学・東洋医学のどちらにとってもそうで、こころの失調はそれほど解明が難しいものです。最も重要なことは、西洋医学においても東洋医学においても、その道の専門家に診てもらうことです。難しい病であるものほど、自己判断は禁物です。ご自分が納得して治療をしていくためにも、習熟された専門の医療機関にお罹りになることをお勧め致します。
※漢方治療のお求めが多いパニック障害・不安障害については、別項で解説しておりますので、ご参照ください。