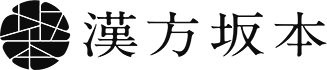色。
世の中には色が溢れています。
郵便ポストの色は赤く、空の色は青く、
年齢を重ねると髪は白くなり、
草木は緑に彩られています。
我々が目にする色。
多種多様な、そこにある色。
当然のように目にしている色ですが、
しかしそれは、ただ私たちがそう感じているに過ぎません。
・
色は、そもそも絶対的なものではありません。
空が青いのは、我々がそう感じているからです。
郵便ポストが赤いのは、「郵便ポスト自体が赤い」わけではありません。
色は、それ自体の固有ものではなく、
あくまで我々が感じているだけのもの。相対的なもの、なのです。
光と、物と、目の、三つの要素。
光の色と物の色、そして、それを目と脳とで私たちがどう感じるかによって、色は初めて定義されます。
イチゴは赤く、生クリームは白く、キャビアは黒くて、きゅうりは緑。
しかし、そうではないのです。イチゴを甘いと感じるのと一緒。色は、本来感覚的なものです。
だからこそ、色は生きている。
状況によって、常に変化を繰り返す生きものと同じです。
でも私たちは、色を固有のものと認識しています。
イチゴが赤いと言っても、誰も不思議に思いません。
それは、曖昧だと認識しにくいほど、訴えてくるものに説得力があるから。
視覚を通じて入り込んでくる情報は、曖昧さを消し去るほどに、私たちの思考を固定させやすいものです。
・
漢方家は人を観ます。
人を観て、症状を把握します。
そして、その症状を消し去る方剤を出すことで、病を改善へと導いていくわけですが、
その時、私たちが把握する症状は、そもそも非常に曖昧なものです。
色と同じです。本来、相対的なもの。
患者さまが訴える症状は、患者さまの人柄やその時々の状況、さらに我々受け手の状況によって、常に不安定に揺れ動いているものです。
しかし我々は、動悸と聞けば、動悸という固定観念を思い浮かべます。
胸がドキドキすること。脈が飛んで息苦しくなること。
動悸と呼ばれるものの典型例。それを必ず、思い浮かべます。
患っている方だからこそ感じる、具体的な症状。
不快感を伴う方だからこそ、訴える症状には説得力があります。
だからこそ、それを聞けば「理解できた」と感じやすいものです。
しかしその症状は、必ずしも受け手が感じるものと、同じではありません。
人を観るということ。
人の症状を把握するということ。
それは、それだけで一つの能力であり、技能です。
経験を通して初めて可能となる、人を知るための能力。
ただし、そうとは分かっていても、我々は自分の認識だけで、症状を理解してしまうことがあります。
つまり、私たちに必要なのものは、
曖昧なものを、曖昧なままに、感じ取ることが出来る「感性」なのです。
・
たとえば、動悸の治療を必死に勉強したとします。
動悸の病理を東洋医学的に把握し、その治療方法を頭の中で用意していたとします。
それでも、動悸を治せるようにはなりません。
そういうことが、東洋医学では当たり前に起こるのです。
その理由は、動悸という症状を、生きた形で把握していないからです。
人が織りなす色の一つ。臨床においては全ての症状が、相対的かつ曖昧であるということ。
それが当然であるという場において、動悸は固有の形をとりません。
たとえ動悸と表現されたとしても、一人として同じものはないのです。
ポストの赤さが、日の光に照らされて変化するように、
患う人の解釈に触れて、動悸という症状にもさまざまな意味が介在します。
師匠は言います。感性が重要だと。
ワーグナー(※)もこう言います。
感性を通じてのみ、余すところなく受け入れられ、
理解される、と。
曖昧さの中に宿る、なるほど、と思える実感。
頭ではなく体で理解する感性こそが、漢方の世界では必要なのです。
・
・
・
※ヴィルヘルム・リヒャルト・ワーグナー
19世紀のドイツの作曲家、指揮者、思想家。ロマン派歌劇の頂点であり、また「楽劇王」の別名で知られている。
・
・
・