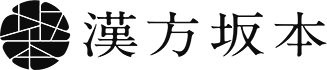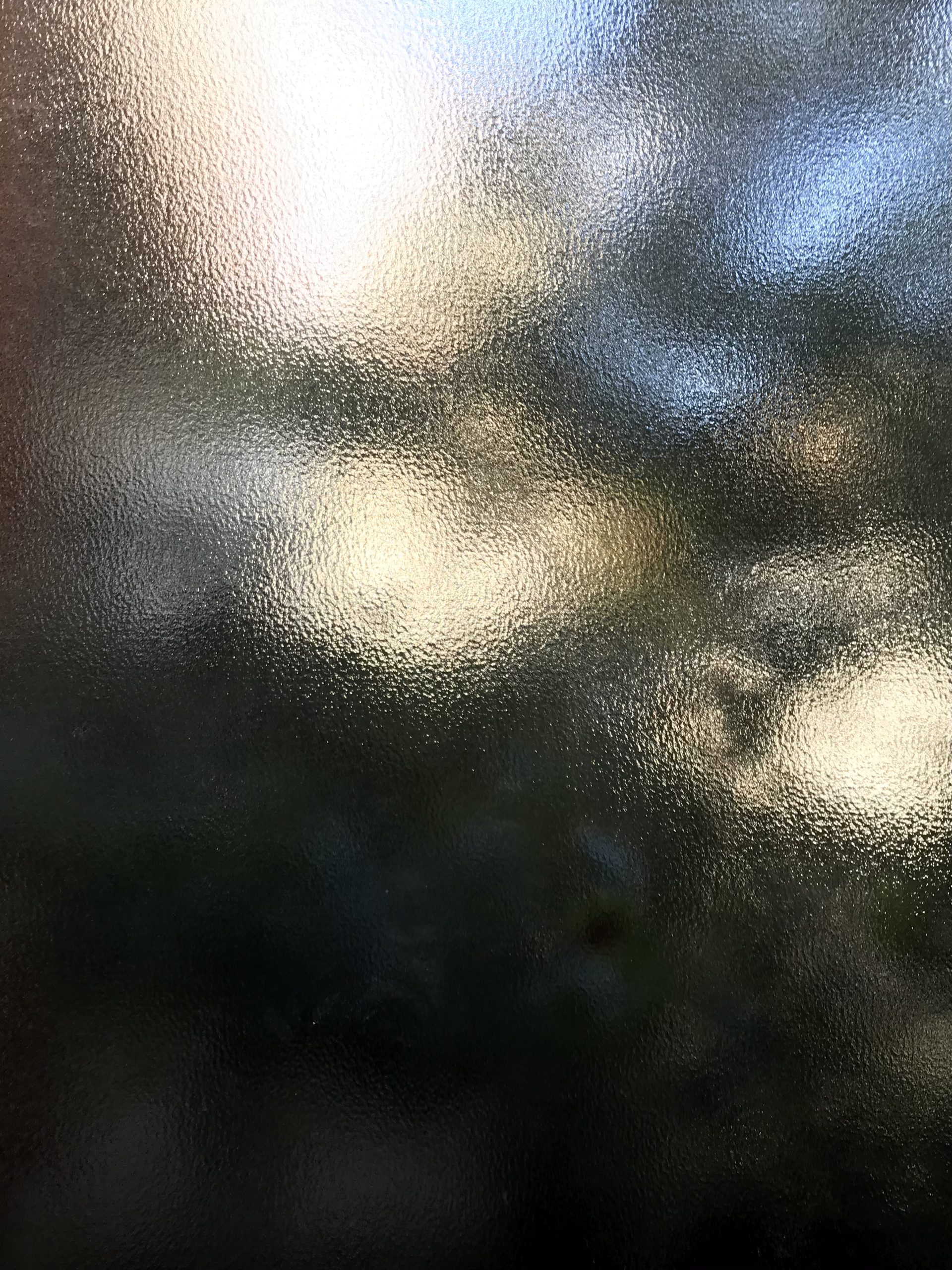・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
真に独創的な画家にとって、
バラを描くことより難しいことはないものだ。
なぜならそのためには、
まずこれまでに描いたすべてのバラを忘れる必要があるからだ。
-アンリ・マティス-
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
広く医療全体の俯瞰して見つめてみると、漢方治療には明らかな弱点があります。
「ガイドライン」が無い、ということです。
「ガイドライン」とは各疾患ごとに定められた治療方針のことです。
西洋医学ではこれがちゃんと定められています。
だから基本的にはどこのお医者さんにかかっても、ガイドラインに則った、ある程度質の高い医療を受けることが出来ます。
しかし、漢方にはこれがない。
だからどうしてもその治療効果が、個人の力量に依存してしまいます。
・
正確に言うと、ガイドラインに近いようなものが有るには有ります。
漢方専門の書籍に載っています。ネットに書いていることもあります。
しかし西洋医学と比べて、その質の低さは否めません。
それに則って治療したところで、満足のいく治療効果があらわれないからです。
これは漢方治療の宿命みたいなものです。
治療手法自体を、「自身の経験」により培わなければなりません。
このような性質は医療全体から見れば明らかに欠点です。
しかし、このような性質があるからこそ、どこにいっても治らなかった病が改善へと向かう、
そういう事実があることもまた、現実なのです。
・
実は漢方治療では「ガイドライン」を作った時点で、治療が上手くいかなくなるものです。
融通無碍(ゆうずうむげ)。
漢方の世界では、治療に長けた先生方の処方運用をしばしばこう表現します。
一つの見方・考え方にとらわれるのではなく、自由自在にものを見、考え方を変え、よりよく対処していくということ。
どんな病であっても個人差があり、その差を見決めるためには疾患というカテゴリーから時に思考を外さなければなりません。
しかし、何でもかんでも自由にやればいい、ということでもないのです。
やはり各々の病には明らかな特徴があります。その軸は、必ず理解し把握していなければなりません。
その先にこそ自由があります。
軸があるからこそ、融けあって通い合い、障碍を受けずに流れることが出来るのです。
執着することなく物事を見つめる目。
経験を拠り所にしつつも、それに依存しない心。
そんな姿勢が必要なのです。だから、漢方治療にガイドラインを作ることが難しいのです。
・
色彩の魔術師、アンリ・マティス。
彼が言うように、バラという固定観念を捨てなければ、本質を描くことは出来ません。
しかし、バラを知らなければ、バラを描くことさえも出来ない。
物事を見るということの苦悩を、感じずにはいられない名言です。
漢方の世界も、全く同じように私にはうつります。
どんなに治療に慣れても、初めて見るかのように。
誰一人として同じ人間はいない。しかし、人間であることに変わりはない。
そういう心持ちが、漢方治療には必要なのです。
・
・
・