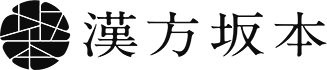「処方に溺れる」という言葉があります。
・
昔、師匠と電話していた時の話。
私はある処方の使い方が分からず、それを師匠にご指導頂いていました。
「この処方はこういう病態に使うべきものだから、このような患者さまに使って良いと思うのですがどうでしょうか?」とか、
「この処方は○○という病に使うべきものなのですよね?」とか、
確かそういう質問をしていた時だったと思います。
その時、師匠は私にこう言われました。
「坂本くん、処方の中に病態は無いよ」と。
・
処方の中に病態は無い。この言葉は、当時の私には到底理解できるものではありませんでした。
処方の中にこそ、それを用いるべき適応病態があり、
それを理解することで始めてその処方が使えるようになると思っていたからです。
人と処方とを繋げる。それが私たち臨床家の務めであると信じていました。
しかし今なら分かります。それは間違いです。
臨床家は人と処方とを繋げているのではありません。
人の中から病態を見出し、その病態をもって処方という形を導いている。
だから極論を言うならば、処方は何だって良いのです。
正確に病態が掴めているのであれば、治し方はどのような形であろうともかまわない。
同じ病態であったとしても、ある人は桂枝湯(けいしとう)を用い、ある人は六君子湯(りっくんしとう)を使う。
観るべきものは人中の病態であり、処方ではないということ。
そして処方は解答ではなく、あくまでも手法。
形は違っても病態に正しく合わせることが出来るのであれば、そのレシピは何だって良いのです。
・
この考えはやや難しいかもしれません。
しかし臨床家であれば必ず意識しなければいけない思考だと思います。
正直、腕の差を決定づけると言っても過言ではありません。
処方の中に病態は無いという考え方は、感覚として骨の髄にまで染み込ませなければなりません。
なぜならば、分かっていても癖のようにやってしまうから。
ある病にこの処方が効いた。それを聞くと、無意識のうちに同じ病を得た人とその処方とを繋げたくなります。
それでは決して効きません。もし効いたとしても、まぐれにしか過ぎません。
同じ病の人でも、誰一人として同じ病態の人はいないからです。
・
病を得た人と処方とを直結する。この考え方は日本漢方の伝統的な手法です。
「方証相対(ほうしょうそうたい)」
この漢方理論の根底にあるものが、当にそれを物語っています。
ただし忘れてはいけません。
「方証相対」とは「昭和の漢方家たちが、漢方を知らない医療者に向けて、分かりやすく、使いやすく説明するために引き合いに出した概念」だということを。
つまり漢方初学者にとっての、初歩概念といっても良いもの。
賛否あると理解はしていますが、あえて初歩概念だと、ここでは言っておきます。
○○湯の証があるから○○湯を用いる。そんな概念は役に立ちません。
そうとは分かっていても、無意識のうちにそう考えてしまう臨床家は多いものです。
ある意味で「方証相対」という魔法の言葉は、それほどまでに日本に浸透した言葉なのだとも言えます。
・
「処方に溺れ、証に溺れる」
昭和時代から時を経て、今はもう令和です。
そろそろ、この矛盾から脱却しても良い時代なのではないでしょうか。
・
・
・