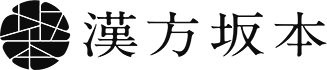今日の話は、
ふーん、という程度にお読みくださいませ。
・
先代である私の父は、66歳で逝った。
亡くなるには、まだ早い年齢だったと思う。
息子の私から見て、苛烈な性格だった父は、
その死に際も苛烈だった。花火のように散る、急に逝ってしまったという感じだった。
腰の内部にできた膿瘍に気付かず、
菌が全身へと回り敗血症を起こした。
その闘病はとても激しくて、
強力に続く発熱は、体を蝕むという表現がぴったりだった。
ICU(集中治療室)に入って、
2週間足らずで危篤に陥った。
結局そのまま逝ってしまったのだけれども、
その逝き方はまるで、自分から突っ走ったような、
もしくは生命の火を爆発させたような、
少し言い方は変かもしれないけれど、そんな積極的な死に様だった。
・
危篤に陥る前の話。
まだ、病室のベットで話ができていた時のこと。
とはいえ父はすでに衰弱の一途をたどっていて、
自分で体を動かすことさえ、ままならない状態だった。
そんな時でも私と父は、漢方のことしかする話がなくて、
もし今の父の病状だったら、どんな漢方薬を出すのか、
この期に及んで、そんな話になった。
実際これはまったくの戯言で、
ICUに入るような状況ならば、漢方の範疇をとうに超えている。
だから昔の人、未だ西洋医学が無い時代の人たちならば、
いったいどんな治療をしていたのかなぁという、想像の話をしていた。
父の体調は、
すでに高熱はおさまっているといっても、
長く続く熱と、節々の痛みで、強力な感染症の真っただ中である。
当然、食事は食べられない。
栄養剤と抗生剤の点滴で、何とか持たせているという体である。
消耗で体の肉は削げ落ち、
体重が激減して、動かせるのは指くらいのもの。
声もか細く、自分で頭を動かすこともままならない。
一見して死の淵、といった様子であった。
・
この状態を漢方で言うならば、
明らかに「少陰病」だろう。
人を支える根源たる生命の火、
その衰退が起こるステージを、少陰病という。
この段階、『傷寒論』においては、
命の火を賦活させる薬が用意されている。
その筆頭たる薬が、四逆湯。
もしくは茯苓四逆湯といったところである。
おおよそ四逆湯の類。その範疇からは外れることはない。
そう感じた私は、他の道無しと思い、
「もうここまで老いぼれたなら、茯四でしょうよ」と、
苦笑いで父に伝えた。
それを聞いた父は、横目でチラッと私を見ると、
天井を見てから、スーッと目を閉じた。
しばらく経ってから、ゆっくりと口を動かすと、
「だいおう、しゃちゅう、がん」
と、小さく呟いた。
・
大黄䗪虫丸。
肺腑を突かれた気がした。
瘀血の重剤。
下剤を含む、強い駆瘀血剤である。
乾血労といわれる、凝固した血液のイメージ。
そのために血流循環がすこぶる悪く、虚労羸痩を起こした時に使う薬。
父の状態に、大黄䗪虫丸?
少なくとも今の父に、下剤を使う勇気は、私には無い。
想定外の処方だった。
しかし、それでもどこか、ハッとさせられた。
確かに大黄䗪虫丸という一手も、
無くはない。そう、思わされた。
危篤間近の父。
その人が呟いた、想像し得なかった処方。
生命の火の乏しい時に、大黄を使うという選択。
私にはなかった。
自分の中にある、少陰病の定義が揺らいだ。
・
誰にでも『傷寒論』は読める。
漢文で書いてはあるものの、解説書がいくらでも出回っている。
それを横に置きながらであれば、誰にでも読める。
しかし『傷寒論』を完全に読み解いた人は、今までの歴史上、一人もいない。
なぜ少陰病に、大承気湯が書かれているのか。
例えばなぜ陽明病に、麻黄湯が書かれているのか。
『傷寒論』の骨格、六経病とは一体何なのか。
単なる「病のステージ」だとは、私には思えなくなった。
『傷寒論』の著者、張仲景。
燃え尽きる命を、多く目にしてきた聖医。
生と死のゆらぎを、何度も目にしてきたに違いない。
その意図を理解するためには、ただ読むだけでは到底及ばない。
父が伝えた、最期の一手。
私が先代から受けた、最後の教えである。
その会話の後、おそよ一週間後に、
父はこの世を去る。虚空から花火が消えるような、
余韻の残る、散り方だった。
(命日・1月19日を偲んで)
・
・
・