■生薬ラテン名
PINELLIAE TUBER
■基原
カラスビシャク Pinellia ternata Breitenbach(Araceae)のコルク層を除いた塊茎
■配合処方例
小柴胡湯
大柴胡湯
半夏瀉心湯
温胆湯
など
※生薬の解説は本やネットにいくらでも載っています。基本は大変重要ですので、基礎的な内容を知りたい方はぜひそちらを参照してください。ここではあくまで私の経験からくる「想像・想定」をお話しします。生薬のことを今一歩深く知りたいという方にとって、ご参考になれば幸いです。
半夏(はんげ)
カラスビシャクの塊茎。いわゆる芋です。
咳止め、吐き気止めとして使われることが多い生薬です。
肺や胃に溜まっている水を去るというイメージ。
これを以て半夏は「痰を消す」とか、「痰飲を去る」と言われています。
『金匱要略』でも「半夏を内れて以てその水を去る」と書いてあります。
また半夏を使い過ぎると、体を乾かすと書いてある解説もあります。
これらは東洋医学の常識ではありますが、
私はちょっと違うとな思っています。
・
今の所、私の経験では、
半夏の使い過ぎで粘膜が乾燥していった人を、見たことがありません。
半夏の表面には、シュウ酸カルシウムの針状結晶があります。
そのまま食べるとこれが刺さります。舌が痛くて、地獄の思いをします。
この刺激のせいで、半夏は毒扱いされることがあります。
粘膜を乾かすというのは、この類の話ではないのかと思うのです。
そして煎じてしまえばこの刺激は消えます。
むしろ味も薄くて飲み口も優しい。粘膜を乾燥させるような印象が、私には全くありません。
「半夏は乾かすというが、むしろ粘膜を潤わせているようにさえ思える」と、
父が昔、言っていましたが私も同感です。
半夏は咽の違和感に使われますが、
確かにそれは乾かすというよりも、荒れた粘膜に潤いつけて正常に戻しているようにさえ感じます。
おそらく半夏は水を去るとか、乾かすとか、
そういうことだけでは論じられない生薬だと思います。
主として嘔吐・咳嗽・腹張・咽痛に使われる半夏ですが、
これらの薬能の柱は「水」ではない。むしろ「気」であるように私は感じます。
・
想うに、
半夏は一種の「鎮静薬」として体に効いているフシがあります。
咳を止めるのも、吐き気を止めるのも、
水分代謝を改善して痰飲を除いているからではなく、
身体の興奮状態を緩和させることで、咳や吐き気を沈静化しているという印象があります。
昭和の大家の一人、精神科医であられた相見三郎先生は、
柴胡桂枝湯を頻用する中で、半夏の分量を多くしていたそうです。
また同じく山本巌先生は、半夏を中枢性の鎮咳薬であると説明していた。
身体が起こしている、もしくは起こしやすくなっている興奮を落ち着けているイメージ。
ただし半夏の成分が中枢に効いているというよりは、
おそらく消化管粘膜を通してそのような効果を発現しているのだと思います。
・
半夏をしかるべき場で使うと、興奮がスッと落ち着く現象が起こります。
逆に言えば半夏が適応する人には、ある種の興奮状態を見て取ることができます。
そしてその性質がしばしば使用の目標になります。
ただしその性質は、百聞は一見に如かず。経験するしかありません。
独特の気配を呈する興奮で、
神経質さの中に、むっつりとした粘着質な印象があります。
温胆湯・大柴胡湯・半夏瀉心湯など、半夏を重く使用するべき人には少なからずそういう印象があり、
さらに上半身、特に胸・肩・首・顎・頬がパンと浮腫んでいる人が多いのも特徴です。
興奮によってせり上がった水を、下に落としていくという考え方。
半夏の去水は、おそらく「降気・下気」を主としています。
浅田宗伯曰く「能く気道を通じて而して水を去る」と。
金匱黄耆建中湯の条に曰く「肺虚損不足、気を補うは半夏を加ふ」と。
私には同じことを言っているように聞こえます。
息が深く吸える。
回答は多分、単純な着想の中にあるのだと思います。
・
・
・
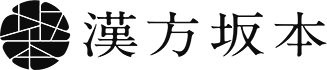

 漢方坂本/坂本壮一郎|note
漢方坂本/坂本壮一郎|note