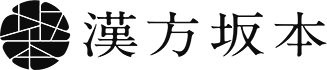十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)・後編
<目次>
補中益気湯と十全大補湯
古方から捉える十全大補湯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※前編までのあらすじ
補気剤と補血剤、両方を備える十全大補湯。
気血双補の疲労回復薬として大変有名な処方です。
ただし気・血はそもそも東洋医学でいう所の概念にしか過ぎず、気虚も血虚も分かるようでいて、実際の臨床ではなかなか捉えにくいものです。
そこで補気剤を「薄いスープ」、補血剤を「濃いスープ」として、補気・補血を「濃淡」として捉えてみる。
すると十全大補湯の使い方が少し分かりやすくなります。
すなわち「体力の回復に補気剤だけでは薄い、少し濃くしてあげた方が効きそうだな」というニュアンスで十全大補湯を使ってみると、不思議と効果的な場合が多いのです。
→前編:【漢方処方解説】十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)・前編
補中益気湯と十全大補湯
体力を回復して疲労を去る補剤。その有名処方の一つである十全大補湯。
そして本方と同じく補剤として有名なのが補中益気湯(ほちゅうえっきとう)です。
両者はしばしば、その使い分けが議論されます。
十全大補湯は気虚と血虚との両方をカバーして補うことができる薬です。
そして補中益気湯は補気剤として有名、すなわち両者の違いは補血作用の有無、ということになりそうです。
しかし、そもそも気虚・血虚というのは概念にしか過ぎず、捉えようによっていくらでもその内容が変わってしまいます。
そこで補気・補血を「濃淡」として捉えてみる。
すると、単に気血を論じるよりも分かりやすくなります。
補気剤は薄いスープ、補血剤は濃いスープです。この薬の濃い・薄いは些細なことのようでいて、臨床においては大変重要です。
この薬の「濃淡」という視点から、本方と補中益気湯との使い分けを説明したいと思います。
・
補気剤として有名な補中益気湯は、実は当帰を含みやや補血の要素を持つ薬でもあります。
しかし、十全大補湯に比べれば明らかに補気寄りです。つまり補中益気湯の方が薄い薬であるといえます。
十全大補湯はより濃く、深い味を持つスープです。料理で言えば中華やフレンチ、イタリアンといった重さを持つ薬です。
ではそういう重さを持つ薬が良く効く人とは、いったいどのようなタイプなのでしょうか。
・
例えば平素は丈夫な人、もともと胃腸の強い人が、大病をして消耗し体が削げた。ただし未だに食欲はあり、少々下痢などしていても、お腹が減って食べたいという、食欲が落ちないタイプ。
そういう人なのであれば、薄い味のスープよりも濃く深い味わいのスープを好みます。味も何もない薄味の薬では、刺激が少なすぎて体が満足できません。
このように体力が消耗している人の中には、濃い味のスープの方が効きそうだなという人がいます。そういう人に使うと良く効くのが十全大補湯です。単純な補気剤だけでは淡すぎるという場合に、十全大補湯を使うべき場があります。
一方で、疲労・消耗と伴に胃腸が弱ってきてしまった人。例えば夏場で体力を失い、疲れやすくなるとともに食欲も落ちてしまった人。
そういう人であれば、中華やフレンチを食べさせようと思っても当然食べることはできません。無理に食べさせれば胃もたれや下痢を起こします。重く濃い十全大補湯ではなく、薄く優しい味のスープである補中益気湯の方が良く効いてくれます。
・
補気と補血、その解釈は「濃淡」というイメージに置き換えると比較的分かりやすくなります。
無理やり曖昧な概念で捉えようとせず、この人だったら少々濃くても飲めるだろうから十全を使おうかくらいに考えた方が迷いが少なくなります。
そして、そういう迷いが少ない治療はしばしば効果を上げやすいものです。
滋養の濃い方が効きやすいのか、もしくは薄くサッパリしている方が滲み込みやすいのか。基本的には食事と一緒です。そういう尺度で考えれば、十全大補湯は比較的使いやすい薬です。
古方から捉える十全大補湯
さて、ここまでが私からみた十全大補湯の基本です。
基本はあくまで基本。十全大補湯の理解は、ここからさらにその先があります。
ただし、ここから先はやや専門的な内容になりますので、さっと流す程度にとどめます。
他の方剤と同じように、理解を深めるために大切なのは歴史です。極々簡単に説明していきたいと思います。
・
十全大補湯は気血双補の剤です。四君子湯と四物湯の合方を八陳湯といい、そこに黄耆と桂皮を加えれば十全大補湯になります。
補気の四君と補血の四物、そこに二を足して、気血双補の十全大補湯。パズルのように分かりやすい組み合わせですが、この四君も四物も十全も、全て中国宗代に書かれた『太平恵民和剤局方』という書物によってはじめて世に紹介されました。
この本が書かれた宋という時代は、印刷技術の発明に代表されるようにさまざまな分野で文化の合理化が進んだ時代です。医学においてもその流れがあり、誰しもが分かりやすく使いやすい理論を積み上げていくことが時代の流行りでした。
補気や補血という考え方は、まさにその流れの中で作り上げられた概念です。つまり十全大補湯を気血双補の剤と捉える解釈は、宋代以降に流行った合理的解釈によるものを基盤としています。
しかし十全大補湯は、実は宗よりも前の時代にすでに存在していました。
唐代に書かれた『千金方』、その中に十全大補湯と全く同じ構成を持つ「黄耆茯苓湯」という処方が掲載されています。
この時代にはまだ四君子湯や四物湯は存在していません。すなわち補気・補血という概念が存在する前からすでに十全大補湯と同じ薬が存在していたことになります。
ということは、この時代ではまだ気血双補という考え方では使われていないはずです。ではどういう使い方がされていたのか。
おそらく唐代以前から続いていた解釈、すなわち東洋医学の聖典である漢代『傷寒・金匱』の考え方が反映されていたのではないかと私は考えています。
・
『千金方』によれば、この黄耆茯苓湯も十全大補湯と同じように身体の虚状・疲労に使う薬です。
そして当時の疲労の捉え方は、漢代から続く「虚労」という概念が基礎になっています。
さらに黄耆茯苓湯は、この虚労の流れの中で使われるある一つの薬に良く似ています。黄耆建中湯です。
つまり十全大補湯(黄耆茯苓湯)は、四物湯や四君子湯とは別に、本来はこの黄耆建中湯が原型となって作られた方剤だと推測できます。
であるならば、十全大補湯は「虚労」という概念の中で運用されることが本来の使い方のはずです。
もっと言えば、「虚労」を正しく捉えることができれば、十全大補湯はより的確かつ効率的に効かせることが可能になります。
「虚労」とは人が疲労を深めていく流れと、そこに対応し得る処方・治療法を述べた概念です。
その流れの中で十全大補湯がどの位置に属するのか。それを紐解くことが、本方を正しく運用する際の決め手になります。
・
ここからは、私の考えとその結論だけを述べていきます。
まず十全大補湯は黄耆建中湯を祖としますが、両者は近しいようで実は違う、同じ段階で使う薬でありません。
黄耆建中湯はその薬能が腹中にかかる一方で、十全大補湯は心肺にかかります。
そういう意味で十全大補湯は炙甘草湯に近く、後の時代になるとより心肺への効能が負荷されることで人参養栄湯へと改良されていきます。
したがって十全大補湯は古人が「肺痿」や「肺瘍」と呼んだ慢性の呼吸器疾患、例えば気管支拡張症や非結核性抗酸菌症などの病に応用されやすく、効果を発揮しやすい処方です。
ただしその際前に述べたように、補気剤よりも濃い性質を持っていることに注意しなければいけません。
心肺に弱さはあるものの、未だ胃腸にまでは落ちていない。そういう段階において十全大補湯もしくはその変方である人参養栄湯を使うというのが、本来の使い方です。
・
十全大補湯、そして黄耆茯苓湯、さらに人参養栄湯と炙甘草湯。
これらの処方が関連しているとう解釈は、江戸の名医・浅田宗伯によってすでに指摘されている所です。
宗伯の『勿誤薬室方函口訣』に詳しいので是非参照してください。虚労という単語は用いないものの、宗伯は十全などの後世の処方を使用する際にも確実に漢代・古方の考え方を基にしています。
歴史を紐解くことで見えてくる漢方処方の使い方。基本からさらに何歩奥へと理解を進めることができるのか。その差が方剤運用の差となり、さらに治療効果の差になるというのが漢方です。
・
・
・
■病名別解説:「更年期障害」