二十歳のころから本格的に漢方の勉強を始めて、
頭に東洋医学の基礎と素養とを叩きこみ、
そして数年経ったころ、
私にはさぁどんとこい、どんな患者さまにも対応できるぞという自信が芽生えました。
結局この自信は粉々に打ち砕かれます。当然です。
まだこの時は患者さんから相談を受けたことがなく、
時間をかけたとはいえ、未だ机上の勉強だけで作った自信だったからです。
バッティング理論を本で勉強しただけで、未だバッターボックスに立ったことのない人間が、
いくら自信を持って打てると思っても、そんな自信は打ち砕かれて当然です。
ただ、学問というものは本の中でのみ完結可能なある種の到達感が確かにあります。
机上の勉強を練り上げていく中で達成できる技量というものも確かにあると思います。
強いて言えば、あの時の私はそれだけ勉強を積み重ねていたということでしょう。
しかし、やはり医学は実学でなければなりません。
現実の臨床で使えない学問であれば、それをいくら積み重ねたとしても自信に繋げて良いものではありません。
・
では机上では学ぶ事のできない技量とは、いったい何でしょう。
色々とあります。総じて実際に人をみることで初めて得られる経験、といってしまえば確かにそうでしょう。
ただ私はその中でも、知識の質に最も違いが出ると思っています。
例えば、知識には濃淡があります。
もっと言えば、重なりや奥行きがあります。
実際の臨床には、机上の学びでは決して得られない四次元の知識があり、
それらを知るか知らないかで、腕に大きな違いが生まれるのだと感じています。
・
机上の勉強を続けていた時、
あの時の私は、一つ症状を言われればそれを回復し得る処方の名を瞬時に列挙することができました。
頭痛と言われれば呉茱萸湯・川芎茶調散・半夏白朮天麻湯・苓桂朮甘湯・当帰芍薬散・麻黄湯・桂枝湯・云々かんぬんと、
これら処方名とその適応病態とをすぐに想定することができました。知識を頭に刻み込んでいたからです。
しかし、そうできたところで臨床ではあまり役に立ちません。
確かに思い浮かべることが出来ないよりかは出来た方が良いと思います。
しかし、それだければあまり使える情報になっていないのです。
なぜならば、頭の中で列挙される知識には濃淡がないからです。
すべて横一直線。各処方が等価で並んでいる状態。
同じ頻度で起こり、重なることがなく、順序もない。
ということが前提となっています。
それでは現実に起こっている現象に対応することができません。
例えて言えばこういうことです。
頭痛を訴える患者さんがいたとします。
そこに横一直線で並んだ知識を展開しても、決して正解を導くことは出来ません。
まず、漢方ではすべての頭痛を網羅できていません。
当然漢方治療では改善することが難しい頭痛もあります。それを本では教えてくれません。
さらに例えば呉茱萸湯と当帰芍薬散の頭痛は全く別に起こっているとは限りません。
それぞれが伴に内在している可能性があります。
さらにそれが混和せず、別々に重なり合って起こる場合もあります。
すなわち呉茱萸湯と当帰芍薬散の頭痛であることを看破したとしても、それを同時に治療するべきなのか、それとも順序を以て治療するべきなのかを判断しなければなりません。
そしてさらに言えば、全ての処方を頭に描いたとしても、これだと積極的に選択できない場合もあります。
決め手に欠けるというケース。実際の臨床においては、それが当たり前なのです。
何事においても、積極的にそれだと選択できるケースの方が圧倒的に少ない。
私たちは10個の中から1つを選択する場合、その1つを積極的に選んでいるわけではなく、
多くの場合、他の9つを諦めることで結果的に1つを選んでいるのです。
可能性の低さや治療としてのリスク、
また可能性が高かったとしても今がそのタイミングではないといった理由で、
他の9つを諦めているからこそ、1つを選択することができます。
私はこの考え方を持てない治療者は得手にはなれないと思っています。
選択は諦めてこそ可能という考え方。
この考え方をしないということは、頭の中にある知識の中に必ず解答があるという考えに他なりません。
机上の学問の中に必ず解答があると信じて、さぁどんとこいと気構えていたあの頃の私には、
自ずとそういう過信があったのでしょう。
打ち砕かれて当然です。
解答と問題とが無限に広がる医学の中で、
臨床では常に不十分な知識の中でどう戦うのかを求められています。
そこへの意識こそが、机上では学ぶことのできないもの。
そして臨床家が持つべき、知識の質なのです。
・
・
・
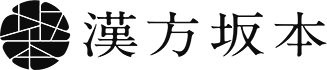

 漢方坂本/坂本壮一郎|note
漢方坂本/坂本壮一郎|note