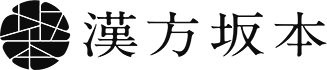呉茱萸湯(ごしゅゆとう)
<目次>
呉茱萸湯の運用と実際 ~基礎編~
呉茱萸湯の運用と実際 ~応用編~
呉茱萸湯の運用と実際 ~まとめ~
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
薬局では呉茱萸は使うな。中島随証先生の言葉です。
使用上気をつけなければいけない薬として有名なのは劇薬に分類されている附子ですが、呉茱萸も相当に効果が鋭く、時に附子以上だと思います。
臨床上、私自身がそう感じるので、中島先生の言葉はそれを示しているのでしょう。
そしてその呉茱萸を主成分とした呉茱萸湯も然り。やはり使い方を間違えてはいけない薬だと思います。
・
ただこの呉茱萸湯は、片頭痛の治療薬として有名であるが故に、頭痛と聞けば呉茱萸湯と、安易に使われている気がしてなりません。
エキス顆粒剤は比較的穏やかなので、それでも良いのかもしれません。しかし一律的な使用では、少なくとも効かせることはできません。
この運用を有名にしたのは、大塚敬節先生の『漢方治療の実際』でしょう。詳しく運用の決め手が書かれています。臨床に則したとても良い解説です。
しかし実際にはそれだけでは足りません。大塚敬節先生が伝えきれなかった文章の行間を、臨床を通して読み取る必要があります。
・
数多の薬の中でも、呉茱萸は特殊な生薬です。私も経験を得て、徐々に、ちょっとずつ、掴むことができるようになりました。
今ではなくてはならない生薬の一つになっています。呉茱萸を使わなければ治らないという病態が、どうしても存在するからです。
そこで今回は、呉茱萸湯の使い方を解説していくのですが、その使い方の答えを示すわけではなく、こういう場において呉茱萸湯は使えるという自身の経験を、基礎編と応用編とに分けて解説していきたいと思います。
あくまで臨床から紐解いていく形です。その方が、本来の漢方治療の形に近いと思います。
呉茱萸湯の運用と実際 ~基礎編~
■頭痛・片頭痛
呉茱萸湯は頭痛の薬。これを有名にさせたのはおそらく大塚敬節先生です。
名著『漢方治療の実際』において提示されています。しかも巻頭、一番最初に頭痛・呉茱萸湯を記載していることから、大塚敬節先生の自身の程が伺えます。
大塚敬節の解説とそのポイントとを要約して記載してみると、呉茱萸湯は以下のような頭痛に効果を発揮すると述べられています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〇頭痛の性質
・発作性のはげしい頭痛に用いる。
・多くは片頭痛の型でくる。
〇併発症状
・発作の激しい時は嘔吐がくる。
・発作が起こるときは、項部の筋肉が収縮するから、肩からくびにかけてひどくこる。左よりも右にくる場合が多く、耳の後ろからこめかみにまで連なる。このくびのこり工合が、この処方を用いる1つの目標になる。この処方を用いる目標のくびのこりは、筋肉の収縮であって、(髄膜炎や悪性脳腫瘍のような)頸部強直ではない。
・発作の時に診察すると、心下部(みぞおち)が膨満し、患者も胃がつまったようだと訴えることが多い。この腹部の状態も、この処方を用いる大切な目標である。
・また発作時には、足がひどく冷える。脈も沈んで遅くなる傾向にある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大塚先生の具体的な経験からくる、臨床に則した的確な口訣です。
私自身もこのヒントから呉茱萸湯を用いて、頭痛を寛解させたことが何度もあります。
併発症状として挙げている、嘔吐・くびのこり・心下部の膨満・足の冷えなどですが、私自身が最も重視しているのは、このうち心下部の膨満です。なぜならば、呉茱萸湯は胃薬としての性質が強いからです。
また発作性の頭痛であるということ。急激に肩・首が拘縮してくる勢いのある頭痛。急激かつ激しく来るというのもポイントで、実際にこういう激しさを目の付け所にすると呉茱萸湯の運用が的確になります。
胃がポイントであるということ。そして急激に激しく起こる頭痛であるということ。
ただし漢方では胃に配慮する頭痛薬は沢山あります。そして片頭痛は大抵が激しくくるものです。
すなわち要を得ているとはいえ、この解説だけでは他薬との鑑別が明確ではありません。故に、さらに詳しく呉茱萸湯の特徴を紐解く必要があります。解説を進めていきましょう。
■胃痛・月経痛
先で述べたように呉茱萸湯は胃薬としての性質が強く、胃痛に良く効きます。
比較的強い痛みを呈するもので、特に冷えて痛む、低気圧で痛む、早食いや食べ過ぎで痛む、月経前や中に痛むという場合に効果を発揮します。
ちなみに呉茱萸湯は月経痛に効く場合もあります。かなり激烈な痛みであっても、時に即効性をもってそれを緩和します。
その際も下腹部痛と同時に胃痛を生じるケースが多く、特に吐き気を催す際に用いて良いことが多いという印象です。
そして呉茱萸の効く痛みでは放散痛が良く見られます。良く起こるのが背中への放散痛。胃や子宮が痛むとともに、しばしば背中へと痛みが波及します。
背中の左にくることが多いことから、古人が「痃癖(げんぺき)」と呼んだ症候に近い印象があります。現代では膵炎治療においてこの病態を想定する場合があり、私は頓用として用いた時に、膵炎による痛みを寛解させた経験があります。
ただし膵炎という特殊な病だけではなく、比較的広く胃痛に用いることができます。しばしばみぞおちが痛み、それが急激で背中に波及し吐き気を伴うという場合。血の気の引くような吐き気です。この時に人参湯や安中散、半夏瀉心湯などとの鑑別が必要になります。
■下痢
呉茱萸湯は胃痛とそれを基本にした吐き気に使う胃薬ですが、同時に下痢を治す薬でもあります。
傷寒論での適応には「吐利」とあります。通常下痢する場合は腹中(臍中心)に痛みがきますが、呉茱萸湯が効く下痢では痛みがみぞおち(心下部)にきます。
下痢を治療している際、さまざまな下痢止めを使っても治らないという場合に、胃薬である呉茱萸湯を選択肢に入れておけるかどうかが重要です。隠れた下痢止めとして、この処方も覚えておかなければいけません。呉茱萸湯でないと治らない下痢というものが、確かに存在します。
そして、冷や汗をかく気配があるような強めの胃痛を起こして下痢をするというのが一つの目標になります。やはり起こり方は急迫的です。食事中、やめておけば良かった最後の一口を食べたら、突然胃痛が起きて下痢するというパターンです。
胃にかかる下痢、という意味ではやはり人参湯に近いのですが、人参湯との鑑別は放散痛を見ます。背中に痛みの気配があるかどうか。通常患者さまは自分から言わないことが多いので、こちらで確認しなければなりません
・
血の引くような、急激な胃痛を中心とし、それに伴う吐き気や下痢、そして背中への放散痛というのが呉茱萸湯を使う際の目の付け所、その基本です。
その際、足首から下が冷える傾向があり、また人によっては頭面に火照りや熱感を覚える方もいます。
大塚敬節先生が提示された頭痛への運用は、背景にこの気配を感じ取った上で使用するとさらに的中率が上がります。
ただし、胃を中心とする胃薬と解釈するだけでは、呉茱萸湯の本質はおそらく掴めません。
本質を掴むためには「呉茱萸」という生薬を理解する必要があります。呉茱萸は特に江戸時代において、その本質を知る人たちによってさらに深い使われ方が為されてきました。
呉茱萸湯の運用と実際 ~応用編~
■脚気衝心(かっけしょうしん)
江戸時代、呉茱萸は「脚気衝心」に使われていました。
「脚気」とはビタミンB1欠乏により心機能の不全を起こす病です。特に突発的な心不全により胸を衝く急迫的な動悸と呼吸困難とを来す病態を「脚気衝心」といい、死に至ることのある怖い病です。
江戸わずらいと言われたほど、かなり流行りました。そしてその突発的な衝心に対応する薬として、しばしば呉茱萸が使われていました。
豁胸湯(かっきょうとう)や息奔湯(そくほんとう)という処方、これら衝心の緩和剤には呉茱萸が入っています。栄養状態の改善により今でこそ見なくなった病気ではありますが、命の急を要する場において、主成分として使われていたことに呉茱萸の本質を感じることができます。
・
江戸の名医・浅田宗伯は呉茱萸をこう評しています。「驅陰の捷方、救急の霊品なり」と。
ここからは私の想像ですが、呉茱萸は人体が何らかの危急状態を呈した際に起こす、一種の興奮・緊張状態に適応する薬であると感じています。
危急状態とはおそらく筋活動の不全で、心筋や消化管平滑筋、血管平滑筋などが一時的に不全となる、そしてその際に体はそれを是正しようと急迫的反応を起こし、その表れとして頭痛や吐き気や下痢、呼吸困難を生じる。呉茱萸はこれらの筋活動を迅速に是正しながら、身体が起こすカウンター、急迫的反応を鎮めるという薬能があるのではないかと感じています。つまり呉茱萸の本旨はその薬能の敏捷さにあり、緊急の状態に陥った体に早く、鋭く、響かせることが出来るという点にこそ、呉茱萸の意義があるように感じられます。
そしてその急迫的反応の多くは上半身に起こります。胸や背中、喉や目、そして面部や頭部、人によっては過剰な興奮状態が起こり、そこに熱感さえも伴うことがあります。
そういう目で見ると、呉茱萸湯の応用範囲が少し広がります。胃にかかわらずとも、突発的に起こる上半身の症状に使って良い時があります。
■心臓性喘息
例えば心臓性喘息。
通常の喘息(気管支喘息)は気道に炎症から浮腫を起こすことで、空気の通り道が狭まり呼吸困難や咳を起こします。しかし、肺の問題ではなく心臓の問題としても呼吸困難を起こすことがあります。これを心臓性喘息といい、通常の喘息治療を行うと悪化させてしまうことがあるため注意を要します。
漢方においても気管支喘息とは異なる処方をもって対応しなければなりません。この辺りの鑑別は江戸時代から行われていました。先で述べた呉茱萸を主薬とした息奔湯などが適応します。したがって現代においても心臓性喘息に呉茱萸湯を使うケースを想定することができます。
■パニック障害
さらにパニック障害。
心理的な要因をきっかけとして、急迫的に動悸と過呼吸を起こす病です。
脚気衝心や心臓性喘息と言った心機能の弱りから来るものとは全く別の病態ではあるものの、着眼点は似ています。適応の場はそれほど多くはありませんが、応用できるときがあります。
例えば『肘後備急方』の「奔豚湯(ほんとんとう)」などがその片鱗を窺わせます。ただしあくまで応用という形。どちらかと言えば、パニック障害の中でもマイナな病態に位置付けられると思います。
■ホットフラッシュ・酒さ・酒さ様皮膚炎
また更年期に伴うホットフラッシュ、さらに寒暖差により起こる酒さ・酒さ様皮膚炎など。
使用する頻度としては決して多くはありません。しかし人体各所の筋肉活動の不調和からくる上半身への突発的な興奮状態という視点で見た時に、ズバリと的中するときがあります。
特に呉茱萸湯を使う場合は、柴胡剤との相性が良いと感じられるケースがあります。主として呉茱萸湯を使うのではなく、柴胡剤で呉茱萸を薄めるという手法です。
ただし呉茱萸は切れ味が鋭く、間違える時は激しく間違えます。この手法は安易に使って良いものでは無いということを重々知っておく必要があります。
呉茱萸湯の運用と実際 ~まとめ~
思えば呉茱萸は不思議な生薬です。まず味が独特です。
辛味と苦味とが共存する生薬であるということが珍しい。
辛味は通常体を温めます。苦味は逆で、体を冷まします。
この両極端な味を共存させているというのが、呉茱萸の薬能の核であるように感じます。他の生薬にはない、一種独特の薬能はこの味にこそヒントがあるように感じるのです。
不思議な生薬ではありますが、ただ考えてみれば人間だって同じです。
人は冷えると冷えっぱなしには決してなりません。必ず体を温めようとする力が、自然と湧き出します。
例えば手を氷水に入れれば当然冷えます。キンキンに冷えてのち、急に氷水から手を出すと、今後はその手が火照ってきます。氷水に入れなかった手よりも暖かくなってきます。
呉茱萸が持つ辛味と苦味も、そういう体の働きに似ています。この意味で言えば、呉茱萸の働きは「命を帯びた薬能」だと言えるかも知れません。
・
呉茱萸湯の使い方にはコツがあります。
それは一種独特の着眼点によりなされるものです。
その独特さを、東洋医学では様々な形で表現してきました。逆冷(ぎゃくれい)、厥陰(けっちん)、中寒(ちゅうかん)などがその類です。
そして、歴代の漢方家がこの方剤をどう応用してきたのか。呉茱萸湯のみならず、呉茱萸を核とした処方の運用にまで視点を広げてみる。
そこで得た着想を、実際の臨床で確かめてみる。
なるほど、と感じたならばその時から、この方剤の深層が薄紙が剥がれるように明らかになっていきます。
・
・
・
■病名別解説:「頭痛・片頭痛」
■病名別解説:「月経痛(生理痛)・月経困難症」