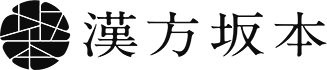薬を出す者にとって、治療とは恐怖である。
改善しなければならないというプレッシャー。
間違えれば害を及ぼす。
病と対峙する時、治療者には常にそういう恐怖がつきまとう。
私が一番最初に診たのは、風邪の患者さまだった。
先代である父に「やってみろ」と言われ担当させて頂いたのだか、
その時は恐怖で頭が真っ白になった。
患者さまの体調も、そしてその心境も、まったく斟酌できない自分がいた。
この時の患者さまには非常に申し訳ないことをした。後悔の念しかない。
経験を重ね、今現在の私はその恐怖をどうにか腹の底にしまうことが出来るようになってきている。
ただ、やはり治療とは恐怖であり、常に緊張との駆け引きであることには変わりない。
今でもそのことを思い出す。私にはそういう症例がある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15歳の女の子。
中学生から高校生への過渡期。
過呼吸が起こり目の前が真っ暗になるという。
昔から立ちくらみが強く起こり、最近になってそれが益々ひどくなった。
彼女はクールだった。性格がだ。
淡々としているというか、それほど苦しむ様子がないというか、若いながらも達観した物腰があった。
体調不良を押して学校には行っていた。おそらく苦悶の表情は家族にしか見せていなかったと思う。
選択した漢方薬で、調子は日に日に良くなっていった。
成長期では一度良くなっても繰り替えすことが多い。私は調子が悪いと感じたら、我慢せずにちゃんと漢方薬を服用するように伝えた。
そして彼女はそれをしっかりと守ってくれた。
しかしある時、異常事態が起きた。
足が動かなくなったのだ。
部活の試合を頑張った後だった。ケガをしたわけでもない。骨折したわけでもない。
なのにまったく立てず、数週間入院した。
その後、退院したが下半身にまったく力が入らず、足を動かすことができない。
そして松葉杖をつきながら、腕の力だけで両足を引きずるようにして来局したのである。
病院では首を傾げられた。
脳も、整形外科的にも、問題はなかった。
こんな状況においてもなお、彼女はいたってクールだった。
しかし私は、内心震えた。この状況を改善する手立てが想像できなかった。
この子の足が、このまま一生動かなかったら。そう思うと恐怖で思考が止まりそうだった。
数日、考えさせてもらった。
そして沈思の末、思う所があった。
それは師匠の教えであり、江戸名医の口訣でもあった。
一点だけである。ただ一点だけ、今まで服用していた薬を私は変化させた。
その結果に一番驚いたのは、私ではないだろうか。
薬を出して3日後、松葉杖無しで普通に歩いてくる笑顔の彼女がいた。
服用した翌日、突然足が動き出したのだという。
朝起きたら、今までが嘘のように歩くことができたのだ。
驚いた。私は心底驚き、そして、彼女と一緒にすごい!!と笑い合った。
ただそのとき、私は同時に理解した。
彼女も不安だったのだ。
常に冷静で、どんな現状でもそれを淡々と受け止めていた。
しかしその時こぼれる彼女の笑顔から、今まで隠し続けたきた不安を垣間見ることができた。
思えば当然のことである。不安で当たり前だった。
私はそのことにさえ気づかぬほど、恐怖で自分を見失っていた。
師匠および現代まで漢方を支えてきてくれた名医たちに、心から感謝するしかなかった。
治療は恐怖との駆け引き。
これは治療に慣れてきた自分にそのことを実感させてくれた症例である。
そして患者さまの心に、また薬方は細部にこそ薬能が宿るということに、気づかされた貴重な経験でもあった。
忘れられない症例である。
・
・
・
■病名別解説:「動悸・息切れ」
■病名別解説:「パニック障害」
■病名別解説:「起立性調節障害」
〇その他の参考症例:参考症例