半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)
<目次>
半夏瀉心湯・創方の意図
半夏瀉心湯・使い所とその応用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
半夏瀉心湯。なかなかの有名処方です。
漢方にご興味のある方ならば、聞いたことがあるかもしれません。
葛根湯ほどではないにしても比較的良く使われます。特に胃腸の薬として有名です。
「心下痞硬」と呼ばれる胃もたれに良く効きます。
胃が詰まった感じとか、むかむかするとか、胃が重いとか、胃が硬いと表現されることもあります。
とにかくみぞおち辺りの症状に効果を発揮する胃薬です。ただし漢方薬には、その他たくさんの胃薬が用意されています。
・
ではいったい他の胃薬とは何が違うのでしょう。
半夏瀉心湯はその生薬構成がやや特殊です。
六君子湯のように単純に気を補う薬ではありません。
また人参湯のように単純に胃腸を温める薬でもありません。
この薬には熱を冷ます寒薬と、体を温める温薬とが同時に入っています。
それが本方の分かりにくさです。解説では上熱下寒とか寒熱錯雑とかいろいろと言われていますが、それがまた分かりにくく理解を妨げています。
そこで今回は、本方運用のポイントを端的に解説していきたいと思います。
なぜ分かりにくいのか。結局の所、寒温で考えるから分かりにくいのです。
もっと単純に考えてみる。
例の如く、創方の意図を探っていきたいと思います。
半夏瀉心湯・創方の意図
半夏瀉心湯を構成している生薬のうち、この処方の核は「黄連」、そして「黄芩」です。
黄芩・黄連を同時に内包する処方を「芩連剤」といいます。本方はその代表的な方剤です。
まず黄連と大黄の二つのみで構成された処方を「大黄黄連瀉心湯」といいます。そしてこの方剤を基本に、黄連が主となって構成された処方を「瀉心湯類」といいます。
この大黄黄連瀉心湯が半夏瀉心湯のプロトタイプです。そして大黄黄連瀉心湯は心下(みぞおち・胃部)の痞えを取る薬であることから、「黄連」を配合した瀉心湯類は胃薬として使われる傾向があります。
さらに「黄芩」も胃薬です。江戸の名医・吉益東洞はその著書『薬徴』において、「黄芩は単に心下(胃部)の痞えを取る薬とだけ考えれば良い」と示しています。
すなわち半夏瀉心湯は「黄連・黄芩を配した胃薬」であるということが最大の特徴です。
では黄連・黄芩は胃薬としてどのようなを性質を持つのでしょうか。
・
黄連・黄芩は「苦み」の強い生薬です。
そしてそもそも苦味は胃薬としての効能を持ちます。
いわゆる苦味健胃薬です。漢方では様々な苦味を有する胃薬があり、これらは比較的即効性が高いという特徴があります。
例えば熊胆やキハダやセンブリ。単に食べ過ぎた程度の胃もたれであれば、これらは少量でも直ぐに効果を発揮します。
そして苦味を主成分とした黄連・黄芩剤にもそういう効果があります。さらにこれらは殺菌作用があるため、感染症による重めの胃腸障害にも使うことができます。
ただし、これらの薬にも欠点はあります。
薬の性質としてやや胃に負担をかけることがあります。
苦味の胃腸薬にもいろいろあり、白朮のように胃腸が弱い方でも問題のないものもあります。
しかし黄芩・黄連は違います。使う分量にもよりますが、性質としては胃に重く当たる可能性があります。
ただし胃腸が弱い人でも黄芩・黄連を必要とする胃腸症状は起こります。
むしろ胃腸が弱い人ほど胃もたれしやすいため、黄芩・黄連を使うケースはむしろ多くなるとも言えます。
そのためこの黄芩・黄連を、胃腸の弱い人でも問題なく飲めるようにはできないだろうか。
そう考えて出来上がった処方、それが半夏瀉心湯です。
・
半夏瀉心湯創方の意図、その一つは黄芩・黄連を胃腸の弱い人でも飲めるようにするという点にあります。
具体的には他の薬を加えることで芩連の重さを緩和させます。これは漢方ではしばしば用いられる手段でもあります。
例えば生姜・甘草・大棗などはこの目的で良く使われます。薬味でスープの味を調えるようなイメージです。
ただし半夏瀉心湯ではやや重めの生薬・黄芩・黄連を緩和させなければなりません。
したがって生姜ではなくより辛味の強い乾姜にして、胃腸の動きを積極的に促すようにします。
黄芩・黄連は寒薬、乾姜は温薬です。
これを理由に半夏瀉心湯は、寒と熱とが錯雑している病態に使うなどと解説されています。
正直に言って非常に分かりにくい説明です。
そうではなくもっと単純に考える。則ち半夏瀉心湯はあくまで黄芩・黄連の胃への負担や冷えを軽減するために、生姜ではなく乾姜を使わざるを得なかったと考えます。
そう考えると、半夏瀉心湯は「芩連で治る胃腸症状を取る薬」であると単純に言えます。
薬能の中心は黄芩・黄連こそが全て。乾姜などその他の生薬は、ひとまずこの芩連の負担を軽減するために入れられていると割り切ってしまう。
すなわち芩連の使い方、どのような症状に効くのかさえ捉えることができれば、半夏瀉心湯を的確に使えるようになります。
では具体的にみていましょう。
半夏瀉心湯・使い所とその応用
まず半夏瀉心湯は胃腸薬ではありますが、食べる意欲さえもないというような胃腸の弱さを回復させる薬ではありません。
そもそも黄芩・黄連を飲める人です。つまり食べることはできるし、その意欲もある。むしろ、食べたことで胃が疲れている人。「自分の胃腸の強さに見合わない食べ方によって生じた胃もたれ」を回復させる薬です。
胃にいつまでも食べ物が残っているという印象です。そのような人は口内炎ができやすく、かつ舌の奥にべったりと厚い苔が付くことが多いものです。
また腸にも食事がいつまでも残って溜まっている。だからゴロゴロと音がなったり腹が張ったり、またガスや便の匂いがきつく、便がトイレにべったりとこびりつく傾向も出てきます。
このような胃腸症状を漢方では「湿熱」と呼びますが、湿熱云々を考えなくても、単に胃腸に食事が長く留まっていれば舌苔は厚くなり便やガスの匂いは強くなります。
黄芩・黄連はこういった消化の停滞による胃腸の負担を消すという印象があります。すなわち食べられない状態に使うのではなく、あくまで食べる力があり、食べたものが消化管にいつまでも残っていて胃腸が疲れている状態です。
そしてやや胃腸の活動に弱りが見えている、すなわち食べ過ぎがたたっていよいよ胃がもたれて食欲がないという人。つまり黄芩黄連の重さをやや緩和しながら飲ませたいと感じる人です。そういう場合に使うのが半夏瀉心湯です。
自分の胃腸の強さに見合わない食事内容・食事量・食べ方によって、胃腸が疲れていつまでも食事が消化できていない状態。そこに半夏瀉心湯は効きます。
そもそも食べる力が弱いという場合であれば六君子湯の方が良いでしょう。また明らかに胃腸が冷えて調子悪いという人であれば、人参湯や安中散を使うべきです。
・
このように黄芩・黄連が適応する胃腸症状に使う。これが本方使い所の大前提です。
ただし使い所の見極めは他にもあります。応用として、半夏瀉心湯は「自律神経失調」に効きます。
大黄黄連瀉心湯に黄芩を加えると、三黄瀉心湯になります。
この処方は興奮性の鼻血や吐血を治す薬として作られました。
さらに漢方では心下(胃部)は自律神経の中枢だと捉えているフシがあります。
すなわち黄連・黄芩を配し心下に効く本方は、自律神経の不安定さを安定させる効能をあわせっています。
そのため本方は過敏性腸症候群のような自律神経の緊張が胃腸に来るというケースでしばしば使われます。
また不眠やイライラ、のぼせなどにも使われます。食生活が乱れている中で起こる自律神経失調というのがポイントで、そのような目で見ていると本方の使い所は大変多く、さらに効果を発揮することが多いものです。
ちなみに本方が効きそうな人には、その特徴があります。
これはお会いして話を聴いていると、その人からの印象として感じるものです。
半夏瀉心湯が効く精神症状は、緊張というより不安や興奮という形で出ます。またその印象として、こだわりの非常に強いむっつりとした印象を受けます。
この辺りは言葉で説明することが難しく、経験を要する所です。
ただしこの半夏瀉心湯適応者特有の印象は経験しているうちに明確に分かるようになります。そして、それががしばしば本方適応の決め手になります。
・
・
・
■病名別解説:「下痢」
■病名別解説:「過敏性腸症候群」
■病名別解説:「自律神経失調症」
■病名別解説:「不眠症・睡眠障害」
■病名別解説:「ニキビ・尋常性ざ瘡」
・
東洋医学をさらに詳しく↓
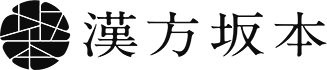


 漢方坂本/坂本壮一郎|note
漢方坂本/坂本壮一郎|note